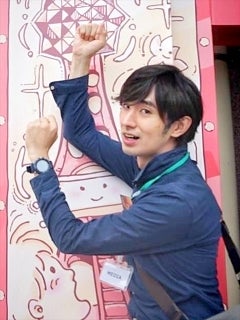健康診断で気にしたい項目が、1. 血糖値、2. 血圧、3. 肝機能、4. 脂質、5. 尿酸値。もし健康診断で引っかかってしまった場合、どうすれば良いのだろうか?
そこで本シリーズでは、RIZAPが蓄える「特定保健指導」の知見をもとに、日常生活で実践できる食事法・運動法を紹介していきたい。連載の第3回目は「肝機能」。
話を聞いたのは、RIZAP法人事業本部で保険者トレーナーユニットに所属する市川菜津美さん。管理栄養士の資格を持ち、医療分野を含む幅広い知見からアドバイスできる立場にある。現在は、健診結果に基づいて生活習慣の改善を促す「保健指導」の業務を担当する。
同社の特定保健指導は、生活習慣改善をサポートするオンラインプログラムで、各個人にあわせた食事法や効率の良い運動法などを提案している。「RIZAPでは、お客様の生活習慣を3カ月で改善するプランを提供しています。私もお客様につきっきりで支援しています」と、笑顔で話す市川さん。
■肝機能項目で引っかかったら…?
――健康診断で肝機能の項目で引っかかってしまいました。どんなリスクがありますか?
肝臓の周りに脂肪がつき過ぎてしまう状態のことを「脂肪肝」と言います。またこれとは別に、お酒を飲み過ぎることで肝臓に炎症が起こる「アルコール性肝炎」もあります。
脂肪肝やアルコール性肝炎は、肝硬変や肝臓がんにつながるリスクが高いため、注意が必要です。
――その原因は?
脂肪肝に関しては、脂質の高い食事を続けた結果、カロリーや糖質の摂取し過ぎとなり、肝臓の周りに脂肪がついてしまったことが考えられます。脂っこい料理が好きな人などは、特に注意が必要です。
先ほどもお伝えしましたが、アルコール性肝炎に関しては、お酒の飲み過ぎが原因です。肝臓にはアルコールを分解する機能があるんですが、働かせ過ぎることで炎症が起きてしまいます。
■対処法は?
――ふだんの生活で気をつけなければいけないことはありますか?
脂肪肝に関しては、エネルギーを摂り過ぎない、適切な量の栄養を摂取する、ということを意識してください。例えば健康のためにタンパク質を摂取するにしても、大事になるのは基礎代謝とのバランスです。1日の中でどのくらいエネルギーを消費しているか、それに対して食事量はどのくらいか、この釣り合いを考えます。
最近の体重計であれば、基礎代謝が表示されるものも少なくないはずです。実は、基礎代謝量に身体活動レベルに応じた係数を掛け合わせることで、おおよその1日の総消費カロリーが分かります。これに対して、自身は1日に食事でどのくらいのカロリーを摂取しているか、計算してみてください。
アルコール性肝炎については、厚生労働省が「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」(=1日あたりの平均純アルコール摂取量)の指標を示しています。それによれば、男性は1日平均40g以上、女性は1日平均20g以上です。
純アルコール量と言われても、ピンとこないかもしれません。例えば、ビール500mL(アルコール度数5%)で20gです。いまインターネットでも調べることができるので、自身のふだんの純アルコール摂取量がどのくらいか、調べておくと良いと思います。そして適宜、"休肝日"をもうけてみてください。
――たしかに、休肝日は大切ですよね……。
そうですね。また、お酒を飲むときは、たくさんのお水を飲むことをおすすめします。アルコールを解毒する際、肝臓はたくさんの水分を必要とするため、飲んだお酒の1~1.1倍くらいの水分量を意識して摂取してもらえたらと思います。
――運動もした方がいいのでしょうか?
そうですね。筋トレ+有酸素運動が効果的です。基礎代謝を上げて、脂肪を燃焼しやすくしましょう。ここで注意したいのが、ダイエットとの兼ね合いです。
たしかに脂肪肝の改善には体重を減らすことも一定の効果があるのですが、体重を減らそうと糖質の摂取を控えた結果、脳が「糖が足りない」と判断し、肝臓が代わりの糖を合成する"糖新生"を行う可能性があります。そうすると、肝臓を休ませることができないばかりか、逆に負担をかける結果となりますので気をつけましょう。