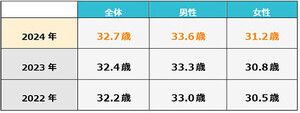『はたらいて、笑おう。』をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングスが4月15日、トークイベント『どうやって“はたらくWell-being”な組織・人を育むんですか?』を開催した。“はたらくWell-being”とは、働くことを通して、その人自身が感じる幸せや満足感のことだ。
登壇者は、元テレビ東京ディレクターで経済動画メディア「ReHacQ」プロデューサーの高橋弘樹氏、AGCでデジタル・イノベーション推進部兼プロフェッショナル・ファシリテーターを務める磯村幸太氏、商工中金ヒューマンデザインで代表取締役を務める松下泰之氏の3名。高橋氏がファシリテーターとなり、会場の参加者の意見も交えながら“はたらくWell-being”について、パネルディスカッションを行った。
■どんな“はたらくWell-being”を実現してきたか
磯村氏が在籍するAGCと、松下氏が以前在籍していた商工組合中央金庫(以下、商工中金)は、ともにパーソルグループが開催している「はたらくWell-being AWARDS 2025」受賞企業だ。
松下氏は、商工中金で管理職を務めた後、同社の子会社である商工中金ヒューマンデザインの代表取締役となり、従業員の幸福度を可視化する「幸せデザインサーベイ」サービスを提供している。
「中小企業では人材不足や離職防止、従業員の定着などが課題。そこで『幸せデザインサーベイ』を通じて、従業員が感じる課題を明確化しています」(松下氏)
では、中小企業に勤めている人のリアルな悩みはどんなことか。参加者からは「従業員と経営者の考えに縮まらない差がある」という意見があった。
「中小企業の中でも、とくにワンマン経営的な企業ではサーベイの点数(従業員の幸福度)が高くないところもあります。その場合社長に気づきを与えるのは難易度が高いけれど、従業員の思いを第三者の立場から伝えると、それも少しずつ変わります。
ある企業では、1回目のサーベイの点数がコミュニケーション・マインド・マネジメントなど、どの要素も低かったんです。ところがサーベイの実施から1年後にはものすごく改善されて『目安箱を置く』『1on1ミーティングを定期的に行う』『賞与のメリハリをつける』など、さまざまな対策に取り組んだそうです。『従業員のWell-beingにつながりました』と言っていただき、やって良かったと感じました」(松下氏)
磯村氏は、素材メーカーであるAGCの企業文化として「自分らしくチャレンジする」という価値観を育ててきた、と言う。
「AGCは素材メーカーなので、社員は基本的にとても真面目な人が多いです。その前提がありつつ、社員がやりたいことにチャレンジする取り組みを推進したり、社員の考えを上司に言えたりする環境を作っています。具体的には、社長と社員が1時間ほど直接対話する機会を年間200回以上設けることで、風通しの良さを重視しています。
そのほか、ジョブチャレンジ(社内副業制度)や、社内で部署を越えたスキルごとのコミュニティ、社外の副業解禁などを実施してきました。自分の新しいアイデアを形にしたり、チャレンジできたりすることで、その成果がメイン業務にもにじみ出て、次のチャレンジにつながっていると思います」(磯村氏)
■副業と“はたらくWell-being”
磯村氏自身も2017年から副業を開始し、それが本業にも良い効果をもたらしたと言う。
「大手メーカーの地方工場で働く人は、兼業で農家をしている人もいます。AGCもその制度があったので、私も自己実現のためにその制度を利用して副業を始めました。今では7つくらいの副業をかけもちしています」(磯村氏)
ファシリテーターの高橋氏も「副業をすると人生のWell-beingがめちゃくちゃ上がる」と賛同。元テレビ東京ディレクターの高橋氏は、テレ東在籍時も副業をしていて、現在はサイバーエージェントの正社員でありながら、tonariの代表取締役社長として会社経営に携わる。
「お金もそうですがそれだけではなく、人生の軸が1.5本や2本になることで、人事異動に左右されないなどの利点を感じます」(高橋氏)
会場の参加者でも「副業をしている」と多数の手が挙がった。
「副業の足場があると、本業で自由に意見を言えるし、本業の収入源があるから副業では嫌な仕事をしなくてよい部分もありますよね。 自分の場合は、一般社団法人パラレルプレーナージャパンの代表をしていて、パラレルキャリアを通じて得たものを生かして、イントレプレナー(社会起業家)として社内で変革を起こす働き方を推進しています。この仕事が本業にもフィードバックでき、いい効果がありました」(磯村氏)
一方で、副業が認められない企業に勤めている参加者からは「本業が楽しく集中できるから、副業禁止でもかまわない」「自分は本業に幸せを感じているから副業をする発想もなかった」といった意見もあった。
■組織におけるウェルビーイングの実現方法
では組織の中でやりたくない仕事に直面したときに、“はたらくWell-being”をどう保つのか。
司会の1人であるパーソルホールディングス はたらくWell-being推進室の中山友希氏は「やりたくない仕事に直面した場合、今の仕事を続けてもいいし、辞めてもいいし、上司に改善を求めてもいい、など自分で選択肢を持てていることが大事」だと話した。
松下氏は、2017年に商工中金の大規模な不正融資が発覚し、業務改善命令を受けた際に事務局員として対応した経験を語った。
「数カ月間、事務局は僕1人で金融庁の検査官から指導を受け続けた期間がありました。当初は深夜までかかる作業もありつらかったですが、1カ月ほどすると検査官の方との関係性が少しずつ変化し、知見を教えていただけるといった経験をしました。人との時間や思いを共有することで、調和が生まれた経験が今の礎になっていると感じています。
当時、周囲の仲間が理解してくれ、支えてくれたことも大きいです。逃げ道も大事ですが、つらい仕事ややりたくない仕事も仲間とともに乗り越えられれば、次の“はたらくWell-being”につながるとも感じます」(松下氏)
磯村氏は、向かない営業職に就いた時期もあったが、大学時代にバックパックで旅した経験から“キャリア自律”を意識できていたという。
「大学を休学してイスラエルを旅していたときに、ある人に『君はいったんレールから外れたんだね、おめでとう』と言われ、自分がそれまでレールに乗っていたことに気づきました。その経験から、自分のキャリアは自分で作るものだと考えるように。私の場合も、入社後に営業の仕事が全然できなかった時代があったけれど『営業は向いていないから次はどうしよう』と部署異動の希望を出すことを考えました。
だからキャリア自律はとても大事。会社にいると大きな物語の中で自分を位置づけてしまいがちですが、それとは別で自分の人生の幸せを考えて、折り合いをつけられたらいいと思います。自分の場合はファシリテーションの仕事がとても楽しいからずっと続けていきたいです。そしてさらに、この分野の専門性を高めることで、会社と交渉できる力にもつながると思います」(磯村氏)
他方、Well-beingには仕事以外で周囲の人と一緒に幸せを感じられることも大事だ、と松下氏は話す。
「仕事で自分がどんな役割や責任を果たしているかも大事だけれど、僕自身は周囲の人と過ごして幸せだと感じたり、周囲の人が笑顔で働いてくれたりすることで十分。Well-beingのハードルが高くないのかもしれません。
僕自身は会社の物語の中にいますが、メンバーに恵まれたおかげで、その中でも自分の好きなように振る舞えていると感じています」(松下氏)
人生で最も多く費やすとも言える“はたらく”時間。だからこそ「自分らしい働き方」や「ほかの居場所」にも目を向けつつ、はたらく時間を心身ともに満たされる状態に近づけることが、体と心の健康や人生の幸福につながるのかもしれないと感じた。