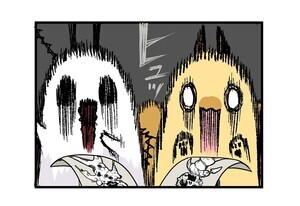2月27日、大阪市中央区のホテルプリムローズ大阪にて、国土交通省近畿運輸局、同神戸運輸監理部が主催する「内航海運活性化セミナー」が開催された。
内航海運は、わが国の国民生活と経済活動を支える重要なライフラインにもかかわらず、有効求人倍率が4倍以上を記録するなど船員不足が深刻だ。国土交通省 近畿運輸局および神戸運輸監理部は、業界全体で課題解消に取り組む機運を高めることを目的に同セミナーを開催。特に若年船員にフォーカスを当て、その教育・育成の現状について、3つのテーマで講演が行われた。その模様をレポートする。
海上輸送の需要は増加、安定・効率輸送の確保に向けた政府の取り組み
開会に先立ち、挨拶をした近畿運輸局次長・池田哲郎氏は、内航海運の人手不足に警鐘を鳴らし、今回のセミナーの意義を訴えた。
第1部の講演は、国土交通省海事局内航課 企画調整官 角野貴優氏による「内航海運による安定・効率輸送の確保に向けた政府の取組等について」。
内航海運は、国内貨物輸送全体の約4割と、石油製品・セメント・金属といった産業基礎物資の約8割を担うのみならず、最近では紙やパルプ品などの製造工業品や農林水産品の貨物輸送も期待されている。さらには、物流2024年問題を受けた船舶へのモーダルシフトや、食料安全保障やインバウンドの受け入れの強化、被災地への復旧・復興支援などに伴い、海上輸送需要が増加。求められる役割は大きくなり、安定的な輸送を確保しなければならない状況にある。
しかしながら、事業者全体の99.7%が中小企業で、内航海運業の営業利益率は全作業と比較して低く、生産年齢人口の減少が見込まれる中で有効求人倍率が4倍以上にまで上昇するなど、課題が山積しているのが現状だ。
そんな中、政府は内航海運業における商習慣の実態調査を行ったうえで「取引環境の改善」「生産性の向上・船員の働き方改革」「海運に求められるニーズへの対応」「海技人材の確保」に関する取り組みを進めている。
内航海運業者と荷主との連携強化を目的とした懇談会の設立や、双方の実務者と行政からなる「安定・効率輸送協議会」や個別部会の開催など、複層的な対話を実施。角野氏は「運賃・用船料算出にあたっての『標準的な考え方』の策定・周知にもつなげていきたい」と力を込めた。
そして、内航海運業界への求職者を増やすには、働き方改革や取引環境改善、生産性向上の取り組み事例を発信することが必要との考えから、昨年2024年6月より「『みんなで創る内航』推進運動」を開始。船員のワークライフバランスを重視した勤務ローテンションの変更や、船内居住環境の整備、船員の労務負担軽減設備の導入などが該当し、計26社が参画している(令和7年1月29日時点)。
近々、創設されたばかりの「内航海運輸送力向上事業補助金」の公募が始まるとのことで、角野氏は「先進的な取り組みに挑戦する際は活用してほしい」と呼びかけた。
また、船舶の空き状況の見える化や新規需要調査を通じ、トラック輸送から船舶輸送への行動変容を促進し、ハードとソフトの両面から海運モーダルシフトの受入環境整備を推進。大型コンテナやシャーシ、DX導入を支援し、新たな需要の掘り起こしを加速している。
最後に、海技人材の確保のあり方に関する検討会の中間とりまとめが紹介され、「海技人材の養成ルートの強化」「海技人材確保の間口の拡充」「海技人材の養成・就業拡大に向けた訴求強化」「海技人材の多様な働き方の促進と職場環境の改善」「新燃料に対応可能な海技人材の確保・育成」の5つの方向性に沿って対応策を講じていかなければならないとの認識が示された。
内航海運の担い手を確保するため、生徒・学生募集に力を注ぐ
第2部の講演は、独立行政法人海技教育機構 学校教育部 募集就職課長 毛利文彦氏による「海上技術学校・海上技術短期大学校における生徒・学生募集」。
海技教育機構は、海上技術短期大学校や海上技術学校を設置・運営し、卒業生の98%が海上就職するなど、若年船員の教育・育成に欠かせない日本最大の船員養成機関だ。
海事関連企業への就職率と海技資格の合格率がともに高い水準を維持しているものの、海上技術短期大学校や海上技術学校の応募者数は減少している。「少子化の影響を受け、平成28年から応募者数は右肩下がり」と毛利氏は明かした。
内航海運の担い手を確保するため、生徒・学生募集に力を注ぐ海技教育機構では、海上技術短期大学校や海上技術学校の入学者にアンケートを実施している。「船員になりたいと思った理由」については「海や船が身近にあった」が約半数を占め、「家族や知り合いが船員」との回答も多く、すでに船や船員に親しみある限られた若者が入学していることが見て取れた。「内航海運の認知度の低さを日頃から痛感している」と話す毛利氏は「船や船員が身近でない若者に対しても内航海運の魅力を伝えていくことが大切だ」と指摘した。
また、「学校を知ったきっかけ」については「家族や知り合い」がトップで、「中学や高校の先生」も上位に入った。海技教育機構では、中学や高校の先生との接触を重視し、教員による積極的な訪問に取り組んでいる。一方で、「SNS」と回答した入学者の割合はわずかにとどまっているため、さらなる情報発信が不可欠と述べた。
「受験の決め手」については「オープンスクール・キャンパス」が最も多く、海上技術短期大学校や海上技術学校では、オープンスクール・キャンパスを出願につなげようと、校内練習船の体験乗船や卒業生である現役船員を招いた講演など、各校が工夫を凝らしている。
この他、特待生制度(海技短大)や奨学金制度といった入学者に対する経済的支援制度を整えたり、大学や専門学校の入試日程を考慮して早い時期に入学者選抜を実施(海技短大)したりするなど、厳しい少子化の最中で試行錯誤を重ねている様子が伝わってきた。
船員の確保・育成のために実習生用の居住区域を拡大した実務型練習船を建造
第3部の講演は、日鉄物流株式会社 内航海運本部 部長代理 福井孝之氏による「実務型練習船『れいめい』による船員育成について」。
実務型練習船「れいめい」の建造を検討し始めたのは2018年10月頃に遡る。その頃から有効求人倍率が高く、現在よりも高齢化が進んでいたため、福井氏は「若手の育成が急務だった」と振り返った。当時、船員の確保・育成を目的に、各事業者が雇用した未経験者の6級海技士免状取得費用の一部を負担する「若年船員育成支援制度」を導入していたそうだが、問題点が浮上。6級海技士免状の取得には、海技学院卒業後6か月間の乗船履歴が必要で、単独当直ができるようになるにはさらに1年以上の乗船訓練が求められる。乗船訓練中は定員外での乗船となるものの、小型貨物船には余剰の部屋が少なく、無資格者を雇用できるほどの余裕がない事業者が多かった。
そこで2018年度に始まった「内航未来創造プランに基づく緩和措置」に基づき、船員の確保・育成のために実習生用の居住区域を拡大した実務型練習船を建造する運びとなった。「れいめい」は総トン数509トン型の船員育成船舶として、鋼材輸送に従事しながら研修ができる。
居住区域は通常7室のところ、12室に。船橋のスペースや食堂を広く取り、シャワーも2箇所設置するなど、実習と居住環境に配慮して設計されているのが特徴だ。
福井氏は「当社基準の省エネ性能を保持しつつ、船橋構造物を四層にすることで実習および居住スペースを拡大し、かつ貨物載貨重量1,500トンを確保したうえで、船員船舶の認定対象となる508総トンに収めることに成功した」と胸を張った。
2020年5月の第1期生から現在実習中の第5期生まで、海技学院在学中の社船実習を計14名が、海技学院終了後の6か月実習を計13名が、それぞれ受けている。実習生の年齢は19歳から44歳まで幅広く、経歴は多岐にわたっているそうだ。
船主からも「きちんと基礎から指導いただける環境は貴重と再認識した」とのコメントが届き、高い評価を得ている。
2024年10月には、指導者研修制度を創設。「れいめい」で使用している指導要領を元に「初任船員教育マニュアル」を作成・配布し、3月には乗船研修を初実施する方向で調整しているという。「今後は若年船員の育成に向け、指導者の指導力の底上げにも貢献したい」と展望を語った。
官民一体となって船員不足の解決へ
閉会の挨拶では、神戸運輸監理部長・臼井謙彰氏が「船員確保と育成体制の強化に取り組み、若年船員の採用促進と定着率向上を図りたい」と締めくくった。
あらゆる産業が直面している人手不足という難題に対し、内航海運では官民一体となって解決に乗り出している。その一端が垣間見えたセミナーだった。