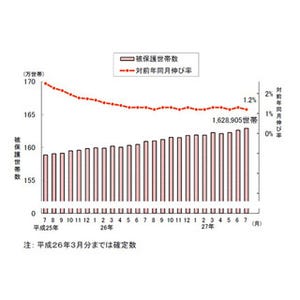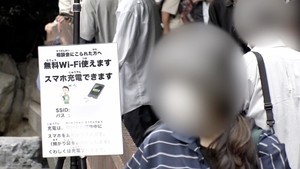日本もったいない食品センターでは、日本における生活困窮世帯の自立支援につながる抜本的な解決への参考にすべく、2024年3月1日~2025年2月28日まで当団体に寄せられた支援要請3,503件を集計した。
このレポートでは「生活困窮世帯がどのような収支で生活しているか」を焦点に、単身世帯・ひとり親世帯・障がいや介護を伴う世帯のそれぞれの収支状況をまとめている。
貧困の状況を1997年と比較(厚生労働省:2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況)すると、貧困線が22万円下がっているにも関わらず、相対的貧困率は0.8%上昇している中、物価上昇は相対的貧困の定義には当てはまらない困窮も浮き彫りになっている。
※「厚生労働省:2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」はこちら
生活困窮世帯の収入
当団体のアンケートでは収入の有無と、収入が有る場合は手取りの金額を質問した。 単身世帯・ひとり親世帯・障がいや介護を伴う世帯ではそれぞれ次のような結果となった。
単身世帯:収入は平均116,584円
単身の生活困窮世帯では5万円~13万円の収入であるケースが多く、1,084世帯中719世帯、66.3%の世帯が5万円~13万円の収入で生活していることがわかった。
ひとり親家庭:収入は平均173,798円
ひとり親家庭の生活困窮世帯では20万円以下の収入であるケースが多く、655世帯中477世帯、72%の世帯が20万円以下の収入で生活していることがわかった。
ひとり親家庭で25万円以上の収入がある生活困窮世帯は78世帯あり、その世帯人数はそれぞれ
世帯人数2名:9世帯
世帯人数3名:22世帯
世帯人数4名以上の多子世帯:47世帯
25万円以上の収入があるひとり親家庭も60%以上は世帯人数が4名以上の多子世帯であることがわかった。
障がいや介護を伴う世帯:収入は平均146,835円
障がいや介護を伴う世帯では5万円~16万円の収入であるケースが多く、512世帯中324世帯、63.2%の世帯が5万円~16万円の収入で生活していることがわかった。
等価可処分所得
可処分所得は厚生労働省によると「所得から所得税、住民税、社会保険料、固定資産税・都市計画税及び自動車税等を差し引いたものであり、「所得」はいわゆる税込みで、「可処分所得」は手取り収入に相当する。」とある。申告ベースの情報にはなるが、当団体のアンケートフォームに記入された収入×12が可処分所得に相当すると考えられる。また、等価可処分所得とは「可処分所得÷√世帯人数」で算出され、貧困線や相対的貧困率の算出に使用される所得となる。
※厚生労働省の用語の定義はこちら
厚生労働省の2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況によると等価可処分所得の中央値は254万円で貧困線は127万円であるため、ひとり親家庭については等価可処分所得の平均は貧困線を超えない数値となった。
※厚生労働省の2022(令和4)年 国民生活基礎調査はこちら
当該団体へ支援要請をされた生活困窮世帯の等価可処分所得は次のような結果となった。
単身世帯:等価可処分所得は平均1,399,009円
単身世帯1,084世帯中520世帯が等価可処分所得127万円以下の世帯。 48.5%が相対的貧困に該当
ひとり親家庭:等価可処分所得は平均1,233,634円
ひとり親家庭655世帯中356世帯が等価可処分所得127万円以下の世帯。 54.3%が相対的貧困に該当
障がいや介護を伴う世帯:等価可処分所得は平均1,289,948円
ひとり親家庭511世帯中270世帯が等価可処分所得127万円以下の世帯。 52.8%が相対的貧困に該当
生活困窮世帯全体としては2,171世帯中1,098世帯が等価可処分所得127万円以下の世帯。
50.5%が相対的貧困世帯に該当した。
支出
当団体のアンケートでは生活の基礎支出として住居費、通信費、光熱費、食費の金額をお尋ねしている。
単身世帯・ひとり親家庭世帯・障がいや介護を伴う世帯ではそれぞれ次のような結果となった。
いずれの世帯でも住居費は大きな乖離は無いものの、光熱費、通信費、食費は単身世帯に比べてひとり親家庭世帯・障がいや介護を伴う世帯では高い傾向が見られた。 合計支出としては単身世帯とひとり親家庭世帯では25,000円以上の差があることがわかった。
エンゲル係数
エンゲル係数は家計の消費支出にしめる食料費の比率を表すもので、総務省の「家計調査」では生活の基礎支出である住居費・通信費・光熱費・食費の他、教育費・教養娯楽費・被服費・保健医療費の合計を消費支出としている。一般にエンゲル係数が低いほど生活水準が高いとされている。
当団体では教育費・教養娯楽費・被服費・保健医療費を集計していない、エンゲル係数そのものではないものの、それに類する係数として生活困窮世帯における生活の基礎支出から食費の比率を集計した。
ここでは「食費割合」と表現する。
総務省「家計調査年報(家計収支編)2023年(令和5年)結果の概要」では総世帯の消費支出は平均247,322円、食料費は71,719円とされており、エンゲル係数を計算すると28.9%となる。
※総務省「家計調査年報(家計収支編)2023年(令和5年)結果の概要」はこちら
当該団体に支援依頼を寄せられた生活困窮世帯の食費割合は平均28.05%となり、内訳は以下のようになる。
単身世帯:食費割合は平均27.12%
ひとり親家庭:食費割合は平均29.60%
障がいや介護を伴う世帯:食費割合は平均28.56%
総務省統計のエンゲル係数と生活困窮世帯の平均的な食費割合を比較したところ、大きな差異は見られませんでした。ただし、生活困窮世帯の食費割合はグラフの形がお椀のような形状になっており、エンゲル係数が低い世帯と高い世帯に大きく分かれることがわかった。
住居費や光熱費に家計が圧迫され食費が不足し支援を要請する家庭と、食費への支出が多く家計が厳しくなり支援を要請する家庭に二極化しているような状況と言える。
光熱費版 エンゲル係数
エンゲル係数が消費支出に占める食費の割合を示すものであるのに対し、光熱費の割合を表す指標は現在のところ存在しない。そのため、仮に「光熱費版 エンゲル係数」と表現する。
それに類似する指標として、当団体が生活困窮世帯における生活の基礎支出から光熱費の比率を集計したものを「光熱費割合」と定義する。
光熱費は食費ほどコントロールが容易ではないが、節約以外にも電力会社の変更などの手段が登場し、電力自由化以前よりも費用を調整しやすくなっている。
総務省「家計調査年報(家計収支編)2023年(令和5年)結果の概要」によると、総世帯の消費支出は平均247,322円、光熱・水道費は19,867円とされており、光熱費版 エンゲル係数を計算すると8.0%となる。
※総務省「家計調査年報(家計収支編)2023年(令和5年)結果の概要」はこちら
当該団体に支援を依頼した生活困窮世帯の光熱費割合は平均18.70%であり、内訳は以下の通りである。
単身世帯:光熱費割合は平均17.28%
ひとり親家庭:光熱費割合は平均20.07%
障がいや介護を伴う世帯:光熱費割合は平均19.64%
総務省統計の光熱費版 エンゲル係数と生活困窮世帯の平均的な光熱費割合を比較すると、10%以上の大きな差異がある。
生活困窮世帯の光熱費割合は、単身世帯では総務省統計の8%近辺に収まる場合もあるが、3,200世帯中2,841世帯(88%)が総務省統計の平均を上回る結果となった。
また、総務省統計による光熱・水道費の平均である19,867円を超える世帯は3,378世帯中1,362世帯(40.3%)にのぼる。今後、生活困窮世帯の自立支援においては、光熱費の抑制や平準化が重要になると考えられる。
通信費版 エンゲル係数
エンゲル係数が消費支出に占める食費の割合を示すのに対し、通信費の割合を表す指標は現在のところ存在しない。そのため、仮に「通信費版 エンゲル係数」と表現する。
それに類似する指標として、当団体が生活困窮世帯における生活の基礎支出から通信費の比率を集計したものを「通信費割合」と定義する。
総務省「家計調査2023」によると、総世帯の消費支出は平均247,322円、通信費は10,310円であり、通信費版 エンゲル係数を計算すると4.1%となる。
※総務省「家計調査2023」はこちら
単身世帯:通信費割合は平均13.13%
ひとり親家庭:通信費割合は平均13.12%
障がいや介護を伴う世帯:通信費割合は平均13.56%
総務省統計の通信費版 エンゲル係数と生活困窮世帯の平均的な通信費割合を比較すると、10%近い大きな差異がある。
生活困窮世帯3,094世帯のうち、1,112世帯(35.9%)は生活の基礎支出の14%以上を通信費が占めていることがわかった。
通信費
生活困窮世帯の通信費の額については、次のような結果となった。
総務省「家計調査2023単身世帯」、総務省「家計調査2023二人以上の世帯」によると、通信費の支出は以下のようになっている。
単身世帯:6,610円
二人以上の世帯:12,195円
※総務省「家計調査2023単身世帯」はこちら ※総務省「家計調査2023二人以上の世帯」はこちら
一方、当該団体に支援を依頼した生活困窮世帯の通信費の平均は、以下のようになっている。
単身世帯:11,624円
二人以上の世帯:16,780円
単身世帯においては、総務省「家計調査」の平均よりも5,000円高くなっており、今後、生活困窮世帯の自立支援には通信費の抑制や平準化が重要になると考えられる。
調査結果の概要
当団体に支援を依頼する生活困窮世帯の50.5%が相対的貧困に該当しており、食費に関しては総務省家計調査のエンゲル係数と大きな差異はないものの、エンゲル係数が高い世帯と低い世帯の二極化が顕著である。
光熱費についても家計調査上の金額とは大きな違いはないが、生活困窮世帯においては支出全体に占める割合が高く、家計の負担となっている。
さらに、通信費に関しては、総務省家計調査よりも生活困窮世帯の支出が高額であり、これらの状況を踏まえると、相対的貧困の判断基準である可処分所得と世帯人数に加えて、支出の過大傾向も考慮する必要があり、抜本的な解決には給付だけでなく家計管理の指導が不可欠であると言える。
生活困窮者の生計を立て直す支援を
当該団体は「地域の食品ロスゼロ」と「地域の食に関する困窮ゼロ」(当団体呼称:ゼロゼロ活動)を目指して活動しているが、食料品支援においては全ての要請に対して支援を実行できるわけではない。
ヒアリングや審査を経て実行可否を判断し、当該団体で実施している支援は食料品の配送または手渡しという方法によるもので、一時的な支援の意味合いが強く抜本的な解決には結びつかないケースがほとんどである。
当該団体として、本調査は生活困窮世帯の自立支援につながる抜本的な解決へとつなげていきたい想いがある。
例えば生活困窮する単身世帯の通信費は11,624円と総務省家計調査(6,610円)より5,014円高く出ている。 一方、生活困窮の単身世帯の食費は平均24,707円となっており、5,014円は6日分の食費に相当する金額である。
光熱費についても同様のことが言え、生活困窮世帯は収入が低いことだけが原因ではなく、家計管理にも起因することが大きいと言える。
本来はこのようなライフスタイルの改善を伴う支援が望ましいため、様々な企業・団体様とともに生活支援に取り組んで生活を立て直すことができればと考えている。
生活困窮世帯における光熱費や通信費の削減を通じた自立支援などにご関心がある事業者様を募集している、とレポートを結んでいる。
調査の概要
調査時期:2024年3月1日~2025年2月28日
調査方法:日本もったいない食品センター回答ページより送信された支援要請を集計
調査対象: 3,503件