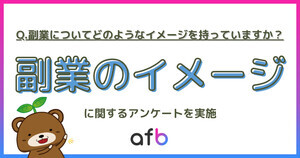最近、「ウェルビーイング(Well-being)」という言葉をよく聞く。
武蔵野大学の前野隆司教授によれば、同大学では昨年、世界初となるウェルビーイング学部を創設した。人生100年時代を迎えた日本では、極めて重要なキーワードになりつつあるようだ。
この武蔵野大学と『はらいて、笑おう。』をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社が共催で、Well-being先進国であるスウェーデンのミカエル・ダレーン教授を招いて開催したトークイベントを取材した。
「Tack=ありがとう」がWell-beingの出発点
国連が毎年、世界の幸福度ランキングを発表している。
2024年版によれば、日本は51位。対して北欧諸国はフィンランド1位、デンマーク2位、アイスランド3位、スウェーデン4位と上位を占めた。
GDPの世界ランキングだと北欧諸国はベスト10にも入っておらず、「幸せはお金では買えない」といったところであろうか。
トークイベントはストックホルム商科大学の教授で、経済や幸福、福祉を中心に研究するミカエル・ダレーン氏の基調講演で始まった。
「スウェーデンで、仕事や生活のWell-beingにおいて重要な言葉に『Tack』があります。スウェーデン語で「ありがとう」の意味で、Well-beingにとても役に立つキーワードです。私の大学では、学生に『このTackを毎日言いましょう』ということを教えています」(ダレーン氏)
確かに人から「ありがとう」と言われると、心が温かくなる気がする。感謝の言葉は心身に良い影響を与えるだけでなく、伝える側の幸福度にも良い影響を与えることが科学的に証明されているようだ。
Well-beingや福祉の重要な柱を網羅する「Tack」
Tackが素晴らしいのは、それだけではない。ダレーン氏によれば、Tackには私たちのWell-beingや福祉における重要な柱が網羅されているという。
「頭文字のTは、togetherを意味します。スウェーデンをはじめとした北欧諸国は、非常に厳しい自然環境にあります。一方、人口リソースは決して多くありません。生き抜いていくためには、みんなで助け合うことが必須なのです。高福祉国家になっているのもそのためです」(ダレーン氏)
かつて日本には、この相互扶助の精神があった。しかし、グローバル化の影響でこの精神は薄れつつあるのではないか。
「2つ目のaはagency(自己決定)です。私たちが研究の成果として見つけたのは『自分たちが何か行うことによって幸せを感じる』ということでした。つまり、ちょっとした行動でいいので、毎日、毎週、何年も繰り返すこと、それが生涯の幸せやWell-beingにつながっていくのです」(ダレーン氏)
ダレーン氏によれば、気持ちよくなる行いであれば何でもいいと言う。毎日のちょっとした行動に幸せを感じられるのであれば、何十年と繰り返すことで「チリも積もれば山となる」のも納得だ。
Well-beingに影響を及ぼすのはGDPの規模より方向性
「3つ目のcはcoherence(統一性)です。私たちは仕事やプライベート、趣味など様々なパーツで成り立っており、それら全部がまとまった存在があなたです。それをワークライフバランスのように、仕事と生活を分けて考えていいのでしょうか。つまり、幸せは仕事においても不可欠なのです」(ダレーン氏)
「仕事は生活の糧」と割り切ってしまうのも、ひとつの考え方だと思う。でも、大抵の人は人生の多くの時間を仕事に費やすことになる。
人生は有限であり、この仕事でも幸せを感じられるのが望ましいのは言うまでもない。
「4つ目のkはkinetics(動力学)で、良い方向にいっているかどうかの研究です。2年ほど前に経済がWell-beingとどう関係しているかを調査したところ、ある程度の経済的発展は、さほどWell-beingに影響を与えないことがわかりました。それよりも方向性の変化、例えば景気が後退する局面では、ストレスや不安から幸福度が低下します。一方、昨年度の幸福度を見てみると、景気が回復基調になり幸福度がアップしました」(ダレーン氏)
やはりGDPの規模は、幸福度にあまり関係がないようだ。それよりも、良い方向に向かっていると期待できるかどうか。失われた30年と言われる日本の幸福度が低いのも当然か。
スウェーデンに比べ仕事における楽しさが低い日本
トークイベントでは、ダレーン氏の基調講演に続き、パネルディスカッションが行われた。
このディスカッションからも、ビジネスパーソンがWell-beingを高める貴重な提言がもたらされた。
-

左からWell-being for Planet Earth 代表理事の石川善樹氏、パーソルホールディングス 人事本部長の大場竜佳氏、武蔵野大学ウェルビーイング学部学部長の前野隆司氏、ミカエル・ダレーン氏
興味深かったのはグローバル調査の結果だ。パネルディスカッションでは、この調査をもとに、日本とスウェーデンのデータ比較を行った。
「調査では世界138カ国・地域を対象に、Q1『働いていて楽しいかどうか』、Q2『他者に貢献しているか』、Q3『キャリアオーナーシッップ』の3つを聞きました。日本とスウェーデンを比較すると、Q2とQ3でほぼ同様の傾向ですが、Q1では15%の差がつきました。さらに、年代別に見ると、Q3では日本の20代がスウェーデンを上回りました。」(石川氏)
「中国や韓国とともに儒教国に位置付けられる日本では『仕事はお客様のために苦しんでもやるべきもの』という儒教感が残っているのかもしれません。でも、Q3を年代別に見ると、20代はスウェーデンを上回っています。このまま20代を伸ばすことができれば20年後、日本も幸福度ランキングでいいところにいけるのではないでしょうか」(前野氏)
最近はワークライフバランスではなく、ワークライフインテグレーションというキーワードが語られるようになった。まさにダレーン氏が指摘したcoherenceと言える。
仕事と生活を切り分けず、共に楽しさを求めていくことがWell-beingにつながっていくのであろう。