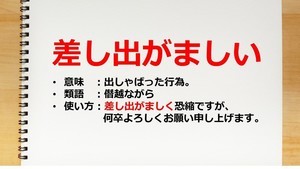「あれは言葉のあやだから…」といった具合に、弁解や釈明の場面で使われることが多い「言葉のあや」という言葉。「言い間違い」や「つい口から出てしまった」といったニュアンスの使い方は、本当に正しいのでしょうか?
本記事では、「言葉のあや」の正しい意味のほか、使い方や例文、言い換え表現などについて詳しく解説します。
「言葉のあや」の意味とは
「言葉のあや」とは、「巧みな言い回し」を意味する慣用句です。つまり、直接的な表現ではないため、さまざまな解釈ができる表現方法です。そのため、詩や文学作品において、作者の感情を表現するために「言葉のあや」が使われることがあります。「この小説には言葉のあやが巧みに用いられている」という場合がそうです。
また、相手にはっきりと伝えづらいことを話す際に、例えや比喩表現を用いて巧みに表現する言葉の使い方もされます。
一方、近年では、発言があらぬ誤解を招き弁明や釈明をする際に「ごめん、あれは言葉のあやだから」といった具合に使われることが一般的になっています。
「言葉のあや」で繊細な事柄をうまく言い表そうとしても、理解されなかったり間違ったニュアンスで受け取られたりすることが多いため、言葉の性質を逆手に取って「そういう意味じゃないんだよ」と弁明の場面で使われるようになったようです。
誤解されがちですが、「言葉のあや」には「不用意な発言」という意味はありません。言い訳の際に使われる「言葉のあや」は、「あの発言は不本意だった」という意味ではなく、あくまで「巧みな言い回しが故の誤解です」ということを表現しています。
「言葉のあや」の語源
「言葉のあや」を漢字で書くと「言葉の綾」となります。「綾」とは、「綾織(あやおり)」のことで、布を織るときに用いられる技法のひとつです。2、3本の縦糸を横糸に通して織っていくのですが、高度な技術が必要です。熟練の技を駆使して織り上げる綾織のように、言葉選びの技術を駆使して文章を表現することすることを「言葉のあや」というようになったといわれています。
「言葉のあや」の使い方・例文
「言葉のあや」は、例えを駆使した巧みな表現と間違いを正すための言い訳の2つの意味で使われる言葉です。以下にそれぞれの具体的な例文を紹介します。
巧みな表現として使う場合
「言葉のあや」が元々持っていた「巧みな表現」という意味で使用される例文です。
- 「この小説は言葉のあやに富んだ本だ」
作者がさまざまな比喩や例えを用いて場面を描写していて、読み応えのある小説であることがわかります。
- 「言葉のあやを使うのはいいけど、遠回しに言い過ぎると印象が悪くなることもあるよ」
優しさから巧みな言い回しを使って注意するのはいいことですが、あまりに遠回しに言うことで誤解を招くことは信頼を損なうこともあるという例文です。
言い訳として使う場合
近年使われるようになった、誤解を招いた際の言い訳として使用される例文です。
- 「言葉のあやでそういっただけで、本気で怒っているわけではない」
感情が高ぶってしまい、つい大げさに批難してしまったけど、本心ではなかったことを伝えています。
- 「言い訳に聞こえるかもしれないけど、あれは言葉のあやで言っただけだから」
冗談半分で言ったことで相手を傷つけてしまったときなど、誤解を説くために伝える例文です。
「言葉のあや」の類義語・言い換え表現
「言葉のあや」の類義語は「比喩」です。「比喩」は、ある物事を類似または関係する他の物事を借りて表現することを意味します。「言葉のあや」も「比喩」も、文章そのものの意味ではない表現という点が同じです。
また、弁明の際に使われる「言葉のあや」は、「誤解を招く言葉」、「誇張表現」などに言い換えることができます。
「言葉のあや」には十分に気をつけよう!
今回は「言葉のあや」の意味について解説しました。巧みな表現が相手にうまく伝わると良いですが、誤解を招くような「言葉のあや」には気をつけて発言しましょう。