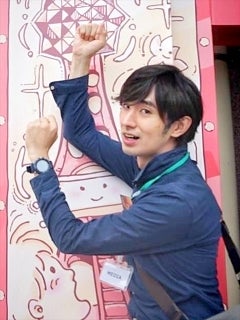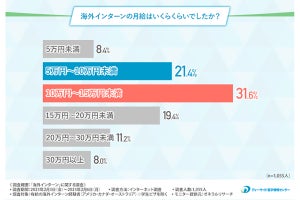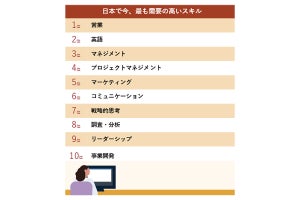唐突ながらTOEICのListening & Reading (TOEIC L&R)を受験したことはあるだろうか? そこで描かれるストーリー展開が「超ホワイト」であり「できるならTOEICの世界に転生したい」などとSNSで話題なのだ。
たしかに、通勤時間が短くなるという理由で近所の支社に転勤できるなんて、どこの話だ!? ひょっとして問題の作成者はホワイトな職場でしか仕事してこなかったんじゃないか……? それともお釈迦(しゃか)様の生まれ変わりとか? そこでマイナビニュース編集部では、中の人に詳しい話を聞いてみることにした。
■TOEIC L&Rってそもそもどんな試験なの?
話を聞いたのは、国際ビジネスコミュニケーション協会で「テスト問題の品質管理」業務にあたっている調査研究室の河西路子氏。外資系メーカーに勤務したのち同協会に転職、すでに10年間以上の長きにわたりTOEIC L&Rの問題用紙と向き合ってきた。いわば、この道のエキスパートだ。その数、設問数に直すとなんと7万問以上……!!
そんな彼女にまずは、TOEIC L&Rで問われる英語の特徴について聞いてみた。
「基本的にビジネスの場面で日常的に使われる英語が問われます。シチュエーションとしては、オフィスにおける会議、何かの製品を受注する、海外に出張する、などがあります。内容としては、そこまで"ビジネス英語"という感じでもなく、日常のやりとりで使われる生きた英語が問われる、と思ってください。ショッピングセンターに買い物に行く、休日にガーデニングをしている、といったビジネスとは関係ない場面も出てきます」。
なるほど、TOEICと言うとビジネス英語。したがって真面目なシチュエーションばかりかと思ったが、実際はそんなことないようだ。
■ホワイトすぎる問題。そのワケとは?
さて、ここからが本題。TOEICの世界観って、ホワイトすぎやしないだろうか? 平日に仲間とピクニックに行ったり、出張のスケジュールに観光の時間を組み込んでもらったり……。筆者の知る限り、上司が部下を𠮟責(しっせき)する、みたいなピリピリした場面は一切出てこない。これはSNS上でも話題になっている通りだ。あえて、そんな世界を描いているのだろうか?
「これはTOEICの成り立ちが関係しているのかな、と思います。TOEIC L&Rは世界160カ国で実施されています。そこで、どの国の人が受験しても内容がスッと入ってくるようにしたい。育った環境は人それぞれですが、文化的な背景によらず、ひとつの同じテストで、同じ土俵で、同じモノサシで英語力を測りたい。そこを大切にしているんです。つまり固有の知識がないと解けない、ということがないようにしたい。それを突き詰めた結果、私たちでさえうらやましく思うほどホワイトな世界になった、ということが言えると思います」。
さらに、河西氏はこう続ける。
「またこれは、受験者をドッキリさせない、という言い方もできると思います。受験者をビックリさせる出来事だったり、推理させるような場面、犯罪ドラマのようなハラハラする展開、そういうものはそもそも取り上げません。事件、事故、自然災害、戦争は起こりません。宗教の違い、肌の色も関係ない。決して人から𠮟られることもありません。たとえ会議に遅刻しても、上司から嫌みなどは言われないでしょう。それは受験者の中には、過去にさまざまな経験をした人がいるということを前提に問題が作成されているからです。受験時に不快な思いをしないように、といった観点で問題を精査するプロセス、それを"センシティビティーレビュー"と呼びます。このプロセスがあることで、設問の内容やシチュエーションによって心に悪影響をおよぼさない状態で英語力を測ることができます」。
なるほど、そこまで考えられていたのか――。すごく納得。それでは一体、どんな経歴の人たちがTOEICの問題作成に関わっているのだろう? 異文化でいろいろな経験を積んできた海外移住者? 優しい理想の世界を作り出す作家? はたまた常に心が平穏で誰に対してもフェアでいられる僧侶とか?
「元僧侶が在籍しているかは不明ですが、ETSという教育機関にはさまざまなエキスパートが在籍していることは事実です。例えば統計の専門家、心理学の博士号を持っている人、などなど。そうした人たちの総合力により、さまざまな側面から考えて作られているテスト、ということが言えると思います」。
さらに彼女は問題についてこう説明する。
「世界情勢は、日々刻々と変化しています。そこで私たちも10年に1度の頻度で、TOEIC L&Rのテストで描かれる環境を見直す機会も設けています。もっとも、どの時代に受験しても違和感のないように、時事ネタは一切入れておりません。『いま不景気だよね』みたいな話ではなく、もっと普遍的なものに題材を求めています。宗教、政治、文化的な背景から考えても常に公平な問題になっているか、定期的にレビューも実施しています」。
なるほど、これまでの話を総括すると誰もが公平にテストを受けられるよう"余計なもの"を排除していった結果、中の人もうらやむようなホワイトな世界ができた、ということが言えるのかも。
■問題作りのポイントは?
では題材のほかに、ETSが問題作りで意識していることは?
「そうですね。TOEIC L&Rは、Listening 100問+Reading 100問の計200問で構成されています。その問題作成には、アイテムライターと呼ばれる人たちを含め、本当にさまざまな人間が関わっています。そのうえで難易度は保たれているか、意図した設問はきちんと機能しているか、この試験で正しく能力が測れるか――。これまでの知見も生かして検討を重ねます。内部で何度も見直し、チェックするレビューのプロセスを経ているんです」。
ところで、ひとくちに難易度を保つと言ってもそれは大変な作業では? だって、大学入試でさえ「今年は難しかった」「昨年は易しめだった」なんてことが起こっているでしょう?
「そこで試験の実施後には、1個1個のアイテムについて数値の観点から徹底検証しているんです。『この設問は、高い英語力を持っている人にしか正解できないようにしたはずなのに、そうでない人も正解できているじゃないか』なんてことになれば、つまりは設問が機能していない、ということになる。これをアイテムアナリシスと呼んでいます。試験後、スコアを出すまでそれなりの時間をいただいている理由は、裏でこんな分析と検証作業をやっているからなんです」。
考えてみれば、どの年の、どの月の、どのテストを受けても難易度が変わらないようにするってとんでもないこと。うん、聞けば聞くほど面白いな。
■届いていたSNSの声
ちなみに中の人たちは、SNSで「TOEICの世界、ホワイトすぎる」が話題になっているのは知っているのだろうか?
「はい。特に"HAPPY NEW CAREERキャンペーン"というものをうってからは、いろいろな声が寄せられています。純粋にありがたいなと思いましたし、そういう視点で見ていただいているんだ、ということで嬉しくなりました。職員の間でも話題になったんですよ」。
やっぱり届いていたんだ、SNSの声。
「昔からよく言われていたのは『コピー機がよく壊れるよね』ということでした(笑)。ホワイトという言い方ではありませんでしたが、昔から『平穏な世界だよね』とは言われていましたね。勤務中なのに歯医者でちょっと抜けてもいいなんて、本当にうらやましい限りです。中の人たちは"ホワイト"という見方はしなかったですが、素直なストーリーだよね、とは見ていました」。
たしかに、コピー機がよく壊れる、というのは記憶にもあるかも。コピー機が壊れても、心がざわついて英語力が正しく測れなくなる心配はないもんなぁ。
「逆に、ホワイトすぎるという声をSNSで見かけるのは、私たちには新鮮でした。そんな見方をされているんだ、と思いました。表面的にはホワイト、その裏には自分たちの思いがある。自分たちのこだわりが、形を変えて伝わっていたんだな、という喜びがあります。余分な要素を取り除いて問題作成してきた、そこが浸透した、理解された、という言い方ができると思います」。
逆にもう少しだけストーリーでドキドキしたい、という声はないんだろうか。
「ツルッとしすぎている、ストーリー展開が面白くない、とおっしゃる方もたしかにいます。ただ、繰り返しになりますが、テストを難しくすることが目的ではないんですね。初級者から上級者まで、ひとつの尺度でワンストップで英語力を測るための"モノサシ"としての役割を考えたとき、面白い小説にする必要がない、というところなんです」。
■中の人からアドバイス
これからTOEIC L&Rを受けてみたい人に、アドバイスがあれば。
「そうですね。テスト問題は、実際に英語が使われる場面を想定して作っています。だから出てくる英文は、まさに現場で使えるものばかり。アメリカ人とメールでやりとりしたり、海外のホテルでチェックインをしたり、電車が遅れていたり、そんなシチュエーションが出てくるので、海外で日常生活を送るときにも役立つでしょう」。
河西氏の話によると、緻密に考えられた良質な200問がそろっていると言う。
「実際に使われている英語がReadingにもListeningにも設問として出題されています。若者言葉は出てきませんし、どの世代の方にも理解できるきれいでスタンダードな英語が使われているのが特徴です」。
TOEIC L&Rがローンチしてから44年ほどが経つ。では、はじめの第1回って、どんな風にテストが作られたんだろう?
「第1回のテストを作成するとき、ディレクターたちは世界各国を回ったそうです。日本にも来ていますよ。複数のスーツケースを持ちこんで、オフィス街などで問題作成の参考になりそうなパンフレット、チラシなどをありったけ詰め込んで本部に持ち帰ったと聞いています。そんなエピソードからも、TOEIC L&Rでは第1回から実際の現場で使える実践的な英語力が問われてきた、ということが分かりますよね」。
なるほど、そうやって44年間"生きた英語問題"を追求し作り続けているのか。最後に、TOEICに向けて勉強を重ねている人たちへのアドバイスをもらった。
「TOEICの勉強をしていたら、いつの間にかビジネスの現場で使える英語が身についていた、という経験を私自身もしています。試験勉強=実践力に結びつくのがTOEICですので、それを励みにしてもらえたら嬉しいです」。