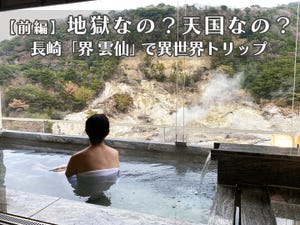戦国時代、将軍、○○藩。小学生の頃からどこかとっつきづらい社会や日本史の時間は、筆者にとって苦痛に等しい時間だった。それは社会人になってからも変わらない……と思っていたのだが、長崎県にある「平戸」という町を訪れてみたら、その考えは一変! 歴史嫌いだったアラサーをも虜にした興味深い"長崎・平戸"の町を紹介していこう。
■「平戸」ってどんなとこ?
九州本土の西北端に位置する長崎県・平戸は、日本で初めて西洋貿易が行われた場所である。戦国時代から江戸時代初期にかけて各国との交流により発展し、貿易港として平戸は隆盛を極めた。また、筆者も覚えることのできた偉人の1人「フランシスコ・ザビエル」もここを訪れ、キリシタン信仰を広めたと言われている。
町を歩けば、教会と寺院が隣り合わせる稀有な景色を見られるなど異文化と日本文化が混じり合った平戸独自の雰囲気を楽しめる。
また、平戸を語る上で外せないのがこの土地を治めた平戸藩主「松浦(まつら)」家だ。地形を生かし外交などで力をつけ、平戸を繫栄に導いた松浦一族。そんな彼らの物語もこの旅では一緒にひも解いていく。
■泊まれるお城「平戸城」!?
「平戸城」は、1599年に平戸藩藩主・松浦鎮信(まつらしげのぶ)によって築城された。別名「亀岡城」とも呼ばれ、築城400年を経た現在も、城主つまりお殿様が存在し、平戸の交流も深いめずらしい城だ。
さらにここは、日本100名城初の常設の宿泊施設「城泊」として城に泊まることができる(事前予約制/1泊約60万円~)。そう、実際にお殿様気分を味わえる、さらにめずらしい城なのだ!
泊まれる場所は、懐柔櫓(かいじゅうやぐら)という櫓の中。足を踏み入れると、そこは和モダンでラグジュアリーな空間が広がる。
食事は、海の幸をはじめとする新鮮な旬の素材を使った創作料理のフルコースを城内の乾櫓を改装したレストランで堪能。海に面する3面ガラス張りのバスルームからは、平戸島の海を見渡せ、非日常体験がかなう。
ちなみに、この城は1613年に大半が焼失。一説では松浦鎮信自らが放火し焼き払ったとされ、戦国時代から豊臣氏と関係が深かった松浦家は、当時の幕府からその動向を疑われていたことが原因だと言う。外様大名としての苦しい立場にあったことが、城の歴史からもうかがえる。
天守閣内にある「歴史体験アミュージアム」では、先端技術を組み合わせた展示物から城や町の歴史を学ぶことが可能。パノラマ映像体験をはじめ、石垣の石組みを体験できる「石垣パズル」やスクリーンを使ったデジタル書道体験など非常に興味深い体験ができるので、ぜひ足を運んでみてほしい。
■松浦家の歴史を知る「松浦史料博物館」
これまで話してきた平戸藩主松浦家について知ることができる「松浦史料博物館」。鎌倉時代から続き、平戸をはじめ壱岐をふくむ長崎県北を治めた平戸藩主松浦家に伝来した資料を保存・公開している。
個人的にここに来たなら体験してほしいのが、殿様の茶室「関雲亭」での呈茶体験。1893年、松浦家第37代詮(心月)が建築した「関雲亭」は、農村庶民の質素な居住様式を取り入れ、自然の材料を多く用いてつくられている。
松浦家第29代天祥鎮信によりおこされた「茶道鎮信流」で点てられたお茶と、復元菓子の烏羽玉(うばたま)もしくはカスドースが楽しめる。
■大航海時代の建造物が甦る「平戸オランダ商館」
平戸オランダ商館は、1609年に江戸幕府から貿易を許可された東インド会社が、平戸藩主松浦鎮信公の導きによって平戸に設置した東アジアにおける貿易拠点である。当初は住宅1軒を借りて始まり、その後、貿易が拡大するに従い、施設の拡大整備が行なわれた。だが、1641年に幕府の命により商館は取り壊され貿易は長崎出島に移転した。
現在の「平戸オランダ商館」は、当時の倉庫を忠実に復元したもので2011年9月に開館した。中には当時の貿易に関する史料や貿易品などを展示している。
同館スタッフによると、日蘭交流がさかんだった時期、平戸は行動制限なく外国人が過ごせていた自由な場所だったそう。自由恋愛も認められており、当時にはめずらしい外国人と日本人のカップルも多く、その子どもも誕生していたそうだ。「平戸オランダ商館」は、人々の交流や繁栄の源となった交易についてなど、平戸ならではの歴史を知ることができる。
■平戸の絶景を眺めながら昼食を!
平戸の歴史を学んだあとはランチタイム! 2022年3月にオープンした「海の見えるごはん屋」へ。その名の通り同店は、平戸大橋や平戸瀬戸を眺めながら食事ができる絶景堪能スポットでもある。筆者が訪れた日は、地元の人の姿もちらほら、地域に根差した店らしい。
米、魚、肉、野菜などとことん平戸の食材にこだわったメニューは、どれもダイナミック!
「"平戸海千山千" 彩り御膳」(1,800円)は、魚料理に天ぷら、そしてあごだしの漬け茶漬けなど、平戸の旬の味をぜいたくにちょっとずつ楽しめる。また、羽釜で炊いた平戸米がツヤツヤほっくほくで、おかずとの相性も抜群だ。
ごはんのあとは、店の隣にある「ひらど新鮮市場」に行ってみるのがおすすめ。地元の魚や野菜などを販売しているので、ぜひ食でも平戸を楽しんでほしい。
■淡いグリーンが美しい!「平戸ザビエル記念教会」
腹ごしらえもすんだら、平戸市街地の丘の上へ。ここに佇むのは、尖鋭な屋根とモスグリーンの壁が特徴的なゴシック様式の「平戸ザビエル記念教会」だ。
平戸に3度にわたって布教に訪れたという宣教師フランシスコ・ザビエル。同教会には、献堂40周年の1971年、聖堂の脇に彼の像が建立された。それがきっかけとなり、「聖フランシスコ・ザビエル記念聖堂」と呼ばれるようになり、現在の名称に至る。
■「平戸蔦屋」で400年愛されるお菓子を堪能!
次に向かうのは創業500年以上、長崎最古の歴史を持つお菓子屋さん「平戸蔦屋」だ。
16~17世紀にかけてポルトガルやスペイン、オランダなどの貿易船が相次いで平戸に入港。南蛮渡来の時代を迎えた平戸に伝わったのが、カステラやコンペイトウといった数々の南蛮菓子だった。同店はこの頃より南蛮菓子に目を向け、カスドースをはじめとする伝統銘菓を作り、平戸藩主松浦家にも献上したという。
店内にはカスドースや牛蒡餅など多くの商品が並ぶ中、ひときわ目立っていたのが「平戸百菓繚乱(ひらどりょうらん)」の菓子「果の花(かのか)」だ。
「平戸百菓繚乱」とは、平戸藩伝来の100種類ものお菓子が掲載されたレシピ図鑑「百菓之図」をモチーフに開発されたもの。そこに描かれているお菓子を、現代の平戸の菓子職人たちが現代風に復刻・アレンジした、平戸スイーツの新ブランドである。
「平戸蔦屋」では、そのうちの1つ「果の花」というフィナンシェ風の洋菓子を創作。江戸後期に誕生した「花かすてぃら」に着想を得て作られた「果の花」は、厳選した卵、バター、アーモンドを使用し、濃厚かつ香り高く焼き上げられている。台湾産のドライマンゴーと平戸産の夏香ピールが爽やかな風味を醸し出し、その見た目と上品な味わいから贈答品にもぴったり。
■お殿様の御用酒屋だった「福田酒造」
日本最西端に位置する酒蔵「福田酒造」は、1688年に平戸藩の御用酒屋として創業。今も現存する当時の酒蔵を利用して酒造りを行っている。代表銘柄でもある「福鶴」は、平戸藩の御用酒でもあった。
近年、同社では長崎県産のジャガイモを使った「じゃがたらお春」や、南蛮伝来の秘法を受け継いで製造された長期熟成酒「かぴたん」など、焼酎類のほか本みりんなども手掛けている。
印象的だった酒は、麦焼酎の「35度 かぴたん10年」。焼酎というよりもウイスキーのような芳醇さを感じる、深くどっしりとした味わいが特徴だ。重厚な雰囲気の中ウイスキーグラスで、噛みしめるように飲みたくなるお酒だった
いかがだっただろうか。異国情緒あふれる町には、交易とともに繁栄した面影が今なお色濃く残っている。当時にタイムスリップしたかのような旅にあなたも出かけてみてはどうだろう? 次回は、平戸藩との関りも深い三川内焼について! お楽しみに。