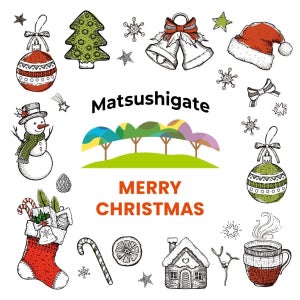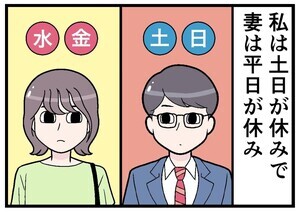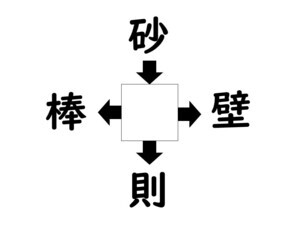なぜ今ネイバーフッドなのか
アメリカにポートランドという小さな街がある。日本で言うと船橋市や鹿児島市位の人口を持つ街だ。その街は「世界一住みたい街」と言われ多くの人の心を魅了し、コロナ禍の中でも、今尚移住者は減ることがない。
この街を生まれ変わらせた中心的な組織の中に居たのが、私だった。
ポートランドの開発局に唯一の日本人として参加し、ポートランドの再生する「街づくり」に携わったのだ。そしてそこから人を招くためには何が必要だったか、何が大事であったかを、“自分が住んでみたいと思う街”の魅力を考えながらからひも解いていこうと思う。
私は、街の魅力というものは、そこに住んで働いている人々や、彼らが作り出す文化やコミュニティの特徴が醸し出すものだと考えている。要は「街は人ありき」という事なのだ。
建築家であり都市計画家でもある丹下健三氏は「人は情報の媒体である」と言ったそうだが、インターネット社会の今こそ、その言葉をもう一度かみしめて考える時が来ているように思える。
今世界の情報はどこにいてもスマートフォンさえあれば入手できる時代になった。それはとても素晴らしい時代だ。
しかしその反面、そのために情報の波にのまれ自己を失い、自分のやり方で新しいことができない人格が生まれてきているように思えている。そして何より大事なことは、人間同士がもつ体温、要するに温度は決して機械からは得られることがない。機械は楽しい時は笑わないし、悲しい時は涙を流すことはない。
人は感情を共有することができる。一緒に笑って泣いて怒る、そんなことが実は一番人生を豊かにさせている、そんな「人ありき」の大事さを教えてくれるのは、自分の住む街だという事は言えないだろうか。
ボローニャの街の魅力
自分が今住むのであればどこがいいかと考えた時に、まず出てくるまちの一つはイタリアの「ボローニャ」という街だ。以前、あるきっかけがあり、私は井上ひさし氏が著者となる『ボローニャ紀行』(文春文庫)という本を読んだ。
ボローニャという街は衰退している小さな町だ。しかし街づくり通や建築通な人達にとても愛されているという。そしてそれは何故なのか、その答えがその本にはたくさんのエピソードとともに書かれていた。
ボローニャは、世界で最初の大学が作られた街だという。そもそも、なんと商工会議所が、街のために専門学校を作ったということだった。何故それを作ったかというと、お店で働く店員が募れないという街の悩みを解決するためだった。
店員を育成する学校を、自分達の街の店舗のためにその街の商工会議所が創設したのが始まりであったというのが驚きだ。それが月日を重ねて大学という母体に変わっていったという。
街を大事にするという点では、自分が日本で担当した富山県南砺市井波(なんとし・いなみ)の地域でもあった古民家を改良してまちやどを経営したり、その町の産業である木彫師とのコラボをしてデザイン性の高い民芸品やお菓子を作ったりしたことが注目を浴び観光客の増大につながったことも。町ぐるみで協力した甲斐あってこそのものであった。
「ボローニャ紀行」には、こんなエピソードも書いてある。
週末で人が大勢歩いているのに店は閉まっている。日本であったら考えられない光景だ。たとえ、年末年始であっても、人が集まるということを察知すれば、日本のどこのお店も"今が儲け時"とばかりに休日返上で、店を開け、仕事をするのが通常だ。
しかし不思議なのは、人が居ても店を開かないという事だ。そして店が開いていないというのに、人々が街に出てくるという事の不思議だ。
店舗はどこも閉まっているため、買い物をすることはできないはずだ。しかし、沢山の人が、街を歩く、これは一体どういうことなのだと本の中で問いかけていた。それの答えは地元の言葉にあった。歩く人はこう言ったそうだ。
「私たちは自分たちの街を視ることを楽しんでいる」と。
そう、街の人は、街を楽しむために歩いているというのだ。そしてこうも言う。「眺めることはとても面白い。歩いていると、知っている人に会う。会えば会話が出来て話に花が咲いたりする。時間を忘れて楽しい時間を知り合いと共有する。これこそ、人生の喜びだ」と。
本の著者は人生の喜びはこういう些細なところに在ったのだと地元の人によって気付いたという。
そしてそれは店の店員であっても住民と同じ感覚を持っているのだろう。店を開けて儲けることよりも、もっと尊いものを欲しがっているに違いない。
そうだ、街が活(生)きていれば、自分の地域を守ることを人々が考える。そして日常の中にこそ在る楽しみや、それによる人生の目的を見つけることができるのだ。
これは「ボローニャ紀行」著者にとって目からうろこであったそうだ。要するに、人々は街にあるお店や施設を楽しむのではなく、地元の文化や人そのものを楽しむ、それが街という器の中で日常的に垣間見える人生の意味でもあると言えるのだろう。
幸せの定義
ポートランドも同様な気質を持っている。いや幸せの基準が同じであるといってよいだろう。ヨーロッパほどの規模はないのだが、都会にいても田舎に居ても、コンパクトであるが故、住民たちは同じファーマーズマーケットに足を運び、そこで知人に会い、楽しい時間を過ごす、そんな街を人々は愛している。
ダウンタウンは小さいので、週に何度も歩けば必ずといっていいほどに同じ人と会うので、顔見知りになり、そこにコミュニケーションが生まれる。
もし、これが東京の都心で会ったらどうだろうか。いや、そもそも知り合いと会うという事が殆どありえず、人と会うのは散歩がてらなどではなく、待ち合わせをしたり場所を特定したりしなければならないのが常だ。
アメリカのハーバード大学を卒業した人達を70年以上追跡調査し、そこから「幸せの定義」を見つけるという研究をした結果があるという。
その結果一番幸せを感じていた人たちは、自分が大事にする身近な人、友達や家族、(それは少なくても良い)が居るという事という結果がでた。
そして経済的には、年収750万程度の収入以上はもう幸せの期待値は変わらないので、そのくらいの収入があれば十分幸せを感じることができるという。そしてそこに自分の居場所があるという事も大事な点であるという。
同じ空間を分かち合い、楽しい会話が出来ることに自分自身も魅力を感じている。私はこれからもその現実化のための街の在り方を考え、提唱していきたいと思っている。もう高度成長の時代は過ぎ、それを目的としない時代が来ていることを感じている。
また、今の人々、特に若者たちは、際限無く金銭的な豊かさを求める人は少なくなってきている。本質的な「生活の豊かさ」を気付き始めたという世代交代が始まっているのだとも感じている。
サスティナブル都市計画家が、日本で住んでみたい街とは
ボローニャ以外で住んでみたい街、もしそれを日本の中で言うのであればそれは自分が手掛け、前述した井波だろうと思う。
私自身も井波地区の将来ビジョン策定のメンバーとなりそこに滞在した期間に沢山の人と顔見知りになったり、友人になったりしている。
そして今もたまにそこに行けば、顔見知りになった人たちが「お帰り」、「また来たね」、と笑顔で声をかけてくれるのだ。
もちろん自分が「街づくり」において、手掛ける方法として行ってきた"住民との対話"(街づくりをする前にそこに住む人たちと徹底的に話し合いどんな街にしたいのかを公、民、そして企業も一緒にワークショップで探っていくという作業)や建物の「ミクストユース」化、「エコディストリスト」などいくつかの方法論も街を良いものにするためにとても大事なことだ。
しかし、何よりも大事なのは、「人が居て、その人たちが住んでいる景観があり、こよなく愛する部分がある」ということなのではないかと私は考えている。
「ボローニャ紀行」を読むことで、「生活の豊かさとは、その街で楽しめることを生み出し、見つけることが出来る」という事を改めて考える機会を持つことが出来たことは自分にとって大きなきっかけとなっている。
街が人を幸せにするということ、これが私に与えられた永遠の課題であると自負している。
著者プロフィール:山崎満広(やまざき・みつひろ)
 |
サステイナブル都市計画家/横浜国立大学客員教授
1975年東京生まれ。つくば市まちづくりアドバイザー、神戸市港湾局・神戸ウォータフロント開発機構アドバイザー、米国のデザインコンサルティング会社Ziba Design国際戦略ディレクター、大鏡建設顧問、ポートランド州立大学シニアフェロー、慶應義塾大学SFC上席研究員、横浜国立大学 客員教授等を兼任。著書に『ポートランド 世界で一番住みたい街をつくる』、『ポートランド・メイカーズ クリエイティブコミュニティのつくり方』(学芸出版社)がある。