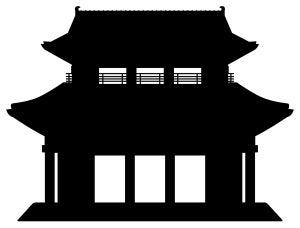1948年(昭和23年)に総合雑誌『展望』に連載された後に書籍化された長編小説『人間失格』は、太宰治の代表作の一つであり、遺作といわれています。自身の死の直前に完結したこの物語は、太宰治の人生を色濃く反映しているとされ、人間の本質とはなにかを考えさせられます。読書感想文の課題図書として読む人も多いのではないでしょうか。
今回は『人間失格』のあらすじや見どころ、読書感想文を書くときのポイントなどを解説します。2度にわたって作成された映画についてもまとめました。
※本記事はネタバレを含みます
『人間失格』の主な登場人物
『人間失格』は主人公の葉蔵の人生を描いた物語です。まずは『人間失格』の主な登場人物について見ていきましょう。
主人公・大庭葉蔵
葉蔵は純粋であるがゆえに子供のころから人に馴染(なじ)めず、「道化」となることでなんとか日々を過ごしていました。資産家の末息子でしたが、心中未遂事件や左翼運動、乱れた女性関係などで身を落とし、ついに「もはや、自分は、完全に、人間で無くなりました」と悟るのです。
太宰治自身の経歴と重なるところが多いことから、作者の「分身」ともいわれています。
葉蔵を取り巻く女性たち(ツネ子・シヅ子・ヨシ子)
成長した葉蔵は、多くの女性たちと関係を持つようになります。中でも物語に大きな影響を及ぼすのが、「ツネ子」「シヅ子」「ヨシ子」の3人です。
進学のために上京した葉蔵はカフェの女給ツネ子と最初の心中を実行しますが、失敗し、一人生き残ってしまいます。その後、葉蔵は未亡人で記者のシヅ子と同棲を始めますが、うまくいきません。その後はバーのマダムの家に泊まり込むようになりますが、そうして出会った向かいの煙草屋(たばこや)の娘である純粋なヨシ子と暮らし始めます。しかし彼女が出入りの商人に汚されてしまったことで決定的に心を病みます。
その他の主要人物(竹一・堀木正雄・父)
中学生時代、葉蔵が「道化」であることを見破ったのは同級生の竹一でした。その後、葉蔵と親しくなった竹一は、彼に「お前は、きっと、女に惚(ほ)れられるよ」と告げます。
上京後、葉蔵に夜遊びや酒を教えたのは堀木正雄でした。2人の腐れ縁は続きますが、ある会話をきっかけに葉蔵は堀木が自分を「真人間あつかいにしていなかった」と気付きます。
そして「自分の胸中から一刻も離れなかったあの懐しくおそろしい存在」だった父が死に、葉蔵は兄の進言によって東京を去り、故郷に戻るのでした。
人間失格のあらすじを100字程度で簡潔に紹介
『人間失格』の詳細なあらすじを紹介する前に、まずは内容について簡単に紹介します。物語の大筋は、次のようにまとめることができます。
生きづらさを抱えつつも社会に適応するため道化を演じる葉蔵は、苦しみから逃れようと酒や女遊びを覚え堕落します。女給との心中未遂、未亡人との同棲の後に内縁の妻を得て、ようやく自分も人間らしいものになれるのではと思ったのも束の間、心のバランスを崩し、ついに「人間失格」となったのでした。
裕福な家庭の末息子として生まれた葉蔵ですが、作品の終盤、田舎の療養地で彼は「いまは自分には、幸福も不幸もありません」と語りました。なぜ、葉蔵はそのように語るに至ったのか、悲しい生涯を、さらに詳しく見ていきましょう。
『人間失格』の見どころを解説
うつうつとした男の人生が語られる『人間失格』ですが、その見どころはどこにあるのでしょうか。ここでは『人間失格』の見どころを3つ紹介します。
破滅していく葉蔵の人生
『人間失格』は、人間社会の中で、上手に生きることのできない葉蔵が破滅していく様を追う物語です。時にもどかしく、時に葉蔵を叱咤(しった)したくなることもあるでしょう。しかし、人間の弱さを「これでもか」とさらけ出す葉蔵の姿に、読者はいつの間にか自分自身を重ねてしまうはず。
「道化」のままではいられない、どうにかして生きようと不器用にもがく葉蔵には、決してポジティブなだけでは生きられない、人間の在り方の不安定な部分が投影されています。
葉蔵の女性関係と、葉蔵の心境
誰にも心を許せなかった葉蔵ですが、「自分には、人間の女性のほうが、男性よりもさらに数倍難解でした」と述べるように、特に女性との関係は複雑で、葉蔵は何人もの女性たちに苦しめられます。といっても、彼女たちは決して悪女ではありません。みな、葉蔵を思い、懸命に生きています。
葉蔵と関係する女性たちとはそれぞれの幸せをつかめたはずなのに、やはり葉蔵は平穏な生活を手に入れることができないのです。女性たちとの「あるかもしれなかった」日々を選ぶことのできない葉蔵は、やがて一人、深淵(しんえん)へと転がり落ちていきます。
葉蔵と女性たちとのやりとりと、その裏にある葉蔵の心境に注目すると、葉蔵がどう感じ、何に苦悩しているのかがよりわかるかもしれません。
太宰治の生涯との関連性
作者である太宰治は、実際に心中未遂を繰り返し、女性関係のうわさも尽きない人でした。そして『人間失格』を執筆し終えた彼は、実際に山崎富栄という女性と心中して命を落とします。
『人間失格』の葉蔵は、太宰自身がモデルともいわれています。「恥の多い生涯を送って来ました」から始まる葉蔵の手記は、太宰治自身の告白だったのかもしれません。
『人間失格』の詳細なあらすじ
それでは、『人間失格』の詳しいあらすじについて見ていきましょう。『人間失格』は「はしがき」「第一の手記」「第二の手記」「第三の手記」「あとがき」の5部構成です。それぞれの内容をまとめました。
はしがき
「私は、その男の写真を三葉、見たことがある」から始まり、第三者の男の目線で語られます。男は葉蔵の写真について語りますが、1枚目の幼少期、2枚目の青年期、そして3枚目の年齢の分からない白髪姿の葉蔵は、いずれも気味の悪い人間として男の目に映ります。
そして男は葉蔵について、「私はこれまで、こんな不思議な男の顔を見た事が、やはり、いちども無かった」と述べています。
第一の手記
ここからは、葉蔵自身の視点で語られます。幼いころから「人間の生活というものが、見当つかないのです」と語り、自分は異質だと思って生きてきた葉蔵は、他者とつながるために「道化」として生きることを覚えました。そんな葉蔵は女中や下男に「哀しい事を教えられ」※ても誰にも言い出せず、ただ笑って過ごすことしかできませんでした。
※作中では断言されていませんが、前後の文脈から推測すると性的虐待と考えることができます
第二の手記
「道化」を演じる幼少期の葉蔵でしたが、それを唯一見破ったのが竹一でした。やがて竹一と親しくなった葉蔵は、洋画を「お化けの絵」と称した彼に「僕も画くよ。お化けの絵を画くよ」と告げます。葉蔵はそれらの絵を、「人間という化け物に傷(いた)めつけられ、おびやかされた揚句の果、(略)それを道化などでごまかさず、見えたままの表現に努力したのだ」と感じて「将来の自分の、仲間がいる」と興奮します。
やがて成長した葉蔵は美術学校への進学を希望しますが、父親にそれを言い出せず、東京の高等学校を受験します。進学とともに上京した葉蔵は、そこで堀木正雄と出会いました。
やがて堀木と飲み歩くようになった葉蔵は、カフェで女給をしているツネ子と関係を持ちます。しかしそれを知らない堀木に彼女を「貧乏くさい女」と称され、葉蔵は初めて「微弱ながら恋の心の動く」のを感じます。そして葉蔵とツネ子は入水(じゅすい)し、葉蔵だけが生き残ったのでした。
第三の手記
生き残った葉蔵は、高等学校から追放されてしまいます。葉蔵は堀木のもとで知り合った未亡人シヅ子の家に身を寄せ、漫画家になります。シヅ子の娘にも「お父ちゃん」と呼ばれて慕われますが、堀木に「お前の、女道楽もこのへんでよすんだね。これ以上は、世間が、ゆるさないからな」と言われたことから、「世間というものは、個人ではなかろうか」と思いはじめます。やがて「自分という馬鹿者が、この二人(シヅ子とシヅ子の娘)のあいだにはいって、いまに二人を滅茶苦茶にするのだ」と考えるようになった葉蔵は、シヅ子の元を去りました。
その後はバーのマダムのもとで生活するようになった葉蔵ですが、ひょんなことから向かいの煙草屋の、人を疑うことを知らない純粋なヨシ子を内縁の妻とします。
ようやく平和な日々を手に入れたかに見えた葉蔵ですが、ヨシ子は出入りの商人に関係を強要されてしまいます。それを知った葉蔵は精神を病み、ヨシ子が隠していた睡眠薬で自殺を図ります。
一命をとりとめた葉蔵でしたが、地獄のような日々は続きます。酒と薬に溺れ、金を苦心するためについに父親にすべてを告白する手紙を出した後、脳病院に連れ込まれ、「人間、失格」と悟るのです。
やがて父が死ぬと、葉蔵は療養として田舎へ連れ戻されます。そしてそこで、「いまは自分には、幸福も不幸もありません」と語ったのでした。
あとがき
ここで語り手はまた第三者の男に戻ります。男はあるとき、バーのマダムから葉蔵の手記と前述の写真を見せられたことを語ります。葉蔵に興味を持った男でしたが、マダムも葉蔵の現在の居場所は知らず、近況についても知りませんでした。生死もわからなくなった葉蔵のことを、マダムは「人間も、ああなっては、もう駄目ね」と言いながら、最後には「神様みたいないい子でした」と振り返るのでした。
『人間失格』について、読書感想文で考察を書くときのポイント
読書感想文を書くときには、あらすじの他、自分の感じたことや意見を入れるのが一般的です。その際、作者についてや時代背景などの情報も鑑みた上で考察すると、より深みが出るでしょう。ここでは『人間失格』の読書感想文を書く上で、考察のヒントになりそうな情報を紹介します。
『人間失格』は遺書? 作者・太宰治の生涯
前述したように、『人間失格』は太宰治の遺作といわれています。生い立ちや複数の女性との関係、アルコールや薬物に苦しんだことなど、その内容は、太宰治自身の生涯とも大きくリンクします。
葉蔵と同じように心中未遂を繰り返した太宰治は、『人間失格』を書き終えた1948年、入水自殺しました。
『人間失格』と太宰治の生涯を重ねて読むと、彼が最期に言い残したかったことが見えてくるかもしれません。
『人間失格』で太宰治が伝えたいこととは?
『人間失格』には印象的なフレーズがいくつも登場しますが、中でも特に有名なのは、手記の冒頭の「恥の多い生涯を送って来ました」と、締めくくりの「神様みたいないい子でした」でしょう。
冒頭の言葉通り、手記に記されているのは、一般的には決して立派とは言えない男の生涯です。しかしその男を、マダムは「神様みたい」と称します。
それは葉蔵の弱さが、決して人間的な欠陥として描かれてはいないことも示しています。どうしようもなく悲しい葉蔵の生涯ですが、その感性やふるまいを、純粋さや優しさ、思慮深さととらえ、死後に「神様みたい」と言ってくれる人がいることは、一縷の希望のようにも思えます。
『人間失格』の意味とは
葉蔵は脳病院へ連れていかれたことで、廃人の刻印を打たれたとし、自身を「人間、失格」と語ります。しかしこれは、正気を失うことを指す言葉ではありません。葉蔵は「人間」として生きようともがき、彼なりに努力を重ねましたが、ついにこの世の中ではそれがかなわぬことを悟ったのです。そして世の中から認められなかったことを「人間、失格」と表現しているのではないでしょうか。
しかしそうなると、人間とはなんでしょうか。葉蔵を真人間扱いせず、ことあるごとに絶望させる堀木のような存在でしょうか。葉蔵と関係を持ち、しかし結局幸福にはできなかった女たちのことでしょうか。
『人間失格』は人の本質と、それを見つけることができずに朽ちていった男の姿を描く物語です。読書感想文の中では、「人間とはなにか」「そして人間として失格とはどういうことなのか」を、自分なりに考えてみるといいかもしれません。
小栗旬や二階堂ふみ出演の実写映画も話題に
-

出典:amazon
『人間失格』は、映画化もされています。特に蜷川実花監督が映像化した『人間失格 太宰治と3人の女たち』は大きな話題となりました。
映画『人間失格 太宰治と3人の女たち』の概要
2019年に公開された『人間失格 太宰治と3人の女たち』では、小栗旬が太宰治を、宮沢りえが妻の津島美知子を演じています。愛人の太田静子を演じた沢尻エリカや山崎富栄役の二階堂ふみとのラブシーンも大きな話題になりました。
ストーリーは太宰治とその女性関係が中心
映画のストーリーは『人間失格』そのものではなく、執筆当時の太宰治をモデルにしています。太宰治のほかにも坂口安吾や三島由紀夫など、多くの文豪たちが登場しました。
この物語は太宰治の生涯に着想を得たフィクションで、史実とは一部異なります。蜷川実花監督の作り出す美麗な映像と豪華なキャストが共演する、贅沢な映画です。
生田斗真主演の映画『人間失格』も
また、2010年には生田斗真主演の映画『人間失格』も公開されました。こちらは葉蔵を主人公にした、原作に忠実な映像化です。「『人間失格』を映像でも楽しみたい!」という人にはこちらもおすすめです。
-

出典:amazon
一人の男の人生から「人間」の在り方を問う小説
人間の弱さや脆(もろ)さを前面に描いた『人間失格』は、読んでいると胸が苦しくなる人もいるかもしれません。しかし、自身を「人間失格」と言った葉蔵を、マダムは「神様みたいないい子」と言ってくれます。そこには、「人間」であることを求め続けて「人間」以上に尊い存在になった葉蔵のイメージも読み取れるのではないでしょうか。
道化として過ごした少年期から、「人間」であろうと努力し続けた葉蔵の、その生き方そのものこそが「人間」の姿なのかもしれません。人間としての在り方を考えされられる一冊です。
※作品内には、現在では不適切とされる可能性を持つ表現がありますが、本記事では基本的に、作中の表現を生かした形で記載しています