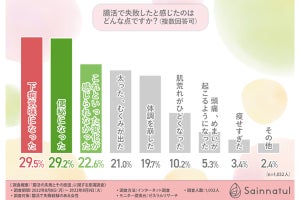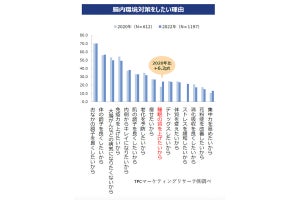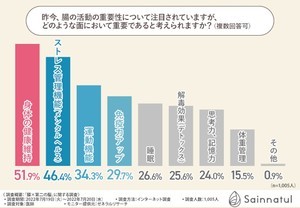サイキンソーは9月27日、「秋の味覚分析レポート」を発表した。同調査は、腸内フローラ検査サービス「マイキンソー」の利用者の中から、秋(9月~11月)に検査を受けた方3,211名の腸内フローラデータを収集し、分析したもの。
腸内フローラ判定(腸内フローラを構成する各菌のバランスを算出し、腸内環境の良し悪しを総合的に判定するもの)と、秋の味覚に関する質問項目の相関性を分析したところ、腸内フローラ判定の良さに特に影響がある項目は、「きのこ類」と「果実類」であることがわかった。
そこで、「きのこ類」と「果実類」にフォーカス。腸内フローラ判定の良し悪しとの関係性を見てみると、いずれも摂取頻度が増えるごとにA判定の割合が高くなることが判明。ただし、毎日1回以上2回未満の摂取群では、A、B判定が半数を越えるが、毎日2回以上のケースにおいては、A、B判定ともに減少傾向に。腸内細菌にとって良い働きをするとされている「きのこ類」や「果物類」であっても、毎日2回以上のケースにおいては、腸内フローラに悪い影響を与える可能性がうかがえた。
次に、腸内フローラ判定の高さに特に影響があった「きのこ類」に関して、「炭水化物(精白米、パン類、麺類、餅)」との関係性を探った。どちらも一般的に酪酸産生菌のエサとなることが知られているため、これらの摂取頻度と酪酸産生菌の保有割合を分析したところ、青で示した「炭水化物」の摂取頻度が1日1回未満の群のほうが、オレンジで示した1日1回以上の群と比較して酪酸産生菌の保有割合が高く、さらに「きのこ類」の摂取頻度が多い人ほど保有割合も高いことがわかった。