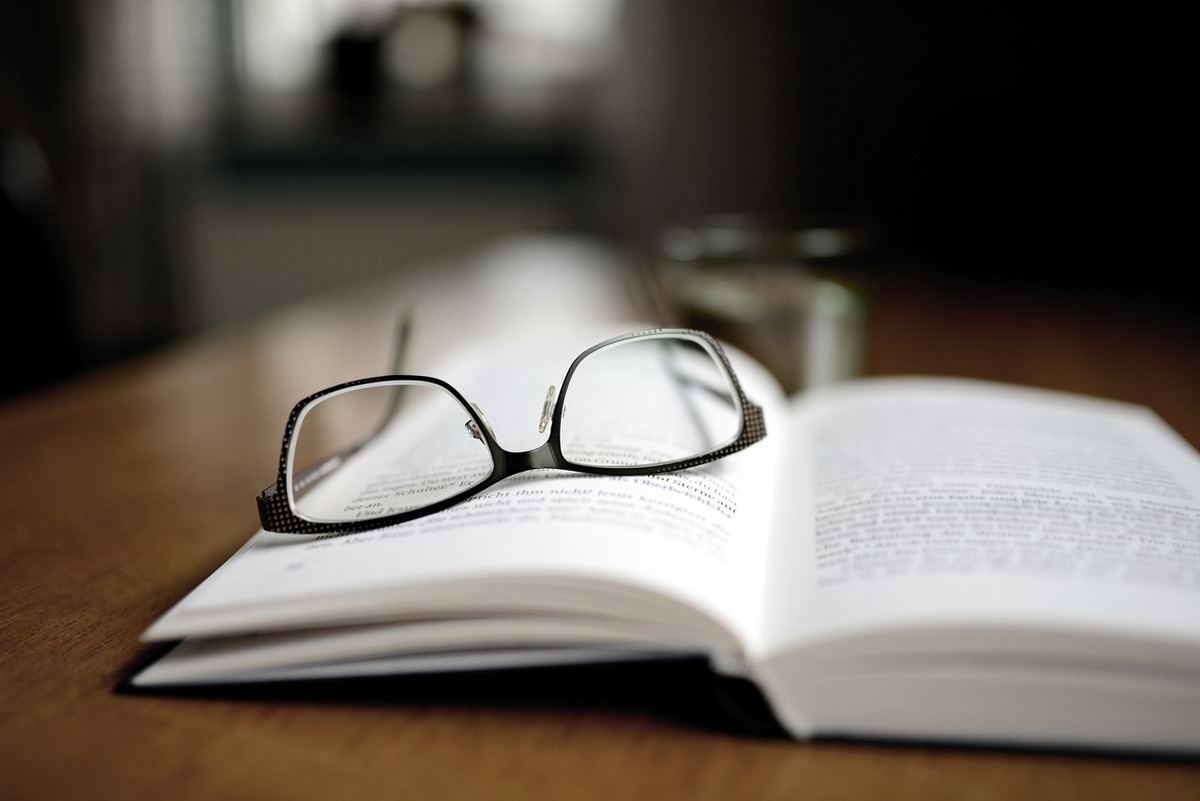うろ覚えの使い方例
うろ覚えは記憶に関連する表現ですので、ビジネスシーンなどふだんから使いやすい言葉です。うろ覚えの具体的な使用例をご紹介します。
記憶があいまいで自信がない場合
うろ覚えですが、その件についてはAさんが以前お話しされていた気がします。
仕事で自分が直接関係することははっきりと覚えていても、ほかの人の担当することに関してははっきりと覚えていないケースがあります。その際、正確な情報を伝えられているか自信がないことはよくあるでしょう。そのようなときにはうろ覚えであることを伝えて、記憶に自信がないことを述べるといいでしょう。
記憶はあいまいだがなんとなく覚えている場合
うろ覚えなので確認したいのですが、明日の集合時間は8時でしたか?
なんとなく記憶があっても、手帳やスマホなどに記録しておらず、確認しておきたいことがあります。そのようなシーンでも上記の例文のようにうろ覚えを使って確認することは多いです。
記憶はあいまいでも、なんとなく覚えていることを主張したい場合に会話に取り入れましょう。
前置きに用いる場合
うろ覚えで申し訳ありません。○○の件についてですが~
相手に伝えたいことがあっても、記憶があいまいではっきりしない場合もときにはあります。そのようなときはうろ覚えを用いて一言添えてから、内容を伝えるとスムーズです。
うろ覚えの類義語
うろ覚えは日常生活のなかで使いやすい表現とあって、似た意味を持つ表現も多いです。うろ覚えの類義語で、代表的なものをご紹介します。
「そら覚え」「空覚え」
「空覚え(そらおぼえ)」には「書いたものを見ずにすむよう暗記すること」「目にははっきり見えないことをなんとなく感じ取ること」があります。このほかうろ覚えと同じ「記憶が確かでないこと」という意味があります。
この場合の「空」の意味は「あてにならない、信頼できない」などです。そのため「空覚え」は「記憶があてにならない」という意味になります。
「生覚え」
「生覚え(なまおぼえ)」は「記憶が確かでないこと」「あまり気に入られていないこと」などの意味があるうろ覚えの類義語です。「生」は名詞につくことで「いいかげんな」「中途半端な」などの意味となりますので、「生覚え」が「中途半端な記憶=記憶が確かでないこと」を表します。
あまり耳なじみがないかも知れませんが「生返事」などと同じような使い方だと理解すると覚えやすいでしょう。
うろ覚えの英語表現
うろ覚えそのものを意味する英単語はありませんので、複数の言葉を組み合わせましょう。うろ覚えの代表的な英語表現をご紹介します。
half-remembered
「half-remembered」とは「記憶があやふやなことがら」などを指します。「half」とは「約半分」、「remembered」とは「remember」の過去分詞系で意味は「思い出す」です。
「half-remembered」を直訳すると「約半分の記憶」となり、あいまいな記憶であるうろ覚えを表す場合に用いられます。
faint memory
「faint memory」もうろ覚えの英語表現に適しています。「faint」の意味は「わずかな」「ぼんやりした」、「memory」の意味は「記憶の範囲」「記憶」などです。「faint memory」を直訳すると「ぼんやりした記憶」となり、うろ覚えの英語表現として適しています。
「faint」の代わりに「漠然とした」を意味する「vague」を用いるのも適切な表現のひとつです。
vague recollection
「vague」は「漠然とした」「あいまいな」などを意味する形容詞。「recollection」には「記憶」という意味がありますので「vague recollection」は「あいまいな記憶」という意味になります。
「vague」の代わりに「faint」「recollection」の代わりに「memory」を用いるのも適切な表現ですので、組み合わせを変えながら使ってみてください。
うる覚えはうろ覚えの方言! 文章ではうろ覚えを使おう
うろ覚えは「なんとなくは覚えていても記憶がはっきりしない」ことを意味する言葉です。一部地域の方言でうる覚えと表現される場合もありますが、標準語ではありません。ビジネス文書などの公的な場で使うのであれば、標準語であるうろ覚えが望ましいです。「うろ」の漢字表現を覚えておくと、正しい言い回しにつながりやすくなります。
うろ覚えは意外とビジネスシーンで使えるシーンは多い表現ですので、この記事で紹介した使い方を押さえておきましょう。
うろ覚えとうる覚えを混同すると、正しい言い回しがうろ覚えになってしまいます。正確にはうろ覚えであることをしっかり理解して、ビジネスの会話などで使っていきましょう。