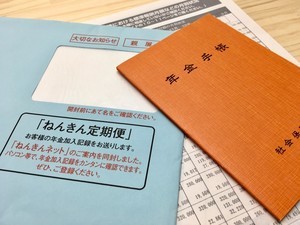令和3年度から年金の支給額が引き下げられたのをご存じですか? なぜ支給額が減っているのか、これからも減っていってしまうのか、支給額引き下げの背景と今後の見通しについて解説します。
国民年金(年金)とはどのような制度?
まずは、そもそも国民年金がどのような制度なのか、おさらいしておきましょう。
国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する公的年金の制度をいい、制度加入者は、老齢・障害・死亡により基礎年金を受けることができます。
国民年金には、「第1号被保険者」(自営業者・学生など)、「第2号被保険者」(サラリーマン)、「第3号被保険者」(第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者)と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。
また、一定の要件を満たせば、将来基礎年金を受給する事ができます。毎月の保険料は、16,610円(令和3年度)となっており、現金・クレジットカード・口座振替等の方法により納付できます。
なお、2年前納制度を利用することで毎月納付する場合と比較し、2年間で15,000円程度の割引となっています。
国民年金の支給額が4年ぶりに引き下げられた理由は?
この国民年金制度における年金の支給額が、令和3年度から0.1%引き下げられました。引き下げは4年ぶりであり、理由は"現役世代の実質賃金水準が下がったため"とされています。
年金の支給額は、物価や賃金の変動率を元に毎年改定されています。
これまでは「賃金と物価がともにマイナスで賃金が物価を下回る場合には、物価に合わせて年金額を改定」「賃金のみマイナスの場合には年金額を据え置く」という例外的取り扱いがあったため、賃金水準が下がっただけで年金額が引き下げられることはありませんでした。
しかし、平成28年に成立した年金改革法により、この例外が改められることになりました。現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、令和3年4月から「賃金が物価を下回る場合には、賃金に合わせて年金額を改定する」とルールが見直されました。
そのため、今回は過去3年間の賃金変動率が0.1%減、物価変動の指標である「消費者物価指数」※が横ばいだったことを受けて、年金改定率をマイナス0.1%としたのです。
年金支給額改定の際は、現役世代の負担を軽減するために、支給額を実質的に減らす「マクロ経済スライド」という仕組みがありますが、令和3年度は改定率がマイナスだったため、これらの調整は行われませんでした。
※全国の世帯が購入する各種の財・サービスの価格の平均的な変動を測定するもの。すなわち、ある時点の世帯の消費構造を基準に、これと同等のものを購入した場合に必要な費用がどのように変動したかを指数値で表している。消費者物価指数は純粋な価格の変化を測定することを目的とするため、世帯の生活様式や嗜好の変化などに起因する購入商品の種類、品質又は数量の変化に伴う生活費の変動を測定するものではないことに留意する必要がある
年金額はどのくらい減ったの?
年金の支給額は、令和2年度が65,141円(月額)であったところ令和3年度は65,075円(月額)に引き下げられました。これは年額では、老齢基礎年金の満額が781,700円(令和2年度)であったところ780,900円(令和3年度)に引き下げられたことになります。
今後も少子高齢化が進み、支給額は減額されていく可能性があります。もし支給額を少しでも増やしたいなら年金を繰り下げ受給することもできます。これは、年金を65歳で請求せずに66歳以降70歳までの間で申し出た時から繰下げて請求できる制度です。
1カ月繰り下げるごとに0.7%増額されます。1年繰り下げると8.4%、5年間繰り下げると最大で42%年金額が増額されます。つまり長生きをすれば得する制度なので、ご自身の生活スタイル等を考慮して選択するようにしましょう。
また、将来に備え支給額を増やしたい方は付加年金や国民年金基金という制度も利用できるので検討されても良いと思います。
今後の支給額はどうなる?
公的年金制度は、現在の現役世代が納めた保険料によって年金が支給される「世代と世代の支え合い」を基本としています。そのため少子高齢化が進む現行においては給付水準を維持することが難しくなってきています。
日本の公的年金制度は納めた保険料に応じて年金が支給される社会保険方式であるため、保険料を納めていない方がいても、国が崩壊しない限りは制度自体はなくならないと考えられています。
しかし、年金の支給額は今後も少しずつ下がっていく傾向にあると考えられるため、自身で将来の備えはしておく必要があるでしょう。