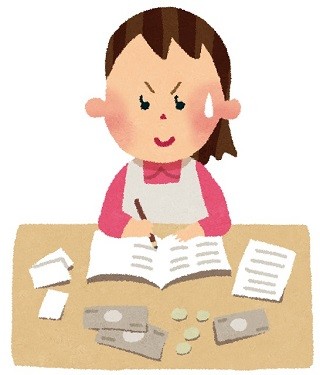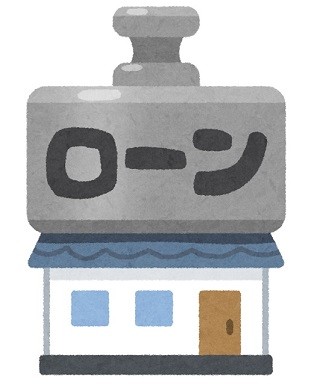既婚、未婚を問わず、若いカップルにとって、共働きか専業主婦(夫)になるかは悩ましい問題です。「二人で働くのが当たり前」という積極派もあれば、「これからは二馬力でないとやっていけないので」という消極派もあります。また一口に「共働き」と言っても、パートから正社員まで幅広く選択肢があります。最近は在宅ワークが急速に身近になりつつあります。
共働きが損か得かは、考え方や問題のとらえ方によっても違いますが、どんな要素があるのかを紐解いてみましょう。
専業主婦(夫)は優遇されている
共働きが損かどうかは別として、専業主婦が恵まれていることは確かです。書き出すと少々腹立たしい気もします。多くは夫を妻、主婦を主夫に置き換えられますが、主婦専用の制度もあります。
所得税も保険料も支払わず年金を受け取れる
仮に卒業と同時に結婚してそのまま専業主婦として過ごし、夫を見送って遺族厚生年金を受給しているケースを見てみましょう。夫との年齢差があると、妻が独自で国民年金に加入しなければならない時期はありますが、大枠は生涯所得税も国民年金保険料も支払わずに過ごし、老齢基礎年金と夫の厚生年金の3/4を遺族厚生年金として受け取ることができます。
配偶者控除、配偶者特別控除などにより所得税を削減される
所得税を支払わないばかりか、夫の所得税も配偶者控除などで軽減されます。余裕があるので専業でいられるわけですので、扶養控除は子供の分だけで十分ではないかと思います。
遺族年金には税金がかからない
あまり知られていませんが、遺族年金には所得税がかかりません。たとえ他の自前の年金を受給している方よりも多い遺族年金を受給していても、自前の年金には税金がかかり、遺族年金は非課税なのです。働いてきた女性の年金は、男女平等の時代でも地位や働き方の違いにより、男性よりはかなり少ないのが現実です。以前は55%程度と言われていました。遺族年金は夫の厚生年金額の3/4ですので、遺族年金の方が高額でも非課税で、それよりも少ない額でも自前の年金には課税されるのです。
遺族年金非課税は住民税や健康保険料等の負担額にも影響する
住民税も寡婦は前年の合計所得金額が125万円以下の人は均等割も所得割もかかりません。
さらに、多額の遺族年金を受け取っても収入がないとみなされる現象は健康保険・介護保険の保険料にも反映されます。遺族年金が非課税として収入がないとみなされても健康保険・介護保険の保険料が免除されるわけではありませんが、負担は小さくなります。下記は東京都世田谷区の健康保険料負担の計算例です。65歳未満は①~③を65歳~74歳までは①と②を負担します。ただし、遺族年金は賦課基準額算定対象には含まれないのです。
また収入がないとみなされるので、子供などの扶養になれ、健康保険料を節約できるケースもあります。
住民税の負担ランクは医療費の自己負担額や都バスのシルバーパス負担金にも影響します。
そもそも夫や妻の年金額が増える
配偶者加給年金とは夫より妻が若い場合、夫が65歳以降、かつ妻が65歳になるまで支給される額です。ただし、配偶者加給年金は夫と妻を入れ替えて読み取ることはでき、妻の専売特許ではありませんが、一般的にも年下の専業主婦のケースが多いはずです。
遺族厚生年金の中高年寡婦加算額
子のない妻や末子が18歳を超えると遺族基礎年金を受給できません。その代わり妻が40歳以降65歳になるまで、中高年寡婦加算が支給されます。
以前は他にも優遇措置があったのですが、順次廃止され昭和31年4月2日以後の生まれの方は上記の項目のみです。
所得控除
所得から差し引かれる控除には寡婦控除、寡夫控除、ひとり親控除などがあります。現実に一人親で困窮しているケースは多いでしょうからやむを得ませんが、元配偶者の扶養義務の徹底や生命保険の加入など、所得控除以前の制度改善や個人でのリスク回避は可能なはずです。
リスク管理面から考えてみよう
上記のように現在の社会制度は専業主婦に手厚過ぎるものとなっています。それでは専業主婦が得かというと、そうは言えません。高度成長期のリスクの少ないごく限られた期間だけに許されてきたシステムにすぎません。
夫婦で働けば、その分確実に収入が増え、老後の不安も少なくなります。病気やケガで働けなくなったとき、離別や死別などに対するリスクも少なくできます。
今まで一人で家計を担ってきた者(一般的に男性)のストレスは相当のもののようです。リタイアした直後の男性のタガが外れたような遊び方をSNSや身近に目にすると、それを実感します。コロナ禍もどこ吹く風のようにも見受けられます。ワークシェアリングを推進し、豊かな気持ちで仕事ができる仕組みが必要になってきていると実感しています。
離婚後に子どもを育てる厳しさ
また、子供をつくるということはどんな状況でも育て切るということです。働きつづけて収入の道を確保し続けるか、いつでも生活できるだけの収入が得られるスキルを維持して、リスクに備える必要があるのです。
専業主婦で、それまで何の準備もなければ、離婚後はゼロからスタートです。残りの人生で子供を育てて老後の準備が果たして可能でしょうか。離婚前提に結婚する方はないでしょうが、専業主婦を選択するのであれば、リスクがあることは把握しておくべきでしょう。
離婚による年金分割
分割できるのは婚姻期間の部分のみです。しかも半分になれば、それぞれ独立して生計を営む上で十分な金額と言えるかどうか疑問です。離婚後正社員となって自分の年金を積み立てられれば良いのですが、働き改革でパートや契約社員が増えて、コロナ禍で職を失う方もあります。途中から働き出して安定した正社員の立場を獲得するのは簡単ではないでしょう。
コロナ禍でばらまいた税金は、これから一体誰が負担するのかと考えます。そろそろ上記の優遇措置も見直す時期になっていかなければならないでしょう。基本はやはり、自分の生活は自分で守ることに尽きます。まずは個として、次は家族として、先々のリスクに備えることが求められます。
また収入の確保だけでなく、モノがあふれた豊穣な生活スタイルを見直し、競争に勝つために一人ががむしゃらに働き、もう一方がサポートに回る専業主婦(夫)の体制よりも、無理なく二人で働き、これからの時代に見合った地に足がついた生活スタイルを作り上げる必要がありそうです。不便を楽しむキャンプが人気なのは、シンプル生活への潜在的渇望の裏返しのようにも思えます。



.jpg)