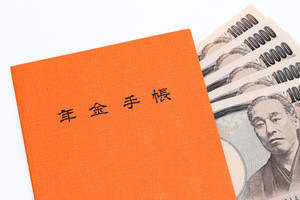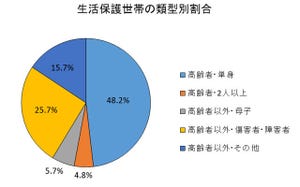「生活保護費は、生活が苦しくなったらもらうもの」と理解しているものの、なんとなくひとごとで詳しい内容までは把握していない人が多いのではないでしょうか。しかし、思わぬ病気や災害などによって、誰もが生活保護を受ける可能性があります。
本記事では、生活保護制度の内容やもらえる額の計算方法などをご紹介します。
生活保護制度とは?
憲法第25条に「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されているように、私たち日本国民には最低限度の生活が保障されています。
それにもかかわらず、病気やケガで仕事ができなくなったり、失業して収入が激減したりするなどにより、最低限度の生活すら危うくなることがあります。そのように生活が困窮した人を救うために施行されたのが「生活保護制度」です。(※1)
生活保護制度は、収入や資産がわずかで生活に困窮し、なおかつ経済的な支援をしてくれる親族がいない人に対して、最低限度の生活費を保障し、自立を支援することを目的としています。
厚生労働大臣が定めた基準で算出した最低生活費と世帯全員の収入を比較し、預貯金や不動産、受給可能な年金などの資産を差し引いたうえで、最低生活費を下回る分を生活保護費として支給する制度です。
生活保護の種類
生活保護には以下の8種類の扶助があり、申請者が必要とするものが支給されるようになっています。(※2)
| 扶助の種類 | 支給内容 |
|---|---|
| 生活扶助 | 食費や光熱費など生活に必要な費用 |
| 住宅扶助 | 住まいの家賃 |
| 教育扶助 | 義務教育に必要な学用品などの費用 |
| 医療扶助 | 医療機関を受診する際の費用(本人負担なし) |
| 介護扶助 | 介護サービスを受ける際の費用(本人負担なし) |
| 出産扶助 | 出産に必要な費用 |
| 生業扶助 | 高等学校等就学費や就労に必要な技能の取得に必要な費用 |
| 葬祭扶助 | 葬儀費用 |
上記のほか、火災で家が焼失したり、長期入院していた人が退院して住居が必要になったりというように、急にまとまったお金が必要になった人に対して、転居などの一時的な出費を補う「一時扶助」が支給される場合もあります。(※3)
さらに2018年からは、生活保護受給世帯の子どもが大学等に進学した際に「進学準備給付金」が支給されるようになっています。自宅通学の場合は10万円、自宅外通学の場合は30万円が支給されます。
受給対象の条件
生活保護の受給には、次のような条件があります。(※4)
- 世帯収入が定められた最低生活費を下回っている
- 預貯金や不動産などの活用できる資産がない
- 受給可能な年金や給付金を受給しても最低生活費に満たない
- 働くことができない、あるいは働けるところがない
このほか、生活保護の条件には含まれませんが、扶養義務者による生活費の援助が可能な場合は生活保護よりも優先されます(扶養義務者 : 配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母が該当します)。
生活保護を受給するまでの流れ
生活保護を受給するまでの流れは以下の通りです。
- 事前相談
- 生活保護の申請
- 生活保護受給の調査
- 生活保護費の支給
以下、順を追って説明します。
1. 事前相談
生活保護の申請先は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所です。まずは福祉事務所の生活保護担当に相談します。福祉事務所がない自治体は、役所に窓口があります。
2. 生活保護の申請
相談のうえ生活保護の利用が決まったら、生活保護申請書を提出します。その際、添付資料として給与明細や収入・資産申告書など必要書類も提出します。
3. 生活保護受給の調査
生活保護を申請後、以下の調査が行われます。
- 生活状況を把握するための家庭訪問
- 預貯金や不動産などの資産調査
- 扶養義務者による援助が可能かどうかの調査
- 就労による収入や年金などの給付の調査
- 就労できるかどうかの調査
4. 生活保護費の支給
生活保護費として支給されるのは、世帯全員の収入の合計額が最低生活費を下回る場合のみです。(※5)
【最低生活費】-【世帯全員の収入合計額や年金、預貯金など】=【生活保護費の支給額】
また、生活保護費の受給が決まった世帯は、以下のような義務があります。(※6)
- 毎月収入状況の報告
- 年に数回、福祉事務所のケースワーカーによる家庭訪問を受ける
- 就労が可能な場合は、就労の助言や指導の実施を受ける
- 世帯に収入が得られるようになった場合は、福祉事務所へ報告 など
上記に従わないと支給停止となる場合があるので注意が必要です。
生活保護費はいくらもらえるの?
では生活保護費とは、具体的にどれくらいの額をもらうことができるのでしょうか?
最低生活費と生活保護費の計算方法
まずは生活保護費を算出するために必要となる、世帯の最低生活費の計算方法をご紹介しましょう。
【最低生活費】=【生活扶助基準(第1類の基準額×逓減率)+第2類の基準額+経過的加算+各種加算の合計額】+【住宅扶助基準】+【教育扶助基準】+【介護扶助基準】+【医療扶助基準】
出産や葬儀がある場合は、上記に出産扶助、葬祭扶助が加わります。
生活扶助の第1類とは、食費や被服費など個人が消費する生活費のことで、第2類とは、光熱費など世帯全体にかかる費用のことです。(※7)
また、生活扶助には、世帯状況により基準額に一定金額が加算されます。加算されるものとして、障害者加算、母子加算、児童養育加算などがあります。
そして、この最低生活費から世帯全員の収入の合計額などを引いた金額が、生活保護費の支給額です。
【最低生活費】-【世帯全員の収入合計額や年金、預貯金など】=【生活保護費の支給額】
単身世帯と母子世帯の計算例
以下、単身世帯(50歳、東京都23区在住)の場合、母子世帯(母40歳・子13歳、東京都23区在住)の場合の最低生活費の計算例を、それぞれ紹介します(計算方法は2022年4月1日時点のもの)。最低生活費は世帯人数や居住地、そして年など条件によって異なるため、あくまで一例として参考にしてください。
<単身世帯(50歳)の場合>
- 生活扶助 : (第1類)47,420円 (第2類)28,890円
- 逓減率 : 1.0000 経過的加算 : 930円
- 住宅扶助 : 53,700円
(47,420円×1.0000+28,890円+930円)+53,700円=130,940円(最低生活費)
<母子世帯(母40歳・子13歳)の場合>
- 生活扶助 : (第1類)47,420円+47,750円 (第2類)42,420円
- 逓減率 : 0.8548 母子加算 : 18,800円 児童養育加算 : 10,190円
- 住宅扶助 : 64,000円
- 教育扶助 : 5,100円(+学級費、給食費など)
(95,170円×0.8548+42,420円+18,800円+10,190円)+64,000円+5,100円=221,861円(最低生活費)
参考 :
厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和4年4月)」
東京都福祉保健局「『住宅扶助基準額』の見直しについて」
上記の計算で求めた最低生活費と、世帯収入および資産を比較して、最低生活費を下回る額が生活保護費となります。
生活保護を受けるメリットとデメリット
生活保護を受けることにはメリットもあれば、デメリットもあります。
生活保護のメリット
- 必要最低限の生活費が保障される
- 医療費と介護サービス費の支払いが免除される
- 状況に合わせて、8種類の扶助が受けられる
- 生活保護を受けていても、大学進学の支援が受けられる
生活保護のデメリット
- 毎月、収入状況を申告しなければならない
- 車や不動産など資産となるものを持つことができない
- 年に数回、福祉事務所のケースワーカーによる家庭訪問がある
- 親族に扶養照会が入るので、生活保護を受けていることを知られてしまう
- カードローンなどで借り入れができない
- クレジットカードが利用できない
生活保護制度を正しく理解しましょう
生活保護制度について、どんな条件があり、どんな援助が受けられるのか、そして生活保護費の計算方法はおわかりいただけましたか?
生活保護を申請する前に、就労可能な人は仕事をして収入を得ること、持っている資産を売却するなどして生活費を作ること、親族の援助が受けられるのなら援助してもらうことなど、まずはできることをします。それでもなお生活が困窮している場合に生活保護が受給できます。
また、もし生活保護を受給することになっても、定期的な収入を得られるようになったら福祉事務所へ正しく申告しなければなりません。生活保護はどうしても収入が確保できず、最低限度の生活が送れない人のためのものであることを頭に入れておきましょう。