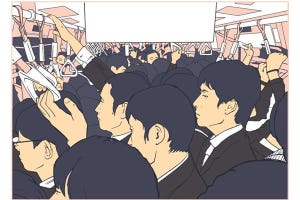日本の人事部「HRカンファレンス」運営委員会は、11月7日、11月12~15日、11月21~22日に「HRカンファレンス」を開催しました。
本稿ではその中から、東京会場で行われた、ビヨンド 代表取締役社長 仁藤和良氏による、特別講演「『今の新人』を定着・戦力化する、ビヨンドの『一皮むける』新人導入研修とは」を紹介します。
コミュニケーションの前提が異なるイマドキの新人
企業には毎年、数多くの新卒採用の新人たちが入社します。もちろん、当人のスキルや経験などは千差万別ですが、人事担当者にイマドキの新人たちはどのように見えるのでしょうか。まず、参加した人事担当者の声に注目しました。
「『やりたいこと』しかやりたくないと言う」、「(以前は)3年間で考えたキャリアを、彼らは半年で考えている」、「正解主義で間違えたくないという姿勢」「『自分のキャリアは~』と一方通行での情報発信力は強い」、「個人として見られることに慣れていて、入社して、その他大勢となることに不満を感じている」など散見されました。
人事担当者の多くは、今の新人たちに対して、戸惑いや不満を感じているようです。こうしたコメントに対して、仁藤氏は「着目したいのは、彼らが生まれ育ってきた環境です。大事なのは、私たちと『コミュニケーションの前提が異なる』という視点を持つことです」と話します。
ここで仁藤氏が紹介したのは、2019年入社の新人たちとインターネット関連サービスとの関係性。彼らが10歳の時に初代のiPhoneが発売され(2007年)、翌年にTwitter、Facebookの日本版サービスが開始、14歳の時にLINE、以降インスタの日本語アカウント、Tiktokなどが登場しています。
Twitterをはじめ「簡易コミュニケーション」の出現は、自分の思ったこと、感じたことを匿名で気軽に発信できるため、それに慣れ親しんだ新人たちは、自分の内面の感情に気付く機会が増えました。
また、SNSの普及により、自分の特性を「商品」として出しやすくなり、さらに個同士のつながりが促進されることでファンや顧客を得やすくなる。結果、人は自分の得意なことで稼ぎ、会社という固定された組織にしがみつかないで生きることが可能となります。
そして、サーチエンジンの検索性が向上した結果、貴重な情報に簡単にアクセスできたり、かつては有料だったコンテンツも無料で閲覧できたりします。また、何かしようとしたときに、事前に「比較された結果」や「まとめ」という、かつては足で稼がなければ得られなかった「答え」を得やすい時代になっていると話します。
ものの見方を変えるとコミュニケーションが変わる
一方、職場の先輩や上司は「リアルなコミュニケーション」を大事にし、先輩の所作を見て真似るという仕事の学び方を行い、そして、個性は大事なものの社会の不条理な面を我慢して受け入れてきました。その経験が彼らの「社会人はこうすべき」という「ものの見方」の前提を作ってきたのです。
仁藤氏は、この「ものの見方」を少し変えてみると、それに伴って受け入れ側の人事や、上司・先輩もコミュニケーションが変え易くなると言います。
仁藤氏「新人は、目的や意味が分からないから動かないだけ。正解を求め、失敗を恐れるのは、リスクを小さくして動きたい、事前に分かるなら失敗しない方がよいという考え方。指示通り理解しない、すべきことをしないのは、『それは本当に必要で、大事なことなのだろうか?』という自分の感覚を大事にしているということではないでしょうか。
これは彼らが生きてきた文脈からすると当たり前なことだし、ある意味、思考停止していた部分がある私たちからすると、彼らから教えられることも多いのではないかと思うのです」。
イマドキ新人の本当の特徴
そして、新人たちの特徴を次の3つに見立てていると解説します。
1.目的・意味づけ志向
2.全体・構造志向
3.そもそも論/本質を感じる力
仁藤氏「この特徴を踏まえて、丁寧に仕事の目的や意味づけを行い、仕事の断片ではなく全体像や体系をまず示し、上下関係ではなく『ヨコの関係』で接しながら、彼らが違和感を抱いたら、それを尊重し共に考えることが、新人に対する大事なコミュニケーション態度だと考えています」。
逆に、信頼関係ができるまでに気を付けなければいけない新人への接し方は、上司・先輩の持論からの「とにかくやってみろ」という粗い指示や、上下関係という権威を楯にした「一方的で断定的」な指示などだそう。
そして講演の後半では、「今の新人」の見立てに沿って設計された、ビヨンドの新入社員研修プログラムが紹介され、参加者たちは多くの気付きを得たようです。
昨今企業で必要とされるダイバーシティ。その本質は、年齢、性格、学歴、価値観など、それぞれ異なる立場から、違ったものの見方ができる人材が集まる組織を作っていくこと。
新人への接し方も根幹は同じ。育成や、職場での関わり方について課題を感じる方は、今回の内容を少し意識してみてはどうでしょうか。