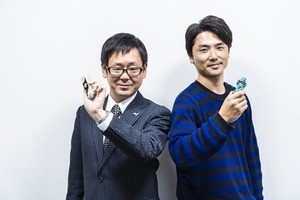塚田:キャスト陣はイケメンぞろいになり、画面を観ているだけで華やかというか、非常に楽しいと思います。僕も"大森学校"の卒業生たちと触れ合って、楽しく仕事ができました。みなさん「仮面ライダー」シリーズに出演していたときと違った魅力の出し方を考えてきてくださって、過去の役柄を引きずっていない、新たな役どころを演じ上げています。
――映画の脚本を谷慶子さんに依頼された経緯を教えてください。
塚田:オリジナルで時代劇の脚本を作るにあたって、どういう方に声をかければいいのかと考えました。さらに今回は舞台と映画が連動するわけで、ある程度プロデューサーの意見に耳を傾けてもらって、フレキシブルに直しに対応してくれる人でないとシンドイなあと思いました。谷さんは、もともと京都撮影所でスクリプターをやっていて、僕がAPを務めていた北大路欣也さん主演の『忠臣蔵』や『隠密奉行朝比奈』でご一緒していました。2人とも、齋藤光正監督という共通の師匠がいて、ずいぶんかわいがっていただきました。やがて谷さんは脚本家に転身して新たな活躍を始めるのですが、今回の企画も谷さんにお願いすればいけるかもと思って、京都にお住まいなのに打ち合わせがあるたびに東京へと来ていただきました。毎回、終電の新幹線で帰すという鬼のような扱いでしたが(笑)。
望月:たまには飲んで帰りますか?と言っていても、結局終電の時間ギリギリまで打ち合わせをしていましたね。
塚田:原作のある作品じゃなくて、オリジナルで一からキャラクターを作っていく楽しさと難しさがありました。シナリオを書く段階で多くのキャラクターを作っていかなくてはならないですから。石田監督も事前に各キャラクターをつかもうと、がんばってくださいました。
――石田監督にとって初めての「時代劇」となる本作は、同時に東映京都撮影所スタッフと初めて組んだ作品になるのですね。
塚田:石田監督はこの作品を撮るにあたって、時代劇作品を勉強され、モチベーションを非常に高めていました。
望月:京都撮影所のみなさんは、東京から「仮面ライダー」で"巨匠"と呼ばれている人が来るぞ、なんて身構えていたらしいんです。
塚田:一方で、石田監督は東映京都のスタッフは"厳しい・恐い"という先入観で現場に乗り込んできた。昔の邦画全盛期ならそんな話も聞こえてきましたが、今では必ずしもそんなに厳しいわけではないんです。でも、イメージが先行してしまっているから、石田監督は最初、どんな人を見ても"恐い"って言っていました(笑)。
望月:それでいて、現場では「遠慮しませんよ!」と張り切られていて、結果的には素晴らしいチームワークで作品を作ることができたと思います。お互い初対面ですから、スタッフとの"ぶつかり"みたいなものはありましたが、優れた作品を作るためのよい意味でのぶつかりだったように思います。
――舞台版は、『宇宙戦隊キュウレンジャー』でメインライターを務められていた毛利亘宏さんが脚本・演出を手がけるそうですね。
望月:それは、以前から毛利さんと組んで舞台作品を手がけてきた中村(恒太/プロデューサー)の力が大きく働いています。舞台で多人数のキャラクターをさばいて、全員を立たせることができる実績を買われての起用ですね。『キュウレンジャー』でも、毛利さんのそういった手腕を期待して、シナリオを依頼していました。
塚田:先に映画を作り、その後で舞台へとバトンを託すという形になります。全体のラフな設計図はもう出来上がっていますが、舞台をどのように作っていくかはこれからの作業となります。
――「東映ムビ×ステ」という新企画についてですが、実際に「映画」と「舞台」との連動作品を作り上げてみて、どのようなメリットがありましたか?
塚田:まず「異なるもの同士をかけあわせて、新しいものを生みだす」ということがあります。それは実際に作っていく中でも、期待から確信へと変わっていきました。具体的に言うと、衣裳やメイクによる"キャラクター作り"の部分です。映画だけで時代劇をやるとなると、比較的リアルな世界になっていくところですが、舞台のケレン味といいますか、2.5次元の風味を備えた派手目なビジュアルを取り入れて、リアルな中にも漫画チックな雰囲気を盛り込んでいます。映画と舞台のスタッフが分担して、ひとりひとりのキャラクターに肉付けしていくという作り方は、今までにないものでした。全体の作り方についても、当初から「映画から舞台へ」と続いていく企画であることを活かして、映画だけ、舞台だけという狭い世界から飛び出し、キャラクターの活躍の幅を広げていくことができました。舞台から逆算して映画に登場させたり、映画で膨らませたキャラクターを舞台でさらに動かすことができるなど、相互にキャッチボールを行いながら作品作りを行えたことが、非常に面白かった部分です。
望月:ひとつの物語でじっくりと描くことができるのは、はっきり言って主役キャラ数名に絞られてきます。でも1本作ると欲が出てきて、「映画では脇にまわった○○の物語を描いてみたい」なんて思うんですよ。映画に出てきた何人かのキャラクターを別の角度から捉えた物語を舞台で描くことができたら、あとはもう無限ですよね。舞台で生まれたキャラを、また次の映画の世界で描くとか……。今後も映画と舞台だけに留まらず、ひとつの世界観のもとでいくつもの物語を作り続けることができたらいいな、と願っています。
――今回「時代劇」というジャンルを選ばれたわけですが、時代劇ならではの魅力にはどんなものがあると思われますか?
塚田:まずクリエイティブな考えとして、現代劇にはない要素……社会の仕組みや文化、着ているものの違いなどを表現するのはとても面白いですね。『純恋の剣』の主人公・凛ノ介の人物設定は隠密、つまりスパイなんです。隠密としての任務を遂行するためには仲間をも見殺しにしなければならないという「非情さ・不条理さ」と、「恋愛」との板ばさみになって苦悩する凛ノ介の姿を描いています。なかなか現代の設定には置き換えにくい物語であり、こういう部分は時代劇でしか描けない魅力的な物語なのではないか、と思います。
望月:現代よりも「死」というものが身近に存在する「時代劇」というジャンルに魅力を感じています。さっきまで普通に話していた人が無残に斬り捨てられてしまうような儚さ、病を患った人間の脆さは、平和で豊かになった現代日本では中々リアリティを持って描けない。だからこそ、衣装や言葉遣いの違いをも取り込んで、「時代劇」というジャンルの中で今よりも刹那的な「人生」を必死に駆け抜ける人間たちを躍動させられるんです。
塚田:僕が東映に入ったころ、90年代前半はテレビ時代劇が一週間に6・7本、ほぼ毎日どこかのチャンネルで時代劇ドラマの本放送をやっていたけれど、今では地上波のレギュラー時代劇がなくなってしまいました。
望月:観る側も作る側も、時代劇に接する機会が減ってきていると言っていいでしょう。そんな中で、"東映といえば時代劇"というイメージが昔からありますし、僕たちがこういう企画を立ち上げた以上はちゃんとしたものを作らないといけないな、という使命感を持っています。
――今は「時代劇はご年配の方が観るもの」というイメージがあるかもしれませんが、もともと時代劇は野心的・挑戦的なドラマを描いた作品が多く、若者の興奮や感動を呼び起こす人気ジャンルでしたからね。『GOZEN』が若者層に強くアピールすることによって「時代劇って面白い!」と盛り上がっていただきたいものです。
望月:若い方に楽しんでいただきたいという思いは、非常に強いです。
塚田:今回の『GOZEN』は少々突飛なキャラクターこそ出てくるものの、ファンタジーではなく、リアリティを重んじた本格的な時代劇として作っています。徳川二代将軍・秀忠の時代、登場人物たちが一生懸命生きている姿をリアルに描くよう努めました。そういう意味では、若い方たちにこそ観てもらいたい作品なんですけれど、一方でおじいちゃん、おばあちゃん世代が観てもしっかりと作品世界に入ることができる、非常に間口の広い作品ができたと思っています。ぜひたくさんの方々に『GOZEN』の世界を体験していただきたいですね。
(C)2019 toei-movie-st