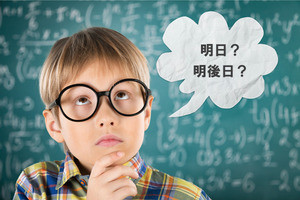新しい冷蔵庫を買おうと思って、いろいろとカタログを集めてみたけど、肝心の値段が分からない。「オープン価格」っていったい何なの? というわけで今回は、「価格」に関する用語の中から「オープン価格」と「希望小売価格」について解説します。
■「オープン価格」と「希望小売価格」とは
「オープン価格」は、メーカーが定価や希望小売価格を設定せず、実際の販売価格を小売業者に一任するものです。おもに家電製品などで用いられています。
これに対し「希望小売価格」とは、メーカーが小売店などに対し「この商品はこのくらいの価格で販売するのが妥当です」という意味で示す、いわば参考価格です。
■「定価」から「希望小売価格」へ
一昔前まではメーカーが決定した販売価格、いわゆる「定価」で販売されていました。定価は、基本的に値上げ値下げは認められません。しかしながら、実際に販売する小売店側は、地域によって流通コストも違えば売れ行きにも差が生じます。にもかかわらず、メーカーに強制された定価でしか販売できないとなると、採算が取れません。小売店にとっては死活問題です。
このことが独占禁止法に触れるとされたことから、メーカーは、「このくらいの価格で販売してほしい」「想定価格はこのくらいです」ということを意味する、希望小売価格を提示するようになりました。希望小売価格には、定価のような強制力はありません。
■「希望小売価格」から「オープン価格」へ
メーカーが希望小売価格へと切り替えたことで、小売店は自由に販売価格を設定することができるようになりました。しかし今度は、小売店側がこの希望小売価格を利用するようになってしまいます。
たとえば、メーカーの希望小売価格が2万円、市場での相場が1万円である家電品を、相場どおり1万円で販売するとします。この時、小売店はあえて「希望小売価格」を表示し、「メーカー希望小売価格の50%OFF」などと安さを強調するようになったのです。
しかし、これでは消費者がまるで半値で購入できると錯覚してしまいますし、メーカー側としても、「半値で売られてしまうような安物ブランド」のイメージがついてしまいます。これがいわゆる「二重価格表示問題」です。これを受けてメーカー側は、実際の販売価格を小売業者に一任するオープン価格を採用するようになったのです。
■オープン価格のデメリット
さまざまな問題から二転三転し、現在では多くのメーカーがオープン価格を採用しています。しかしオープン価格には、「カタログを見てもいくらで買えるのかが分からない」という欠点があります。消費者にとって価格が見えないことは不安要素でしかありません。
あくまでもメーカーが設定するのは卸価格だけですから、消費者は小売店が決めた価格を信用するしかありません。それゆえ、なんのリサーチもなしに出かけて行った結果、「市場相場7万円のテレビを10万円で買ってしまう」なんてことも起こり得るのです。
もちろん、そんな小売店はほんの一握りでしょう。しかしながら、オープン価格にはそんな危険性も含んでいるということを、われわれ消費者は認識しておくべきでしょう。
今回は「オープン価格」「希望小売価格」を中心に、価格表記についてお話ししました。今までオープン価格に疑問を抱いていた人も、その理由に少しでも納得していただけたでしょうか。メーカーや小売店は少しでも高く売りたい、消費者は少しでも安く買いたいのが本音です。さまざまな機関が公正な取引を監視しているとは言え、われわれ消費者も、自ら適正な価格で買うための知識を身に付けることが必要ですね。