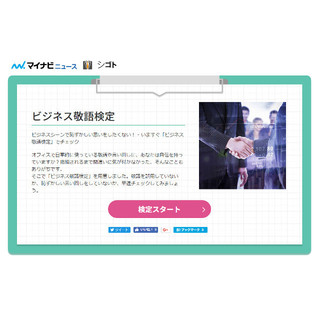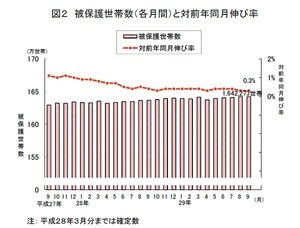厚生労働省は12月13日、「平成27年(2015年)都道府県別生命表」を発表した。同調査は、人口動態統計調査及び国勢調査のデータを用いて、2014年~2016年の死亡状況を都道府県単位で表したもの。1965年から5年ごとに作成しており、今回が11回目となる。
世界トップクラスの長寿大国、日本。いつの時代も女性の方が長生きする傾向にあるようだが、家族のためにと定年まで勤め上げた男性の寿命が短いというのは、何とも切ない気がする…。女性も生涯働き続けることが多くなった近年、男女の寿命に変化はあったのだろうか。早速、調査結果を見てみよう。
平均寿命の男女差、6.23年
調査によると、平均寿命(0歳の平均余命)は全国の男性で80.77年、女性は87.01年となり、平成22年の前回調査と比べると、男性は+1.18年、女性は+0.66年となった。
これを都道府県別にみると、男性は「滋賀県」(81.78年)が最も高く、次いで「長野県」(81.75年)、「京都府」(81.40年)と続いた。一方女性は、「長野県」(87.675年)で最も高く、次いで「岡山県」(87.673年)、「島根県」(87.64年)という結果に。平均寿命の最も高い都道府県と最も低い都道府県との差は、男性が3.11年、女性は1.74年となった。
男女の平均寿命の差は、全国で6.23年。都道府県別にみると、「青森県」が7.27年で最も大きく、次いで「沖縄県」(7.17年)、「鳥取県」(7.10年)となっている。一方、男女差の最も小さな都道府県は「愛知県」の5.76年。次いで「滋賀県」(5.79年)、「岐阜県」(5.82年)と続いた。
平均寿命の推移
1965年~2015年までの平均寿命の推移をみると、男女ともに増加傾向が続いており、男性は1965年から13.03年の増、女性は14.09年の増となった。都道府県別では、男性では「長野県」「神奈川県」の2県、女性では、「沖縄県」(1975年以降)、「岡山県」の2県が常に上位10位以内にランクインしていることがわかった。
死因別死亡確率
死因別に死亡確率をみると、男性は「悪性新生物」(29.38%)、「心疾患(高血圧性を除く)」(14.26%)、「肺炎」(11.24%)が上位に。「悪性新生物」と「心疾患」及び「脳血管疾患」(8.08%)を合わせた三大死因の死亡確率は、51.72%となった。
一方、女性の死因別死亡確率の上位は、「悪性新生物」(20.35%)、「心疾患(高血圧性を除く)」(17.41%)、「老衰」(13.24%)という結果に。また、「脳血管疾患」の死亡確率は9.40%であったことから、三大死因の死亡確立は47.16%となった。また、「老衰」については男女差が大きく、女性13.24%に対し、男性は4.75%だった。