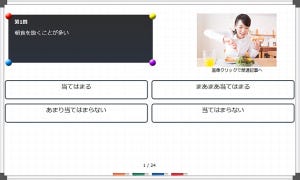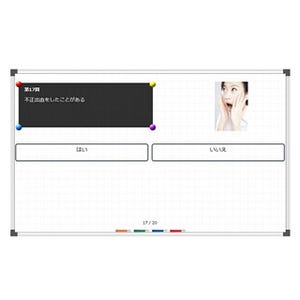生理のトラブルのほか、次に挙げる病気にも注意が必要です。
・卵巣のう腫
子宮や卵巣の病気の中でも、10・20代の若い世代に多発しているのが、卵巣にできる良性腫瘍(しゅよう)である「卵巣のう腫」です。初期には自覚症状がほぼありませんが、腫瘍が大きくなると、下腹部にしこりができ、違和感やお腹の張りを覚えることもあります。また、腫れた卵巣がねじれを起こし(卵巣茎捻転)、激しい痛みが生じる場合もあります。・子宮内膜症
「子宮内膜症」は、子宮内膜に似た組織が子宮以外の場所にでき、炎症や癒着を起こす病気です。それによって、ひどい生理痛や経血量の増加といった症状を引き起こします。初潮から年数を増すごとに増加する傾向があり、発症のピークは40代ですが、20代でかかる人も少なくありません。・バセドウ病
「バゼドウ病」は、首にある甲状腺という器官から出る甲状腺ホルモンの分泌が過剰になる病気で、特に20・30代の若い女性に多い病気です。甲状腺ホルモンには新陳代謝を促す働きがあるため、多すぎると代謝が異常に活発になり、体のかゆみや口のかわき、甲状腺が腫れる、脈拍数が多くなる、食べているのにやせてくる、眼球が出てくるなどの症状が現れます。甲状腺の病気にはほかに、甲状腺ホルモンが少なくなって代謝が低下し、疲れやすくなったり、むくみや体重増加などの症状が出たりする「橋本病」という病気もあります。・子宮頸がん
女性特有のがんの中でも、近年、20代の女性の間で増えているのが「子宮頸がん」です。子宮頸がんは、子宮の入り口付近にできる悪性腫瘍。その発生には、主にセックスを介してうつる「HPV(ヒトパピローマウイルス)」が関係していると考えられています。通常、初期には症状がまったくなく、進行すると、生理以外の出血、セックスの際の出血、おりものの変化などの症状が出ることがあります。重症化すると命に関わりますが、検診などで早期に発見できれば、比較的治療しやすいがんだと言えます。
20代女性がなりやすい病気には、自覚症状がないものや症状がわかりにくいものも多いので、早期発見のためには定期的な検診が不可欠です。ぜひ20代のうちから、気軽に通えて相談しやすい、かかりつけの婦人科を見つけておきましょう。
※画像は本文と関係ありません
記事監修: 鈴木俊治 医師
葛飾赤十字産院 副院長
日本産婦人科医会 副幹事長
1988年長崎大学医学部卒業、日本医科大学付属病院産科婦人科学教室入局、葛飾赤十字産院産婦人科派遣をへて米国ロマリンダ大学胎児生理学教室へ研究留学。帰国後、日本医科大学産科婦人科学講師、学助教授、東京臨海病院産婦人科部長を経て、現在は葛飾赤十字産院にて副院長を務める。