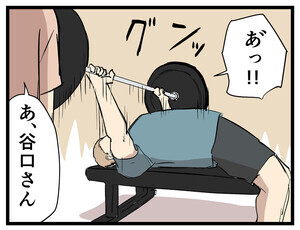ソルベイ製薬は15日、社会不安障害(Social Anxiety Disorder、通称SAD)による社会的損失について着目したセミナーを開催した。日本におけるSADの患者は推定300万人以上と言われている中、SADを未治療のままにしておくことでどれだけの労働損失が及ぶのか。和楽会 横浜クリニック院長で東洋英和女学院大学人間科学部教授の山田和夫氏がSAD患者の実態・治療について、昭和大学 薬学教育推進センター社会薬学教室教授の亀井美和子氏が薬剤経済学に基いた労働損失についてを語り、SADの治療の必要性と社会損失を訴えた。
SADとは、人前で話したり、食べたり、書いたりすると極度の「不安」や「恐怖」を感じ、赤面、震え、多量の汗をかくといった症状を起こす疾患のこと。一般的に極度の"あがり症"と言われる症状をさす。SADの程度によっては、仕事に支障をきたし、欠勤、退職といったケースも多々あるという。
山田氏は「非婚化、ひきこもりの原因の1つとされるコミュニケーション不全は、背景にSADが隠れています。SADは従来『内気な性格』が原因と思われてきましたが、性格なら慣れで克服できます。そうでないものが疾患(SAD)なのです」と、SADに関して一般に正しい認識されていない現状を指摘した。山田氏が院長を務める横浜クリニックには、SADで悩む患者が5年間で1,000人以上に上る。またSADで悩む人は1位会社員、2位学生、3位主婦という順番になるとし、1位の会社員の職種比率では、技術職が40.6%も占めることを明らかにした(2008年 SAD NETアンケート調査より)。
「SADのテーマは『治療して本来の姿を取り戻す』こと。働き盛りの20代、30代が受診に対して思い留まっているという結果がでているが、多くの人に(SADが)治療で治ることを理解して、治療に望んで欲しい」(山田氏)。
後半の亀井氏による講義では、薬剤経済学の視点からSADによる労働損失額について話された。薬剤経済学とは、費用と結果の両面からみた比較分析で、「効果だけを追い求める」のではなく、"費用対効果"をみる経済学だ。
亀井氏は「SADの治療薬は一見、費用がかかると思われがちですが、約1年で治療できる点や、健康保険適用されている製薬なので、1日にかかる治療費は少なく、"費用対効果"が高いと言えるのではないでしょうか。残念ながら、日本において、SADの治療率は極めて低い現状。研究データによると、20代~60代のSADによる労働損失額は1兆4,795億円に上ります。患者にとってだけでなく、企業や日本経済にとってもSADの治療は重要だと考える必要があります」と述べ、SADへの理解と早期治療の啓発を呼びかけた。