よしこ「実は私も共著でマンガの描き方本を出していたりするんですね。こちらの3冊。美術出版社が出していた季刊の漫画情報誌『Comikers』で、マンガ家の菅野博之先生と山本貴嗣先生と一緒にやっていたマンガ入門的な連載をまとめたものです」
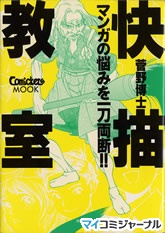 |
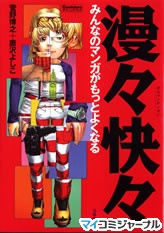 |
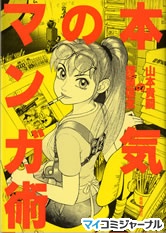 |
|
菅野博之・唐沢よしこ著『快描教室-マンガの悩みを一刀両断!!』(画像左)、同じく『漫々快々-みんなのマンガがもっとよくなる』(中央)、山本貴嗣・唐沢よしこ著『山本貴嗣の謹画信念-本気のマンガ術』(右) |
||
なをき「菅野先生との本は技法書として、ほかの本ではあまり触れてないような細かい点、動いたときの服のシワとか、メガネのツルとか、ドアノブの大きさをどう描けばいいのかといった、かゆいところに手が届く内容がおもしろく描かれている本で、素人さんからプロでバリバリ描いている方まで、結構使える本じゃないかなと」
よしこ「いっちょ俺も描いて見るか、という気になる本ですね。これから本格的に描き始めたいと思う人や、同人活動をしている人、とにかくマンガを上手に描きたいと思う人に読んでほしい本です」
なをき「まだまだ本屋さんで手に入りますので、ぜひ読んでいただきたいですね」
――それに比べて、山本貴嗣先生とお出しになった本のほうは……。
よしこ「かなりプロ志向の本ですね。もちろん、これから描き始める人にも参考になる本ですが、どちらかというとある程度描いてきて、自分のマンガ力をもうワンランク上げたい、という人のほうが受け取るものは多いかもしれません。この本の企画のきっかけになったのは、昔、山本先生がアシスタントに来た人向けに作った指導要綱のようなものを拝見したことだったんですよ」
――そのマニュアルには、どんなことが書いてあったんでしょう?
よしこ「例えば、先生が描いたキャラクターにベタを塗るとき、ちょっとはみ出しちゃったとする。"じゃ、ちょっと線を膨らませて塗って、誤魔化しちゃえ"などということは、死んでもやってくれるな! と(笑)。"その線一本を作家がどれだけ考えて描いたのかわかって欲しい"というようなことから始まって、作画作業で見過ごしがちなポイントがみっちり描いてありましたね。なをさんもすごく参考になった、と」
――実際の仕事の現場のノウハウがもとになっている……。
なをき「そこから出発して、それ以上の本になってますね」
よしこ「では最後に、変わり種としてアメリカのマンガ入門書でも」
なをき「アメリカンコミックの描き方ですね。高校のころ、洋書店にまで行って買ってきた本なんですけれども、そうか、アメコミってこうやって描くんだ、みたいな」
よしこ「向こうは同じマンガ家でも会社員みたいな形態で働いてる人が多いんですよね。職業としてのアメコミ作画法を教えるって感じなので、根性論みたいなのが頭にないんですよ。技法から入ってるから、最初の30ページでもうパースの話が出てくる。日本の入門書では、ありえないですよ。大抵キャラクターの描き方が先で、パースなんてちょっとしかやりませんもん」
――ここまでいろいろ見てきましたが、こういった知識は今のお仕事に直接関連しているんでしょうか?
よしこ「これはウチの宣伝になりますが、マンガ入門本マニアの知識を活かした『BURAIKEN』というマンガがあります。主人公は剣術の使い手なんですけれども、すごく物知りなんですね。ウンチクを披露して相手がひるんだ隙に斬るという(笑)」
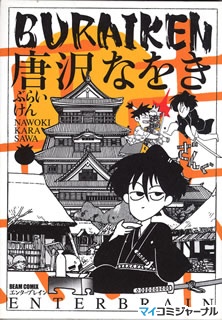 |
|
唐沢なをき先生の『BURAIKEN』 |
――そんな卑怯な勝負を……。
よしこ「毎回、ペットの飼い方とかウンチクを披露している間に相手を倒すんですけれども、その中でマンガの描き方というのがあって」
 |
――これまでに得た知識を余すことなく活用されてますね。
よしこ「そのウンチクにかなり参考になっているのが、最初にあげた冒険王編集部編の……」
なをき「『マンガのかきかた』がもとになっているわけですね」
よしこ「この中に出てくるのが、マンガの歴史ということで"鳥獣戯画"とか"写実画とマンガの違い"、"デフォルメの仕方"などを指南するという、マンガ入門本のお好き方には、かなり笑える内容になっています」
――なるほど。こちらもぜひお読みいただきたい本ですね。どうもありがとうございました。


