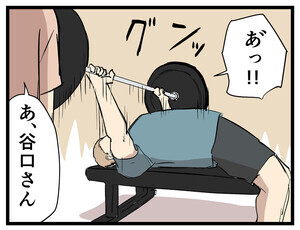病院を受診し、処方せんを持って薬局に行くと、薬剤師から「後発医薬品(ジェネリック医薬品)を希望しますか?」と聞かれたことは誰しもあるはず。大きな違いはなさそうだし……と、なんとなくそのまま「はい」と答えている方も多いのではないでしょうか。
さらに、2024年10月、選定療養制度が改正され、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で先発医薬品の処方を希望する際は、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金を支払うことになりました。
とはいえ、子どものいる保護者は「きちんと治療するため、子どもに合った薬を選択したい」という思いが強いことでしょう。子どもが使う薬だからこそ、安心・納得して使えるものを処方してもらうためには、後発医薬品(ジェネリック医薬品)と選定療養制度について知っておく必要があります。
そこで今回は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)と選定療養制度について、小児科の先生にインタビューを実施!そもそも先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)はどう違うのか、選定療養制度の改正が薬の選択にどのように影響するのかなど、疑問をぶつけてみました。

高円寺こどもクリニック 院長 保田 典子先生
同じだけど違う!?
先発医薬品・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の違いとは?
――まず、先発医薬品の定義について教えていただけますでしょうか?
先発医薬品は、いわゆる「新薬」とも呼ばれていて、新たに開発・承認された医薬品のことです。人に対する有効性・安全性に関する厳しい臨床試験「治験(ちけん)」をクリアしたものだけが先発医薬品として承認を受けています。 |
先発医薬品を開発した医薬品メーカーには特許権が与えられるため、特許期間※の間は、他の企業が同じ有効成分や効能・効果を有する医薬品を製造・販売することはできません。
※出願から20~25年
――先発医薬品は“新しい薬”なんですね。では、これに対して、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の定義も教えていただけますでしょうか?
特許期間が終わった先発医薬品と同じ有効成分を用い、その含量等の規格も同じものが後発医薬品(ジェネリック医薬品)です。開発にかかるコストが少なく済むため、先発医薬品と比べて低価格で提供されることが一般的です。 |
――有効成分は同じとのことですが、先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)には、どのような違いがあるのでしょうか?
先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、一般的には同じ有効成分を同じ量含み、効能・効果、用法・用量等が原則的に同一とされていて、安全性も同等です。しかし、医薬品は有効成分だけでできているわけではないので、全く同じかといわれれば、そうではありません。例えば、塗り薬では、患部の保護や有効成分を溶かす役割を果たす「基剤(きざい)」や剤形まで同じとは限りませんし、塗りごこちも変わってきます。飲み薬では味も異なります。 |
――有効成分が同じでも、そのような違いがあるのですね。そんな中、薬局に行くと「後発医薬品(ジェネリック医薬品)を希望しますか?」と聞かれることが多く、後発医薬品(ジェネリック医薬品)が推奨されている印象があるのですが、なぜでしょうか?
高騰する国の医療費を抑制し、医療保険の財政を改善するのが狙いです。後発医薬品(ジェネリック医薬品)は先発医薬品よりも安価ですので、患者さまにとっても自己負担の軽減につながります。 |
選定療養制度の改正で、
先発医薬品を患者さんが選択した場合に特別料金が発生
――最近は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)をさらに多くの人に選択してもらうために選定療養制度が改正されたと聞きました。
そもそも選定療養制度とは、追加費用の負担によって保険適用外の治療を保険適用の治療と併せて受けることができるものですが、2024年10月に改正され、新たに「長期収載品の選定療養※」が始まりました。「長期収載品」とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のこと。「医療上の必要がある場合」などを除き、患者さまの希望により、長期収載品の処方を受ける際は選定療養の対象となり、特別料金の支払いを求められるようになりました。 |
長期収載品を希望する場合の特別料金は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1の金額に相当します。
※ すべての長期収載品が対象となるわけではありません。
――この改正によって、どのような影響があるのでしょうか?
ますます後発医薬品(ジェネリック医薬品)を選ぶ流れになると思いますので、先ほどもご説明した通り、患者さまの金銭的な負担は軽くなるでしょう。ただ、塗り薬に関していえば、基剤が塗りごこちに影響するため、個人差が出るかもしれません。 |
後発医薬品(ジェネリック医薬品)について知っておいてほしいこと
――このような制度のことを知らない患者さんもいそうですよね。必ずしも後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用しなければいけないというわけではないのでしょうか?
もちろん、そういうわけではありません。特別料金を支払えば、理由は問われず先発医薬品を選ぶことができます。また、医療上の必要性が認められる4つのケースは選定療養の対象外となり、特別料金はかかりません。実際、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用して副作用が出てしまったお子さまに対しては、先発医薬品を処方するようにしています。 |
なお、薬局に後発医薬品(ジェネリック医薬品)の在庫がなく、先発医薬品しか提供できないケースも選定療養の対象外となり、特別料金の支払いは不要です。保田先生は「症状が落ち着いている場合は、医薬品を変えずに使い続けたほうが良い」といい、医薬品の安定供給の重要性を指摘しました。
――もし、合わない医薬品を選んでしまうと、どのようなリスクが考えられますか?
塗り薬に多いのですが、先発医薬品であれ後発医薬品であれ基剤の差で有効成分の浸透具合が変わるだけでなく、かぶれなどのアレルギー反応を引き起こしてしまうリスクが考えられます。そうなると、原因は基剤にあるかもしれないのに、その医薬品自体の使用を控えなければなりません。基剤が違うことで問題なく使えていたとしたら、患者さまが受ける損失は大きいです。 |
子どもに合う医薬品を出してもらうため、保護者が意識しておきたいこと
第一に「定期的に通う」ことですね。「後から診察する医者のほうがより正確な診察ができる」という意味の「後医は名医」との言葉がありますが、特に塗り薬は初診でぴったり合う医薬品を処方するのは難しいのが実情です。きちんと病院やクリニックに通っていただき、経過に応じて試行錯誤しながら合う医薬品を見つけていくことが一番の近道だと思います。 |
塗り薬での治療は長期にわたるため、試行錯誤が欠かせないと力を込める保田先生。塗るのが負担にならないような塗り方や適切な使用量を細かく指導し、保護者と二人三脚で子どもの治療に向き合っています。
――過去に処方された医薬品があれば、その所感もお伝えしたほうが良いのでしょうか?
すでに他のところで診察を受け、医薬品を処方されたことがある場合は、お薬手帳を見せてもらいながら経過をお伝えいただくようにしています。「この医薬品を使うと調子がよかった」「効き目がイマイチだった」「塗りやすかった」など所感を教えていただくと、その後の治療がスムーズに進みます。忘れないように、お薬手帳に所感を記録しておくのがおすすめです。 |
塗り薬を含む外用剤の剤形には軟膏、クリーム、ゲル、ローション、液、パップ、テープ、パウダー、フォーム、スプレーや泡状スプレーなど幅広いため、具体的に伝えることで、より適した医薬品を出してもらいやすくなると保田先生は付け加えました。
――病院やクリニックにきちんと通い、患者側からお医者さんや薬剤師さんに経過や所感を伝えるのが大切なんですね。最後に、子どもに合う薬を選びたいと考えている保護者にメッセージをお願いいたします。
大事なのは「観察」することです。医薬品を使った結果、症状が良くなったのか悪くなったのか、それを観察して医師や薬剤師に申告するといったサイクルを回していけば、お子さまにとってより良い選択をより早くできるようになるのではないでしょうか。気軽にご相談いただきたいですね。 |
皮膚科学に特化したリーディングカンパニー マルホのこだわり
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及で、処方される医薬品は変化しつつあります。子どものために安心・納得して使える薬を処方してもらいたいと考えている方は、病院やクリニックの先生に相談してみましょう。
ちなみに、皮膚科学に特化した製薬企業であるマルホ株式会社は創業以来、薬の研究・開発や生産、情報提供活動を通して、多くの皮膚疾患に悩む患者さんに応え続けてきました。加えて、患者さんが使いやすい薬を提供するため、さまざまなこだわりを持っています。
医薬品メーカーや医薬品のことを知っておけば、お薬選びを病院やクリニックの先生に相談するときに役立つことでしょう。
マルホの塗り薬は材料の選び方にこだわっています。効果を発揮する有効成分はもちろん、塗り薬を構成する基剤についても最適な品質のものを厳選。製品の安定性や塗りごこちも追求し、検討を重ねて選び抜いています。
材料の仕入れから完成までのすべての工程で品質を確保する工夫をしています。製造にかかわる600以上の工程に社内資格制度が設けられており、それぞれの資格を取得したスタッフが丁寧に作業を行っています。患者さんに万一のことが無いように、ミスが起こらないための体制を築きあげています。
使いやすさにもこだわっています。患者さんの負担を少しでも減らしたいとの思いから、塗りごこちまで社内評価を実施。容器についても、小さな手でも持ちにくくないか?フタをなくしてしまう心配はないか?などマルホの薬を使っている多様な患者さんが使いやすいように何度もブラッシュアップして作っています。
薬を必要としている患者さんをお待たせしてしまうことがないように、製造にかける時間と材料をしっかり確保して、安定的に薬を作り続けています。万が一自然災害などが起きたとしても供給が途絶えないように、製造が多い製品は自社グループで4つの工場を持つなど、何重もの対策をしています。
マルホは創業以来、多くの皮膚疾患に悩む患者さんに応え続けてきました。肌の病気やお悩みに関する情報があふれるなか、どのようにケアをしていくべきか悩む人々に寄り添い、さまざまな形でサポートしています。マルホのこだわりがさらに詳しく解説されたWEBサイトや、皮膚症状に悩む患者さんに向けたサポートサイトもぜひチェックしてみてください。
[PR]提供:マルホ