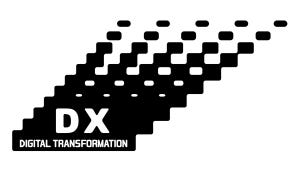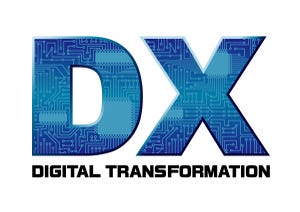テクノロジーが進化し、AIの導入などが現実のものとなった今、「働き方」が様変わりしてきています。終身雇用も崩れ始め、ライフプランに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。本連載では、法務・税務・起業コンサルタントのプロをはじめとする面々が、副業・複業、転職、起業、海外進出などをテーマに、「新時代の働き方」に関する情報をリレー形式で発信していきます。
今回は、業務可視化組織改善ツールを提供するQasee代表取締役CEO村田敦氏が、海外から見た、日本の働き方の異常性ついてお話します。
日本社会の「働き過ぎ問題」は世界的にも有名になっています。
世界一の収録単語数を誇るオックスフォード英語辞典には、2002年の時点で,「Karoushi(過労死)や「Zangyo(残業)という英単語が収録されてしまうほど、世界から見て日本は、「勤勉であると同時に働き過ぎ」だとという風に映っていると言われています。そもそも日本の働き方は、他の国と比べたときにどういった点で変わっているのか、またどういった問題が潜んでいるのか、海外の視点を元に考察してみたいと思います。
日本人=(イコール)長時間労働しているという誤解
毎日、朝早くから夜遅くまで、働きすぎで疲れ果てている日本のサラリーマン像は、すごく想像がしやすいのではないでしょうか。
ですがそんな想像とは裏腹に、意外にも日本は、世界的な統計から見ると長時間労働ではありません。OECD(世界経済協力機構)が毎年発表している年間労働時間によると、日本の労働時間は2012年以降、過去10年減少傾向にあるのです。
また、アメリカの場合、「定時になったらすぐに帰る」という日本の外資系企業のイメージとも重なってそのように思っている方も多いと思うのですが、意外にもアメリカは先進国の中では労働時間が長いと言われ、2017年に行われたOECD(経済協力開発機構)の調査では、アメリカの労働時間は1日7.5時間。日本が1日7.1時間と意外にもアメリカの労働時間のほうが長いという結果になっています。
祝祭日の日数も、日本は他の国と比べても、多いのです。
2019年は、以下の通りでした。
- 英国:8日
- ドイツ:9日
- アメリカ:10日
- フランス:11日
- メキシコ:11日
上記に対し、日本の祝祭日日数は16日と、祝祭日が多い国、それが日本の現状です。
ではなぜ、日本が海外からみて長時間労働のイメージを持たれることが多いのか。 これには幾つか理由があるように思います。
海外から見える日本人の違和感
ひとつは、日本の通勤電車の混雑ぶりです。 「日本に来たら体験すべき」スポットとして注目され、渋谷のスクランブル交差点同様、インスタ映えする名所となっていますが、乗り切れない乗客を駅員が押し込む風景は日本独特のラッシュアワーは、実は多くの外国人から働く日本人の姿は外国人の目に「よく働く日本人」という印象で深く焼きついています。
また、エクスペディアが世界19カ国を対象に実施した有給休暇に関する国際比較調査の結果で、日本の有給休暇の取得率は19カ国中で最下位の50%と、その低さも世界から見ると働きすぎという印象を与えているようです。
日本の現状の課題とは
またその中でも、特に世界から見て、異常なほど「働きすぎ」なのではという印象を与えてしまっているのが、世界共通語にもなってしまった「Karoushi(過労死)」の存在です。ニュースでも度々、月に100時間以上の残業が常態化し、過労死に繋がったというのを目にします。
なぜこのような事が日本では起きてしまうのか。色々と世界と比較すると、日本の評価制度や組織構造の問題なのではと感じます。日本の平均労働時間は、冒頭でもお伝えしたとおり、統計的には低いのです。低いはずなのに、過労死の問題はなくならない。要するに、一部の従業員に業務や作業が集中する組織的欠陥が否めないのです。
これには、日本人の悪しき慣習が関係している気がしてなりません。
調和を大事にし、空気を読む日本の企業文化では、上司より先に仕事を切り上げて帰路につくことに、どこか後ろめたい気持ちが生じたり、キャパ以上の業務を請け負う事が美徳とされたり、評価に直結することもあります。業務が一段落していても、なにをするわけでもなく「オフィスに残る残業」という”不思議な”現象まであります。
定時きっかりにオフィスを出ず、なんとなく周囲の人に合わせて帰宅準備をしたり、真っ先にオフィスを出るのが自分にならないよう様子をうかがったり。接待などで会社を早々に出た上司が、食事の後にオフィスに戻って来るかもしれないといった事態に備えて、上司が家路に着くのを確認するまでは帰宅できない暗黙のプレッシャーもあると聞きます。
また、日本の独特なサラリーマン像として海外で取り上げられるのが、仕事終わりの飲み会です。
「飲みニケーション」と称して仕事が終わってもなお、同僚や上司と飲食をともにする。「コロナ禍でなくなってしまって寂しいこと」のナンバーワンにあげられるのも仕事終わりの飲み会です。日本人にとってはすでに欠かせない大事なルーティーンになっていたりします。
日本のこうした働き方は、終身雇用制度にも下支えされてきました。新卒を一斉に採用し、めったなことでは解雇もないのが一般的です。労働者は雇用主に忠実で、安定した雇用が保持できる。これもまた、調和を重んじる日本の文化、労働環境ならではの産物で、海外から見ると、ものすごい違和感として映り、こうしたことが「Karoushi(過労死)」にも繋がっている可能性もあることを考えると、日本人の意識や行動自体も変えなければいけないのかもしれません。
その他にも、日本では労働生産性が他の先進国に比べ低いという別の問題も存在します。一部の人に作業が集中してしまったり、業務上の非効率が表面化されず、長年に渡って放置されてしまっていたり、また評価制度も上司の主観的な側面が強く残る内容になってしまっていたり。
こうした問題にも、今一度向き合い、どうすれば組織が活性化し、悪しき風習の改善や労働生産性を上げていくことができるのか、広い視点で自社を見つめ直し、現代の様々なテクノロジーを駆使して改善を図っていくことが、今の多くの日本企業にとって必要なことなのかもしれません。