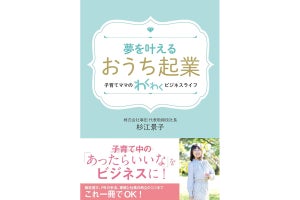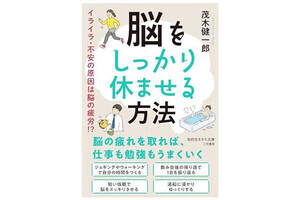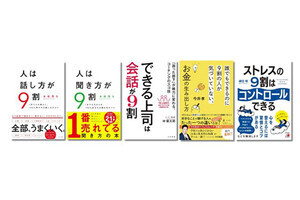日経BPは、このほど『若手はどう言えば動くのか? ~相手を「腹落ち」させたいときの伝え方~』(1,980円/ひきたよしあき著)を発売した。本書は、若手の成長を促し、チームの貴重な戦力になってもらうための「伝え方」を詰め込んだ一冊である。
著者は、大阪芸術大学放送学科客員教授、早稲田大学招聘講師であり、SmileWords代表取締役のひきたよしあき氏。同氏は、コミュニケーションコンサルタントとして上場企業や行政機関などでコミュニケーションスキルの指導を行っているほか、政治、行政、大手企業のスピーチライターとしても活動している。
今回紹介するのは、コミュニケーションの中で登場する曖昧な言葉「大丈夫」について。部下や後輩が言う「大丈夫です」のワード、それはどんな意味を指しているのだろう。この曖昧ワードに潜む危険性についてもみていく。
■「自分で考えて動く若手」をどう育てるか
【case10】
「大丈夫です」と言ってトラブルを隠そうとします
【お悩みへのAnswer】
「大丈夫」はくせ者ワード。曖昧言葉をビジネスから排除せよ
■相手を気遣う「大丈夫」で混乱…どちらの意味?
トラブルはすぐに共有する。これも「当たり前のビジネス習慣」ですが、若手のなかにはハードルが高いと感じる人もいます。
さらに「大丈夫です」という言葉が、本音を分かりにくくしています。
教え子の学生や若い人と食事をしているときのこと。「 デザート、食べる? 」と尋ねると、
「大丈夫です」
とにっこり笑いながら言われます。ここで悩みます。
1. まだおなかに余裕があるから、大丈夫(=食べる)なのか。
2. ここまでの食事で満足しているから、大丈夫(=食べない)なのか。
確認すると、正解は2。「もう結構です」の意味で「大丈夫です」と答えていました。
「いらないです」などと言うと言葉がきつ過ぎて、私が傷つくのでやわらかく表現したといいます。しかし、この気遣いのせいで、意志疎通がすんなりできなくなっています。
だから、若手が「大丈夫です」と言った場合は、細心の注意が必要です。もしかすると相手は、仕事を完成する見込みがあるから「大丈夫」と言っているのではなく、完成できないけれど、きつい言葉を返したくないから「大丈夫」と言っているのかもしれない。
あるいは、仕事によって自分のメンタルが弱っていないかを聞かれたと勘違いして、「はい、(私のメンタルは)大丈夫です」と答えている可能性もあります。まず、「大丈夫」という言葉がくせ者だと認識しましょう。
相手が「大丈夫です」と言ってきたら、にっこり笑って、
「どう大丈夫なの? もう少し詳しく教えて」
と聞き返すことです。「大丈夫」という言葉に疑い深くなりましょう。
■「ビジネスでは曖昧な言葉は避ける」を共通ルールに
「大丈夫」は、人によって使い方にかなりの差があります。若手を育てるときは、「大丈夫」という言葉が曖昧な伝わり方をすることを教えてください。そして「大丈夫」の代わりに、ビジネスでは意思を明確に伝える言い回しを使うよう助言しましょう。
「大丈夫です」のような曖昧な言葉を使わないことをルールにしている企業はたくさんあります。日本を代表するある一流ホテルでは、「なるほど」という言葉を禁止しているとか。
曖昧な上に、上から目線を感じさせる言葉でもあるからです。リーダーと若手はもちろん、人と人との意思疎通を円滑にするには、意味合いや印象に幅のある曖昧な言葉を少なくしていくことが大切です。
■トラブルを隠そうとする人の3通りの心理とは
さて、「大丈夫です」と言ってトラブルを隠そうとする人の言葉には、3通りの心理が隠されています。
1. 怒られるのが怖い!
2. 私がトラブったなんて、認めたくない!
3. きっと自分で解決できる!
同じ「大丈夫です」でも、その人のキャラクターによってトラブルを隠す動機が違います。
1は「ビクビク型」、2は「プライド型」、3は「のんびり型」といったところでしょうか。
しかし、本人の性格以外にも、トラブルを隠す理由は存在します。それは、「ネガティブなことを報告しづらい」職場の風土です。若手がトラブルを素直に開示しやすくするには、上司や先輩が「どんなことでも受け止める」という姿勢を見せて、それを言葉で表すことが大切です。
特に1の「ビクビク型」は、上司など先輩社員の日頃の態度や発言にも問題があります。まずは相手の努力や成長を認める発言から入りましょう。
「4月にここに来た頃よりも、発言がしっかりしてきたよね」
「あれこれ調べたり、あちこちの意見を聞いたりして大変な作業をしているよね」
と、相手の承認欲求を満たしてから、本題の仕事の話に入る。そして、
「私もうっかり見過ごすことがあるから、今度は早めに報告してもらえるとうれしい」
などと、自分を一段、落とした言い方をします。すると、相手の不安を和らげることができます。
■早めに開示することのメリットを提示
2の「プライド型」は、そのプライドを傷つけないような言い方に努めます。
「あなたの仕事をもっと完璧にするために、私が力になれることがあるかもしれないので、今後は相談してほしい」
あくまで主人公は、相手であることを認めながら話します。
3の「のんびり型」については、「トラブルは早めに開示して対応策を取るべき」という法則をきちんと理解し、実行してもらわないといけません。
「トラブルは1人で抱え込まなくていい。みんなで解決したほうが、あなたにとって良い結果につながる」
と、相手にとってのメリットを伝えましょう。
「そこまでやらなければいけないのか? そもそもトラブルを報告するのは義務ではないのか?」と怒りたくなる気持ちも分かります。しかし、若い頃は、トラブルを報告する必要性や、やり方を、中堅社員ほどには知らないのが普通です。丁寧に教える必要があります。
若手がトラブルなどのネガティブな情報を開示しやすくするには、CASE2でお伝えしたように、普段から先輩社員が積極的に「失敗談」を話すことも有効な方法の1つです。「上司や先輩も、昔はこんな失敗をしてきたんだ」と分かると、若手は安心し、心を開きやすくなります。「失敗談の共有」を、社内研修プログラムに取り入れている企業もあるほどです。
「ネガティブなことを報告したら叱責される」「評価が下がる」と思うと、報告をためらいがちになるものです。若手から先輩社員までが、ビジネスに必要な情報を気兼ねなく共有でき、何でも言い合える職場環境をつくることも、成果を出すためのリーダーの大事な仕事なのです。
まとめ:受け入れる姿勢を示して「隠さなくてもいい」環境をつくろう
書籍『若手はどう言えば動くのか? ~相手を「腹落ち」させたいときの伝え方~』(1,980円/ひきたよしあき著)|
本書では、ここで伝えた内容以外にも若手を指導する際の言葉選びや、リーダーとしてのマインドについて紹介している。ぜひ本書を通じて具体的な声のかけ方など実践方法を学んでみてほしい。
イラスト/こつじゆい