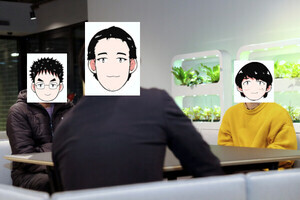毎日髪を洗って清潔に保っているはずなのに、なぜかフケが出てしまうことがあります。そんなとき「一瞬でフケをなくすことができたら!」などと思ってしまう人もいるかもしれません。
フケが出る原因にはいろいろあります。「間違った頭皮ケア」もその一つで、あなたがよかれと思って行っている行為がフケが悪化させる原因となっている恐れもあります。
この記事では、専門医監修のもと、フケの原因やフケを改善する方法を紹介します。原因を見極め、正しいケアでフケ対策をしていきましょう。
フケを一瞬でなくす方法はあるの?
結論からお伝えすると、フケを瞬時になくすことは難しいと言えます。
そもそもフケとは頭皮からはがれ落ちた古い角質片を指します。頭皮のターンオーバーによって出るものである以上、フケ自体が生理現象の一つと言えます。日々の生活を過ごすうえで必ず生じてくるフケを一瞬でなくすというのは難しいですが、フケが出る原因を把握していればその量を減らしていくことは可能かもしれません。
ここからはフケの発生メカニズムなどについて詳しく見ていきましょう。
フケには「乾性フケ」と「脂性フケ」の2種類がある
頭皮は、ほかの皮膚と同じように常に新しく生まれ変わっています。新陳代謝によって古い角質がはがれ落ちていくため、フケが出ることは誰にでも起こるごく当たり前の現象ですが、量が多く目立つ場合には注意が必要です。
フケには大きく分けて2つの種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。まずは自分のフケがどのタイプなのかを知っておきましょう。
「乾性フケ」の特徴
フケには主に2つのタイプがあります。1つめは「乾性フケ」で、白色で細かく乾燥した状態なのが特徴です。頭皮が乾燥することによってターンオーバーのリズムが乱れて、未熟な角質がはがれてしまっている状態です。
黒っぽい服を着ているときに肩に白い粉状のものが目立ったら、それは乾性フケが増えている状態かもしれません。乾性フケは、もともと乾燥肌の人に起こりやすいもの。しかし、普段は乾燥肌ではない人でも、冬場の乾燥した気候が続く時期などには乾性フケが出ることがあります。
健康な頭皮でも、ターンオーバーによって一定量のフケが出ますが、少量のため目立ちません。乾性フケの量が多い場合には、頭皮になんらかのトラブルが発生している可能性が考えられます。
「脂性フケ」の特徴
フケのもう一つのタイプは、「脂性フケ」です。脂性フケはベタベタとしています。髪の根本に湿り気のあるベトついたフケが付いていると感じたら、それは脂性フケが増えているのかもしれません。
脂性フケは、角質に皮脂やホコリなどの汚れが混ざったものです。毛根あたりにベッタリと張り付いていることが多いので、乾性フケのようにサラサラとは落ちにくいのが特徴です。
脂性フケは、ターンオーバーがうまく行われないときに起こります。多すぎる皮脂をエサに雑菌が繁殖して、頭皮を刺激することで悪化します。特に皮脂の分泌が多い脂性肌の人がなりやすい症状です。
フケの原因として考えられるものは?
フケの原因はいくつか考えられますが、最も一般的なのは「頭皮の乾燥」や「誤ったシャンプー方法」によるものです。また、生活習慣の乱れやストレスなどが原因となることも考えられます。
フケが気になる場合には、原因ごとに対応方法が異なりますので、まずはなぜフケが増えたのかを確認していきましょう。
頭皮が乾燥している
フケが増える原因の一つに、頭皮の乾燥があります。皮膚が乾燥すると白く粉を吹いたようになることがありますが、頭皮が乾燥したときも同じような状態になります。
頭皮が乾燥したときに発生するのは、主に乾性フケです。頭皮が乾燥すると、もともと持っているバリア機能が低下します。そうすると、ターンオーバーが乱れてしまい、頭皮の角質が未熟な状態ではがれ落ちて乾性フケになるのです。
頭皮の乾燥は、空気が乾燥しやすい冬や、空調がききすぎて湿度が低い場所に長時間いるときに起こりやすくなります。また、紫外線も頭皮の乾燥の原因となります。
洗髪方法やシャンプー選びが間違っている
正しい洗髪ができていない場合、フケが増えることがあります。フケが多くなるのは頭皮環境悪化のサインです。毎日欠かさずシャンプーしているのに、なぜかフケが改善されないという人は、洗髪方法を見直してみましょう。
洗髪方法が原因でフケが出る場合、まず考えられるのが「洗いすぎ」です。頭皮に必要な皮脂まで取り除いてしまうと、頭皮が乾燥したり、逆に皮脂の過剰分泌が起こったりします。また、十分に洗い流せずにシャンプー剤などが頭皮に残っている場合にも、フケが出ることがあります。
さらに、洗浄力が強すぎるシャンプーなど自分に合っていない製品を使用することで、フケにつながることもあります。
生活習慣が乱れている
ほかの部分の皮膚と同じく、頭皮も生活習慣の乱れによる影響を受けることがあります。特に偏った食生活は、頭皮環境が悪化する原因になります。外食が続いて油分の摂取量が多くなると、頭皮がベタついた経験がある人もいるのではないでしょうか。
日々頻繁に口にする食べ物は体調を大きく左右します。頭皮環境も例外ではありません。スナック菓子やジャンクフードなどの脂肪分の多いメニューを摂取しすぎると、皮脂が過剰分泌されて脂性フケの原因となることがあるでしょう。そのほかにも睡眠不足や喫煙、飲酒なども、頭皮環境の悪化の原因になることが知られています。
ストレスがたまっている
ストレスがフケが出る原因になることもあります。ストレスは、乾性フケと脂性フケの両方の原因になることがあるので、注意が必要です。
ストレスがたまると、交感神経が優位になり、血管が収縮します。頭皮の血管が収縮して血流が悪くなると、頭皮のバリア機能が低下します。栄養不足状態の頭皮は、少しの刺激からも大きなダメージを受けやすくなります。そのため、頭皮環境のバランスが崩れて、フケが増えることがあります。
また、ストレスは免疫機能にも影響を及ぼします。免疫機能が落ちると、頭皮の常在菌のバランスが崩れて新陳代謝が悪くなります。さらに、ターンオーバーが正常に行われなくなることで、皮脂を分解する菌であるマラセチア菌などが増殖しすぎてフケが発生するケースもあります。
フケをなくすためのシャンプー方法は?
フケをなくすには、頭皮と髪の正しい洗い方を知り、実践することが大切です。誤った方法でシャンプーを続けていると、フケがさらに悪化することもあります。
ここでは、医療法人社団五良会 竹内内科小児科医院の五藤良将院長の解説のもと、毎日の正しい洗髪方法を紹介していきます。
ブラッシングする
シャンプーする前には、まず髪が乾いた状態でブラッシングするのがおすすめです。とくに外出した日は、髪にはホコリなどの汚れがたくさん付着していますので、シャンプー前にブラッシングして汚れを落としておきましょう。
慣れないうちはシャンプー前にブラッシングするのを忘れてしまいがちですが、入浴前のルーティーンとして習慣化することで、無理なく行えるようになります。
ぬるま湯で流す
次に、洗髪の工程に入ります。まずは、ぬるま湯で頭皮と毛髪をまんべんなく流します。シャンプー液を使って洗浄する前に、予洗いをするのです。実は、この工程で頭皮の汚れの大部分を落とせます。この際、お湯の温度が高すぎると、必要な皮脂まで流してしまうことになるので、注意しましょう。36℃くらいのぬるま湯を使ってください。
ぬるま湯で流しながら、指の腹で頭皮を優しくマッサージするのがおすすめです。このとき爪を立ててしまうと、頭皮に傷が付いてフケが悪化する原因となるので気をつけましょう。頭皮全体を数分間丁寧にマッサージしたら、予洗いは完了です。
シャンプーを泡立てて優しく洗う
シャンプーは直接髪につけず、適量を手に取ってから、少量のお湯と一緒によく泡立ててから髪にのせます。その泡で頭皮を優しくマッサージするように洗います。フケが出ていると、つい念入りに洗いたくなるものですが、シャンプー時間が長くなると、必要な皮脂まで除去してしまうことになります。長くても3分以内を目安にするとよいでしょう。
外出しなかった日など、頭皮や髪があまり汚れていないと感じる場合には、シャンプー時間は1分程度で問題ありません。
シャンプーする際には、髪の毛を洗うのではなく、指の腹で頭皮をマッサージするように洗います。頭皮を傷めにくいシリコン製のシャンプーブラシなどを活用するのもおすすめです。
すすぎ残しに注意する
頭皮や髪の根本付近の汚れがしっかりと落ちたら、ぬるま湯ですすぎます。シャンプーの成分が頭皮や毛髪に残っていると、頭皮トラブルが起こる可能性があります。頭皮環境が悪化すると、フケの症状がひどくなることも考えられるので、すすぎ残しがないように気をつけましょう。
シャンプー液や泡が残りやすいのは、耳の後ろや後頭部、襟足などです。シャワーする角度を調整しながら、すすぎ残しがないように丁寧に流してください。
しっかり流そうとしてシャワーの水圧を強めにしがちですが、できるだけ優しく流すようにするとよいでしょう。フケが出ているのは、頭皮環境がよくないときです。そのため、頭皮にできるだけ負担をかけないようにケアしましょう。
頭皮を意識してもう一度洗う
一度シャンプーした後の頭皮を確認して、汚れが残っているようならもう一度シャンプーしてください。2回目のシャンプーの量は、1回目の半分程度を目安にします。洗いすぎは頭皮の乾燥を招くので、手早く1分程度にするのがおすすめです。
1回目と同じく手でしっかりとシャンプーを泡立て、指の腹で頭皮をマッサージしながら優しく洗ってください。その後、水圧が弱めのぬるま湯で、すすぎ残しがないように丁寧に洗い流します。
トリートメントをつけて流す
シャンプーを流し終わったら、トリートメントをつけます。事前に、髪の水分はしっかりと切っておきましょう。トリートメントを使用するのは、髪の長さの半分より毛先のみです。頭皮ケアをうたっている製品以外は、頭皮にはつけないように気をつけてください。
頭皮にトリートメントが付くと、しっかり洗い流したつもりでも残りやすく、ベタつきなどで頭皮環境を悪化させる原因となることが考えられます。また、トリートメントが毛穴を詰まらせる可能性もあるので、毛先を中心に、適量を使用することを意識しましょう。
トリートメントを塗り終わったら、浸透させるために5~10分ほど時間を置くのがおすすめです。トリートメントを浸透させている間に、洗顔やボディケアを済ませましょう。その後、ぬるぬるとした感じがしなくなるまでぬるま湯でしっかりと洗い流したら、トリートメントは終了です。
ドライヤーでしっかり乾かす
入浴後は、ドライヤーを使って髪を乾かします。毛髪と頭皮が濡れたままで放置すると、雑菌が繁殖して頭皮環境が悪化することがあります。そのため、できるだけ早めに髪を乾かすとよいでしょう。
ドライヤーを使用する際には、頭皮が乾燥しない程度にするのがポイントです。近距離からドライヤーの熱にさらされると、頭皮がダメージを受ける可能性があります。ドライヤーを頭皮から少し離して、頭皮の負担にならないようにしてください。
乾かしムラが出ないように、角度を変えながらまんべんなく風を送るようにします。ドライヤーを持つ手を持ち替えながら、頭皮と毛髪全体を乾かしましょう。
シャンプーの種類の見直しも検討する
頭皮に負担が少ない方法でシャンプーをしてもフケが改善しない場合には、使用しているシャンプーが自分に合っていないのかもしれません。肌に合わない成分が入ったシャンプーを使うと、髪がきれいにならないどころか、頭皮の環境を悪化させる原因となることがあるのです。
「洗浄力の強すぎるシャンプーは避け、自分の頭皮タイプに合った低刺激な製品を選ぶことも重要です。乾性フケには保湿、脂性フケには抗菌成分を意識すると効果的です。改善が見られない場合は、皮膚科専門医に相談しましょう」(五藤医師)
トラベル用の1回使い切りタイプや、お試し用のミニサイズボトルなどを活用して、自分の頭皮に合うシャンプーを見極めましょう。
フケをなくすためにはどうすればいい?
フケ対策には正しいシャンプーと頭皮ケアが有効ですが、対策をしても効果が感じられないときには、そのほかの方法を試してみましょう。シャンプー以外のフケ対策を紹介しますので、自分にはどの方法が合うのかを確認してみてください。
頭皮を保湿する
フケ症状を改善するには、頭皮の保湿が有効な場合があります。ターンオーバーが正常ではない頭皮にとっては、シャワーやシャンプーが負担になっている場合もあります。そのため、とくに頭皮がデリケートな状態である入浴後には頭皮の保湿を行いましょう。
頭皮の保湿は、専用の保湿剤を使用するのがおすすめです。頭皮と毛髪の水分を拭き取り、指の腹で保湿剤を頭皮に塗り込みます。乳液タイプやジェルタイプで、低刺激の保湿剤を使用してください。
また、エアコンやクーラーがきいた空間に長くいたり、紫外線を浴びたりしても、頭皮が乾燥することがあります。頭皮の乾燥を感じたらこまめに保湿ケアをして、紫外線対策には帽子や日傘を使うとよいでしょう。
生活習慣を見直す
頭皮環境は、日々の食生活、睡眠時間や質などの影響が大きいものです。食事や睡眠が乱れがちになるとフケが増えたり、頭皮がベタついたりすることが多くなります。
食事に関しては、さまざまな栄養素をまんべんなく摂取し、脂肪分や油分、塩、糖は控えめにすることを心がけましょう。また、皮脂の分泌を抑えて良好な頭皮環境の維持を助けるビタミンB2と、頭皮のターンオーバーを整えるビタミンB6を積極的に摂ってください。食事だけで必要な栄養素を摂ることが難しい場合には、サプリメントを活用するといいでしょう。
また、質の高い睡眠も頭皮環境の改善に役立ちます。寝る前にはデジタル機器の使用を控えてスムーズに入眠できるように心がけましょう。早寝早起きする生活に切り替えて健康的に過ごせば、頭皮の状態がよくなったと感じられるはずです。
ストレスを解消する
ストレスを解消することも、頭皮の血流改善によってフケの軽減につながります。ストレスの解消方法は人によって異なりますが、おすすめは軽い運動をすることです。また、1人でリラックスできる時間を確保したり、家族や友人と楽しく過ごす時間を作ったりして、うまく気分転換をしてください。自分に合う方法でストレスを軽減して、頭皮環境の改善に努めましょう。
改善しない場合には医師に相談する
正しい頭皮ケアや生活習慣の見直しをしてもフケが改善しない場合には、医師に相談しましょう。単なるフケと思っていたら、治療が必要な皮膚疾患が背景にあることも。セルフケアでも改善せずフケが続くようなら、皮膚科を受診してください。
フケをなくすための頭皮セルフケアを実践しよう
フケが多くて悩んでいるなら、正しいシャンプー方法をマスターして、頭皮ケアを実践するのがおすすめです。食事や睡眠、運動習慣などを見直して体質を改善することで、フケが軽減できることもあります。
フケを一瞬でなくすのは難しいにしても、対策となる頭皮に優しいセルフケアは、すぐに始められる簡単なことばかりです。さっそく今日から取り入れて、フケの改善を目指しましょう。
「フケは見た目の問題だけでなく、頭皮環境の乱れという身体からのサインでもあります。一瞬で解決できる魔法のような方法はありませんが、毎日の小さなケアの積み重ねが、健やかな頭皮と美しい髪を育みます。まずは、自分のフケのタイプを知り、今日からできることを一つずつ始めてみてください。焦らず丁寧に、自分をいたわる時間を大切にしましょう」
五藤医師の助言も参考にしながら、フケ対策をしてみてください。
この記事は、医療健康情報を含むコンテンツを公開前の段階で専門医がオンライン上で確認する「メディコレWEB」の認証を受けています。