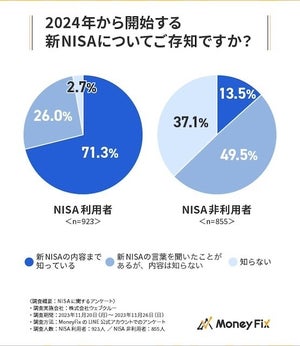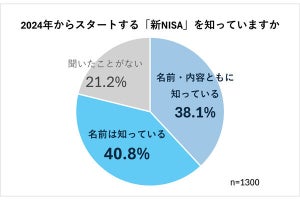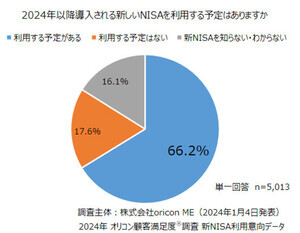2024年になり、新しいNISAがスタートしました。非課税となる期間に期限がなくなり、非課税で投資できる額も大きくなるなど、より使いやすい制度となりました。
一方で、新しいNISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」という2つの枠があります。この仕組みは、利用する際に最も難しく感じる点ではないでしょうか。それぞれ投資できる上限額や投資対象などが少しずつ違います。
2つの枠について、どのような特徴があるかを見ていきましょう。
まず「つみたて投資枠」は、年間の非課税枠360万円のうち120万円まで利用できます。生涯の非課税保有限度額としては1,800万円まで使うことができます。言い換えると、1,800万円全部をつみたて投資枠で埋めることが可能です。
名前のとおり、NISA口座において積立投資を設定することで使うことができる投資枠です。例えば「月に1回、2万円をAファンドに投資する」といった方法です。
また、投資できる商品が指定されているという特徴もあります。こちらについては後述します。
次に「成長投資枠」は、年間の非課税枠360万円のうち240万円まで利用できます。生涯の非課税保有限度額では、1,800万円のうち1,200万円まで利用できます。
投資方法については、一括投資でも積立投資でもかまいません。上場株式や投資信託など、幅広い商品が対象となっています。
図でまとめると下記の通りとなります。
これを見ると、「成長投資枠」のメリットが大きいことが分かります。「つみたて投資枠」には、生涯の非課税保有限度額の上限まで利用できるというメリットがある一方で、投資の方法や対象の柔軟性が低くなっています。
実は「成長投資枠」はリスクを抑えた運用もしやすい
それぞれの枠の投資対象を見てみましょう。まず「つみたて投資枠」ですが、結論を先に言いますと、対象商品は株式に投資する投資信託が主流となっています。投資信託の中でも、リスクが高いとされる商品です。
一方、前述の通り「成長投資枠」は幅広い銘柄に投資をすることができます。大まかな図にすると以下の通りです。
「つみたて投資枠」という名前の印象からは、「成長投資枠」よりもリスクが低いような印象を持たれるかもしれません。ただし、現状では「つみたて投資枠」の対象商品のリスクは意外と高いため、それだけに投資をしてしまうと、人によってはリスクを取り過ぎてしまう可能性があります。
特に、蓄えた資産を使う時期が近づくほど、あるいは運用する資産の額が増えるほど、リスクを取り過ぎて大きな損失を出すことは避けたいものです。
資産運用においてリスクをコントロールするには、値動きが異なる資産を組み合わせて投資をするという方法が基本となります。代表的なものとしては、株式と債券の組み合わせです。株式の比率が高まるほどリスクが高くなり、債券の比率が高まるほどリスクは抑えられることになります。
このような運用をしようとした場合、投資できる対象が幅広い「成長投資枠」を使うことになります。
枠を使い切ることを考えず、自分に合った資産運用を
2つの投資枠について理解を深めたところで、どのように使うのかを考えていきます。
ポイントは「自分がどのくらいのリスクが取れるか」になります。リスクと言うととらえにくいので、「どのくらいの値動きであれば、自分は途中で資産運用を止めることなく続けられるのか」という質問に答えるつもりで考えてみるといいでしょう。
ネットには、自分がどのくらいリスクを取れるのか診断できるサービスもあります。例えば、私がアルゴリズムを作っているロボアドバイザーのウェルスナビであれば、簡単な質問でリスクがどのくらい取れるのかを診断しています。
その結果に沿って、具体的な資産配分を考えていきます。ちなみにウェルスナビの場合、NISA口座で自動積立を設定いただくと、「つみたて投資枠」で米国株のETFを購入し、「成長投資枠」で米国株を含む株式、債券、金、不動産のETFを購入します。そして、資産全体として一人ひとりに合ったリスクのレベルになるように自動で資産配分を調整します。
ご自身で資産配分を考えて購入する場合は手間がかかります。難しければ、必ずしも2つの枠を使わなくてもいいのではないでしょうか。まずは自由度の高い「成長投資枠」で、自身に合ったリスクレベルの商品を購入していきましょう。現状、日本の世帯の金融資産の中央値は600万円台なので、多くの方は「成長投資枠」だけでも賄える計算です。
新しいNISA制度をいかにお得に使うか、などといったことが話題になっていますが、無理に投資枠を使い切ることなどを考えると、本来やるべき資産運用から遠ざかってしまう可能性があります。
資産運用の主役はあくまでも自分です。制度に振り回されることなく、自分に合った資産運用を着実に続けていきましょう。