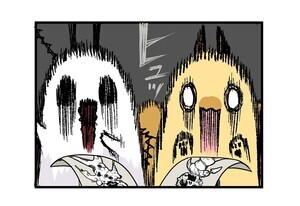普段、スキンケアやメイクアップ製品を手に取ることはあっても、それがどのように開発され、どんな理念や技術に支えられているかを知る機会は、ほとんどない。ましてや、日本国外に暮らす若者たちにとっては、なおさらだろう。
私たちが日常的に使っている化粧品の背後には、成分の研究、安全性の検証、香りや色の設計、肌へのアプローチ、そしてブランドとしての世界観──目には見えない多くの工程と、人の手と思いが積み重ねられている。
そんな「化粧品の向こう側」に、台湾から来日した若い学び手たちが、一歩踏み込んだ。
日常で触れている化粧品。その“向こう側”を見に行く
2025年7月、台湾教育部(Ministry of Education, Taiwan)が推進する国家プログラム「Global Pathfinders Initiative(GPI, 青年百億海外圓夢基金計畫)」の一環として、台湾全土から選抜された高校生20名が来日。
GPIは、台湾の若者に海外での実地体験や学びの機会を提供することで、国際的な視野や進路選択の幅を広げることを目的とした国家プロジェクトである。
今回の訪日では、コーセーの協力のもと、2日間にわたり同社の研究所、美容専門学校、本社、直営店舗を巡る特別プログラムに参加した。
参加者の多くは、美容やスキンケアに関心を持ち、「いつかこの業界で働いてみたい」と語る15〜18歳の高校生たち。化粧品に惹かれるきっかけは人それぞれだが、その向こうにある“人”や“仕組み”にふれる体験は、誰にとっても初めてのことだった。本稿では、このプログラムの様子をレポートする。
1|研究所:化粧品の“効く理由”に、実験と対話でふれる
プログラム初日、台湾の高校生たちが最初に足を運んだのは、東京都北区・王子にあるコーセーの研究所。普段日常的に手に取るスキンケアやメイクアップ製品。その背景には、どんな研究と理念があるのか──そんな問いの答えに出会うプログラムが始まった。
案内役は、現場で日々製品開発に携わるコーセーの研究員たち。まずは講義形式で、成分開発や安全性試験、香りの設計、メイクのシミュレーション技術など、ふだんは見えない領域の工夫が紹介された。
参加した学生の一人はこう振り返る。
「講師の方がとても面白くて、インタラクティブな授業だったので自然と集中して聞くことができました。香りのデザインにまでこだわっているとは知りませんでした。」
さらにこの日は、座学に加えて研究所見学の時間も用意されており、美白成分の効果を検証する実験も行われた。2つのマッシュルームの一方に保湿美容液、もう一方には美白美容液を塗り、その上からシミの原因となるメラニンに変化する成分を添加した。すると、保湿美容液を塗った側はじわじわと黒く変化し、美白美容液を塗った側はそのままの色を保ち続ける。
その様子を目の当たりにした学生たちからは、驚きと納得の声が上がった。
「目で見て違いが分かるから、すごく直感的でした」
「成分がどう働いているのか、頭じゃなくて体で理解できた気がします」
研究所のガイドは製品の説明だけでなく、コーセーが大切にしている理念にも触れた。安全性へのこだわり、美容成分との向き合い方、長年にわたる研究成果の蓄積。学生たちは、目の前の化粧品が“技術と哲学の結晶”であることを肌で感じ取っていた。
「成分分析やメイクシミュレーションの仕組みまで丁寧に説明してくれて、会社全体の開発力を実感しました」
「有名ブランドの“中身”を知る貴重な機会でした。こういう学びが、高校の授業でももっとあるといいのにと思いました」
この1日目の体験で、化粧品がただの“商品”ではなく、感性と科学の融合から生まれる「成果物」であることを知った高校生たち。彼らの目には、コーセーの研究所が、職業としての可能性を秘めた“未来の入り口”として映ったのかもしれない。
2|美容専門学校:職業と教育の「リアル」を知る
研究所で「化粧品がどう作られるか」を学んだ高校生たちは、午後にコーセーが母体の美容専門学校を訪問。ここでは、製品の“つくり手”ではなく、それを“届けるプロ”になるための学びに触れる時間が用意されていた。
案内してくれたのは、現役の教員や在校生たち。まず最初に見学したのは、サロンさながらの実習室「エスポワール」。シャンプー台やメイクブースがずらりと並ぶ空間に、学生たちは思わず感嘆の声を上げた。
「日本の美容学校って、こんなに設備が整っているんだ」
「実際の美容室みたいでびっくりしました」
現場での学びをリアルに再現する環境は、まさに「教育の中に職業がある」ことを実感させるものだった。また、学生たちはその場で専門学生と直接交流する機会にも恵まれた。言葉は違っても、「美容が好き」という共通点は、すぐに距離を縮めてくれる。
ある台湾の高校生は、こう語ってくれた。
「年齢も興味も近いから、話していてすごく楽しかったです。将来の選択肢が具体的にイメージできました」
「普通科の高校に通っている自分でも、美容の専門学校に進めると聞いて安心しました。興味があれば挑戦していいんだと思えた」
教員による授業紹介では、国家資格取得に向けたカリキュラムや、メイク・ヘア・ネイルといった専門分野の指導方針も説明された。ふだんの学校生活では出会えない“職業教育”のあり方に、学生たちは真剣な表情でメモをとっていた。
「製品を知ることと、技術を磨くこと。どちらも美容の世界には必要だと感じました」
「台湾にもこういう学校があればいいのに、と心から思いました」
この訪問は、単なる「学校見学」ではなく、ひとつのキャリアの可能性に正面から触れる時間だった。美に関わる仕事が「夢」ではなく「現実」に変わる瞬間が、確かにあったように感じられた。
3|本社:商品企画を“やってみる”という挑戦
2日目の午前中、学生たちは東京・日本橋にあるコーセーの本社を訪れた。迎えてくれたのは、広報・商品企画・アジア事業部の社員と、メイクアップアーティストとして第一線で働く社員の方々。冒頭は、会社紹介やブランドのポートフォリオ、事業戦略、さらにはコーセーの台湾市場での展開に至るまで、幅広いテーマが専門的かつ分かりやすく語られた。
「プロフェッショナルな内容なのに、私たちにも理解できるように説明してくれて、すごく嬉しかった」
「社内の経営モデルや戦略を学ぶなんて初めて。コーセーがなぜ台湾市場を大切にしているかもよくわかりました」
学生たちはメモを取りながら、コーセーという企業の“全体像”を吸収していく。そして続くのは、コーセー社員との共同ワークショップ。テーマは「台湾の若者に届けたい美容体験を考える」。グループに分かれてアイデアを出し合い、ターゲット、製品の特徴、キャッチコピー、体験ブースの演出までを自由に設計する。
「自分たちのアイデアに対して、現役の社員からアドバイスをもらえるなんて思っていませんでした」
「“それ面白いね”って言われたとき、自信がついたし、商品企画って面白いと思いました」
プレゼンテーションでは、参加者全員が前に立ち、堂々と発表。コーセーの社員たちからも、現場視点の具体的なコメントが寄せられた。インタラクティブなこの時間は、まさに“実践力”を鍛える体験だったように思える。
また、ワークショップ後には、参加した全社員と学生による「質問会」も実施された。これは一方通行の座談会ではなく、“双方向”のコミュニケーションの場。学生からも、企業側からも積極的に質問が飛び交い、その濃密なやりとりこそが、今回のプログラムの核心だった。
たとえば学生からは、
「商品開発の皆さんが、個人的に好きなコーセーのブランドは何ですか?」
「目の下のクマを自然に隠すには、どんなメイク方法が効果的ですか?」
といった、プロとしての知見に触れたいという関心が寄せられた。
一方で企業側からは、
「台湾の若者は、どのようなSNSやメディアを通じて美容情報を得ていますか?」
「日常的によく使っているブランドは?それらのどこに魅力を感じていますか?」
といった、生活者としてのリアルな視点を引き出そうとする問いが投げかけられた。
このプログラムを振り返り、コーセーの担当者は
「一人ひとりの視点に驚かされました。高校生だからこそ持てる感性に、私たちも学ぶことが多かったです」
と語っていた。
そして学生たちもまた、
「自分たちの話を“顧客の声”として丁寧に聞いてくれていると感じた」
「双方向に学び合えるって、こういうことなんだと思いました」
と語っていた。
一つの企業を舞台に、文化や言語、立場を超えた対話が実現したこの時間は、まさにこの越境型プログラムの醍醐味だったと言えるだろう。
4|Maison KOSÉ:ブランドの“届け方”を実地で知る
スタディツアーの締めくくりは、銀座・原宿にあるMaison KOSÉの店舗訪問。ここでは、ブランドが“商品”としてだけでなく、“体験”としてどのように届けられているのか、顧客との接点の最前線に触れる機会となった。
入力した名前に応じてAIが世界に一つだけのメッセージカードを作るサービス、テスターによる香りやテクスチャーの比較──学生たちは、まるで実際の購買者のように店内を巡り、手に取って、感じて、話し合っていた。
特に印象的だったのは、多くの学生がその場で商品を購入していたこと。「かわいい!」「これは台湾の友達にも紹介したい」といった声が自然に飛び交い、商品袋を手にした彼女たちの表情は晴れやかだった。
その様子を見ていたある生徒は、こんな気づきを口にした。
「“可愛い”とか“いい香り”っていう気持ちは直感的なものだけど、それがどうやってデザインされているのか、どんな人に向けて作られているのかまで考えると、ブランドの見え方が全然変わった」
また、店舗スタッフの丁寧な接客や立ち振る舞いを目にしたことで、「コーセーは商品だけでなく、人の育成にも力を入れている会社なんだ」と感銘を受けたという声もあった。
「午後の店舗見学では、コーセーが社員を丁寧に育成されているのだなと感じました」
販売の現場を支える“人”の存在とその専門性。それを感じ取った生徒にとって、ここは単なるショップではなく、「ブランドが完成する最後の場所」だったのかもしれない。
Maison KOSÉという空間は、ブランドの世界観を“触れて、試して、感じる”ことで自然に理解できるよう設計されていた。そしてそれは、若い世代の心に、単なる知識を超えた“好き”の実感を残していた。
おわりに──“ブランドを深く知る”という体験が、未来を動かす
今回のコーセーでの2日間は、単なる職場見学や商品体験にとどまらず、ブランドが持つ理念や技術、そして人の想いに深く触れる貴重な機会となった。
高校生たちは、研究所では化粧品の「効く理由」に触れ、専門学校では職業教育のリアルを知り、本社では自らのアイデアを形にするワークショップに挑戦し、店舗ではブランドが消費者にどう届けられているかを体感した。
2日間のプログラムを通して、社員と参加者の間で活発なやりとりが行われ、企業の考え方やブランドの背景に触れる機会が随所にあったように思われる。
一方で、高校生の率直な質問や感想は、企業にとっても自社の価値を見つめ直す機会になった。
「学び合う時間だったと思います。伝える側も、たくさんの刺激と気づきをもらえました」
(コーセー担当者の言葉より)
「なぜこの商品をつくっているのか」「どんな想いを誰に届けているのか」──そんな問いに向き合う時間は、企業にも学びをもたらす。そして、それを自らの言葉で理解し始めた学生たちは、やがてブランドの未来に新しい風を吹き込んでいくはずだ。
この2日間の体験は、台湾と日本、教育と企業の間に対話と理解を生むきっかけとなった。特に参加した高校生たちにとっては、今後の進路や価値観に影響を与える時間になったはずだ。
構成・文責:岡林 浩輝(マイナビ グローバル経営戦略室)