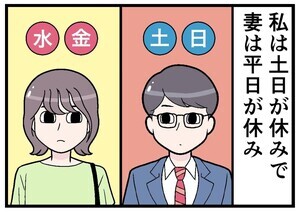少年野球人口の減少が叫ばれながらも、多くの子どもが集まっているチームも少なくありません。今回取材した東京都三鷹市にある『三鷹ジャガーズ』もそんなチームの一つです。決して強豪というわけでもなく、プロ野球ジュニアに選手を輩出しているわけでもないチームに、多くの子どもが集まる理由はどこにあるのでしょうか? 練習が行われている小学校の校庭を訪れてみました。
◆「見守り当番」があっても子どもは集まる
小学校の校庭で楽しそうに練習に励む「三鷹ジャガーズ」(2、3年チーム)の子ども達。現在の部員は18人で、チーム全体では53人。これでも十分大所帯ですが、今年度の1年生はまだ入部受付していないため(取材時点)、部員はもう少し多くなりそうです。
この日、練習に参加した子どもは15人、お父さんコーチの姿は8人。大人1人で子ども2人を見る計算になりますから、なかなかのお父さんコーチ参加率です。
「体験会に来たときにお父さんには『一緒にやりましょうよ』と声はかけていてます。もちろん強制はしていなくて『来れる人はお願いします』というスタンスなのですが、それでも毎回多くのお父さんがお手伝いしてくれています。子どもと一緒に楽しみたいと思ってもらっているようで、子ども同様にお父さんもけっこうハマってくれていますね(笑)」
そう話してくれたのは2、3年チームを預かる三津井淑人監督。
このチームではお母さんの当番、いわゆる「見守り当番」があります。たくさんのお父さんコーチがいるため、大人の目は十分足りているように思いますが、それでも「見守り当番」が必要なのにはこんな理由があるそうです。
「これからのシーズンは熱中症などが危ないですし、もちろん私もお父さんコーチも注意深く見てはいます。それでもお母さんは子どもの体調の変化に敏感で、お父さんが気付かない子どもの変化や、子どもが『大丈夫』と言っても、『いや、ちょっとおかしい』というふうに気付いてくれることも多いんです。ですので毎回1人、見守り当番をお願いしています」

当番制について、この日練習を見に来ていたお母さんはこんな話をしてくれました。
「当番が回ってきても時間が短いですし、子どものことが見られるからいいかなと思っています。逆に当番の制度がないと、いつも同じ人が来てやることになったりしますから、そういうのも嫌ですし、むしろ当番制があった方がこちらもやりやすいと思っています」
毎回1人のはずの見守り当番のお母さんの姿はこの日は4人。その数はその後ポツポツと増えていき、最終的には8人のお母さんが練習を見守っていました。
少年野球人口の減少とセットで語られることの多い「親の負担」問題ですが、少なくともこのチームを見ている限りでは「お父さんコーチ」も「見守り当番」も、一概に「親の負担」とは言えないのではないか、そんなことを思いました。
◆低学年目線に立った練習メニュー
練習が始まり、ウォーミングアップが終わると続いて行われたのは「タグラグビー」と「パルクール」などの全身運動と「ラダー」を使ったトレーニング。これをたっぷりと1時間行っていました。
「最近の子どもは外で遊ばない」と言われることの多い昨今。週末の野球の練習以外は外で遊ばない、運動もしないという子も珍しくありません。それは怪我にも繋がりかねません。そのため「野球の練習をする以前に、色んな運動、体の動かし方などを意識して行わせる必要がある」。そう考えて練習時間の1/3を割いて、こういった練習メニューが取り入れられていました。この辺りの考え方にも、チームに子どもが集まる理由の一端があるのかもしれません。

キャッチボールは、お父さんコーチ1人に対して子ども2人、3人一組になって行われていました。この狙いは子どもが思いっきり投げられることにあるのだと三津井監督は言います。
「上手い子もいればそうでない子もいます。捕るのが上手くない子には思いっきりボールを投げることができませんから」
お父さんコーチが相手ならば的が多くて投げやすいだけでなく、低学年であれば後逸しそうなボールも捕ってくれるので、逸らしたボールを都度捕りに行くこともなくなります。さりげないことではありますが、限られた練習時間を有効に使うための工夫と言えるかもしれません。
キャッチボールの後半では全員がピッチングも行っていました。低学年ですからキャッチボールもずっと続けていれば集中力が切れてしまう子もでてきます。ですがキャッチボールの相手が座って構えてくれると、子どもはストライクを目指して投げようという集中力が出てきます。またチームとしても、低学年から全員がピッチングを行うことで、ピッチャーができる子が多く育つため、特定のピッチャーに負担がかかることを防ぐことにも繋がります。

トスバッティングはJ球ではなくテニスボールが使われていましたが、トスは斜め前からではなく、正面から上げられていました。それをバットを出す角度を確認しながら、いわゆる「バーティカルスイング」で打ち返す子ども達。三津井監督も一人ずつ見て回り、低学年の子でも分かるようにこのスイングの理論、理屈を噛み砕いて教えていました。

練習の最後は紅白戦。子ども達は毎回この紅白戦を楽しみに練習に来ているそうです。紅白戦を見ていて感じたのは、バーティカルスイングの練習をしているだけあって角度の良い打球が外野に結構飛ぶこと。そしてゴロが少ないということ。
「この数ヶ月で外野にバンバン良い打球が飛ぶようになってきました。打球角度が良いですから、これで将来パワーがついていけば楽しみですよね。練習は裏切らないなと個人的には思っています」
野球の入口である低学年チームの方針は「とにかく楽しく、楽しく!」。そして、ただ楽しいだけではなく、この先のこともしっかりと見据えた練習を行う。
こういった指導方針が保護者に支持されて、多くの子ども達が集まっている。そんなことを思った三鷹ジャガーズ2・3年チームの取材でした。(取材・写真:永松欣也)
後編に続きます。