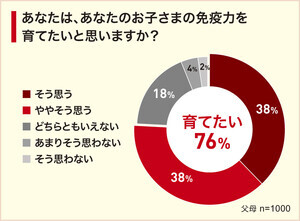発熱した子どもに起こることがある熱性けいれん。元気な我が子が突然意識が不安定になるため、親は動揺してしまうものです。発熱時にけいれんが起こったら、あわてず冷静になることを心がけ、親がするべき対処をしましょう。
■熱性けいれんとは
熱性けいれんは、38℃以上の高熱に伴って子どもが起こすけいれん発作です。髄膜炎や脳炎、てんかんなどほかの原因による発作とは区別され、熱だけが原因で起こるものを指します。
<熱性けいれんの症状>
「けいれん」と聞くと体が震える状態をイメージしますが、そうとは限らず、全身をつっぱらせることもあれば、突然力が抜けて脱力することもあります。白目になる、一点だけを見つめるという場合も。
いずれにしても意識がないか、混濁した状態になります。呼びかけにも応じず、発作中は呼吸も不規則になります。口から泡を出すことや、嘔吐が伴うこともあります。
熱性けいれんは一時的なもので、多くは2~3分以内で止まり、後遺症も残りません。たいてい生後6カ月から5歳ごろまでの間で、発熱から24時間以内に起こります。日本では10~30人に1人が経験するといわれ、珍しいことではありません。
<熱性けいれんの原因>
原因は詳しくはわかっていませんが、熱のために神経系の働きが乱れて起こると考えられています。引き金となる要因として遺伝があり、近親者に熱性けいれんを起こしたことがある人がいる場合に起こる確率が高くなります。
■家庭でやること・やってはいけないこと
まず「やってはいけないこと」を説明します。次のような行動は、けいれんを長引かせることや、窒息につながるおそれがあります。誤った対処をしないためにも、親は何よりもまず冷静になりましょう。
<やってはいけないこと>
・大声で呼びかける
・体を揺さぶる、叩く
・体をおさえつける
・口に手やハンカチなどを入れる
※けいれんで舌を噛むことはないため必要ありません。口に何かを入れると吐いたものを詰まらせる危険があります
以上のことは避けましょう。
<まずやること>
子どもを布団や床など平らで安全な場所に寝かせます。衣服をゆるめて刺激を避け、吐いたものを詰まらせないように体ごと顔を横向きにしましょう。あごをのばしてあげると呼吸が楽になります。
<確認すること>
次に、可能な範囲でけいれんの経過を観察できるといいでしょう。
・けいれんが始まった(気づいた)時間と終わった時間
けいれんの持続時間を知るために記録します。けいれんがどのくらい続いたかによって、その後の対処が変わってきます。
・目の様子
白目をむいているか、黒目が左右どちらかに寄っていないか、一点を見つめているか、確認しておきます。
・手足の様子
つっぱっているか、ガクガク動いているか、だらんとしているか。また手足の動きは左右対称になっているか、非対称か確認しておきます。
・唇や肌の色
いつもどおりか、青白かったり、紫になったりしていないか確認を。
そのほかにもけいれんが起こる前の様子や、発熱がいつからで何度あったかも、受診時に確認があります。
なお、けいれん中の様子を動画撮影しておく保護者の方もいるようです。受診した際に医師から確認される点を覚えておけるといいのですが、子どもがけいれんを起こしている最中、冷静にすべてチェックすることはなかなか難しいものです。動画で記録しておけば、そのまま様子を見せることもできて受診時に役立ちます。
ただ、撮影できるほど冷静でいられない場合もあるでしょう。その場合は、上記の<まずやること>だけでも行いましょう。
■熱性けいれんで、救急車を呼ぶ目安は?
熱性けいれんで救急車を呼ぶ目安は次のような場合です。
・けいれんが5分以上続く
・けいれんが止まっても意識が戻らない、戻りが悪い
・呼吸が不規則、弱い
・一度の発熱で2回以上のけいれんがあった
なお、初めてのけいれんで本当に熱性けいれんかどうかわからない場合は、髄膜炎や脳炎などではないか早急に確認が必要です。初めてのことで保護者も混乱しているときは、救急車を呼んでもいいとされています。自家用車で向かうにしても動揺して安全運転が難しいことも、病院に向かう途中で子どもがけいれんを繰り返すこともあります。必要だと感じたら救急車を呼びましょう。
■熱性けいれん後の対応は?
けいれんが止まると、本人は眠ってしまうことが多いです。初めてけいれんを起こした場合や、2回目以降でも以前と様子が異なるときは、なるべく速やかに受診をしましょう。
けいれんは一旦止まった場合でも、下記の場合はすぐに受診をしてください。
・けいれんの時間が5分以上だった
・左右非対称だった
・けいれんを短時間に繰り返す
・生後6カ月未満
・6歳以上
・手足の一部に麻痺が残る
上記に該当しない場合は、診療時間内に受診するか、病院などに連絡して相談しましょう。
■熱性けいれんを経験した後に注意すること
熱性けいれんの再発率は30%ほどといわれています。処方薬による予防は、けいれんを起こした回数や年齢、持続時間などにより異なります。かかりつけの医師と相談しましょう。
一度でも熱性けいれんを経験すると、次の予防接種まで間隔をあけることになります。保育園での発熱時の対応が変わることも、処方薬に制限が出ることもあります。かかりつけの医師や通っている保育園にも報告して、けいれん後に気をつけることを確認しておきましょう。
熱性けいれんを起こすと心配になりますが、命に関わることはなく、多くは後遺症も残りません。親にできることとして様子をよく観察し、状況に応じて救急車を呼ぶ、救急受診をする、診療時間内に受診するなど、対応していきましょう。
最後に子どもの熱性けいれんの対処法に関して、小児科の専門医に聞いてみました。
熱性けいれんとは、発熱時に発症するけいれん発作のことであり、発達段階にあり脳の感受性が高い生後6カ月から就学前までの乳幼児にしばしば見られる小児救急疾患です。
けいれん中の子どもは意識状態が不安定となり非日常的な姿を示すため、目の当たりにした保護者は不安に襲われます。そのような状況において、けいれんの様子を細かく観察したり動画撮影をしたりすることは困難であることが予想されます。可能な範囲で構わないので、吐物を誤嚥しないように顔を横に向けるなどして気道を確保して頂くこと、けいれんが数分以上続くようならば速やかに病院受診をして頂くことが大切だと思います。
救急車の使用については様々な意見がありますが、救急車には酸素が準備されており、呼吸補助の訓練を受けた救急隊が駆けつけてくれることは大きな強みとなりますので、相談されることも大切だと思います。
けいれんが治った後に、しばらくして意識が戻れば一安心ですが、何らかの違和感や普段と異なる様子を認めた場合は、脳炎や脳症の可能性もあるため、専門的な治療や経過観察が必要となります。