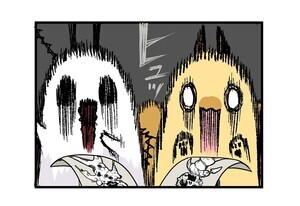ガクラボ学生ライターのさくらです。皆様は英語のスピーチコンテストを見たこと、または出場したことはありますか?
少しハードルが高いかも...と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ今回のレポートを読んでコンテストの雰囲気を感じてみてください!
今回私は、2025年5月17日に開催された「第3回IIBC大学生英語スピーチコンテスト」を取材してきました。
『IIBC大学生英語スピーチコンテスト』とは?
『IIBC大学生英語スピーチコンテスト』は、日本でTOEIC® Programを実施・運営する一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(以下 IIBC)が主催しているコンテストで、今回が3回目の開催となります。
今回は本選に残った学生たちが『現代社会における課題、問題を提起し、私たちがどう取り組むべきかを表現すること』をテーマに、事前に準備をした最大8分間のスピーチを発表。発表後には審査員による8分間の英語での質疑応答も行われ、順位が決定します。
スピーチをただ覚えて披露するだけでなく、英語での質疑応答や意見を求められるなど、自身が提起したテーマに対して深堀りする力や、質問を聞き取って考えを述べる対応力も重要なようです。
コンテストのはじまりと審査員からのメッセージ
コンテストは、IIBC理事長(本コンテストの審査委員長)による開会の言葉から始まりました。続いて、前回の受賞者によるIIBCカップ返還が行われ、コンテストの伝統と誇りが引き継がれました。
その後、審査員の紹介が行われました。 様々な分野の、エキスパートの方々が審査されることを知り、驚きました。
● 徳久 徹さん(元国際協力銀行米州地域外事審議役)
● 中曽根 佐織さん(日本学生協会(JNSA)基金理事、駐日欧州連合(EU)代表部元調査役)
● Dwain Conferさん(アメリカン・スクール・イン・ジャパン教諭)
● 笹山 尚子さん(早稲田大学 文学学術院 准教授)
● Thomas W. Whitsonさん(一般社団法人 日米協会理事)
● 藤沢 裕厚さん(一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 理事長)
続いて、審査基準・ルール説明があり、特にスピーチ後の質疑応答の重要性について強調されました。
このコンテストでは、出場者の持ち時間がフラッシュカードに表示され、カードが捲られるにつれて残り時間の数字が少なくなっていく様子を、目で確認することができます。加えて、一定時間になるとベルでお知らせすることもあり、目と耳で残り時間を把握できるのは面白いなと思いました。
7人のファイナリストのスピーチ
1. Where Are They in the Circuit
宇野 詩織さん(高知工科大学)
宇野さんは、ジェンダーと教育、特に理工系分野における女子学生の少なさに着目。「女性教授が女子学生に偏見を持つ現実」や「幼少期の玩具の選択が将来の進路に影響すること」などを通じて、ジェンダーバイアスが進学の選択肢に及ぼす影響の可能性や、女子学生として感じる学ぶ環境への問題を定義しました。
2. English

丸山 泰熙さん(東京大学)
アクセントに対する偏見(アクセンティズム)について発表した丸山さん。「英語は世界70カ国以上で話されている」ので英語を第二言語として学んでいる人が大多数とし、イギリス英語とアメリカ英語の違い、そして“訛り”に対する日本人の偏見を指摘。アクセントに囚われず、「言っていること」に耳を傾ける姿勢の重要性を説きました。
3. Connecting beyond the language barrier
小倉 栞奈さん(獨協大学)
小倉さんは幼少期にアメリカで英語が分からなかった際に経験した疎外感を踏まえたスピーチを展開。海外から日本へ来た学生たちが学業面で直面する“孤立”の現状に焦点を当て、言語の壁を超えた「非言語コミュニケーション」や「学校での多言語支援」の必要性を提案しました。
4. Should we really have to learn English?
波山 慎子さん(奈良女子大学)
スペイン出身で自身は英語を第二言語として習得し、奈良の大学に通っている波山さんは、英語学習の意義を問い直しました。観光地目線で日本を見た際に「英語は便利だが、母語も大切にすべき」と主張し、観光地での英語需要と住民のストレスのバランスを問題提起。言語は“ドアを開く鍵”でありつつ、文化の保持も不可欠だと訴えました。
5. Share, Don’t Scare. Guide, Don’t Hide

後藤 美海さん(東京大学)
文化の違いと伝え方についてスピーチした後藤さん。SNSで見かけたという、ルールを守っていない外国人を怒鳴りつけている動画に対して、賞賛の声が多かったこと、また「外国人は日本文化を知らない」と決めつけることによって生まれる“負の連鎖”を問題視。「伝え方を変えれば理解は深まる」とし、「叱るより導く姿勢」でのコミュニケーションの大切さを語りました。
6. Living with AI
山口 崇史さん(関西学院大学)
同級生の多くが教室で考えることを放棄し、いかに教授に指摘されずにAIを使って課題をこなすかについて話していたことがとてもショックだったことをきっかけに、AIとの共生について問題提起した山口さん。学ぶために行くことを決めた大学で、学びを放棄することへの危機感を抱いたと強調しました。AIの進化によって日々学習への姿勢が変わりつつある中、「AIは学びの補助であり、代替手段ではない」と念を押しました。学校教育の中でAIをどう正しく使うか、その責任と可能性について提案がなされました。
7. Open the Box of Trauma
廣岡 莉紗さん(立教大学)
廣岡さんに降りかかった過去の辛い経験をもとに「心の傷は“箱を開けて”整理することで乗り越えられる」と語りました。自身を認めてくれ、真摯に話を聞いてくれる適切な人に打ち明けることの大切さ、そして受け入れられてこそ、乗り越えられる経験の力について力強いメッセージが届けられました。トラウマと向き合う力について考えさせられる内容でした。
審査結果発表
審査の結果、次の3名が入賞しました。審査員からは、そもそも母語でない英語で、自身の意見をまとめて主張する機会に挑戦することが素晴らしい旨が伝えられました。「質問を予測して準備すること」、「個人的な経験を一般化して伝えること」、「情報源を明示すること」など、英語という“橋”を通じて、社会課題に向き合い、未来を語った学生たちに実践的なアドバイスが共有され、出場者たちの今後の学習意欲をさらに高めるアドバイスが贈られました。
スピーチの内容が気になる方はぜひ下の動画でチェックしてみてくださいね。
● 第1位:廣岡 莉紗さん(立教大学)
● 第2位:後藤 美海さん(東京大学)
● 第3位:小倉 栞奈さん(獨協大学)
上記3名には、表彰状、トロフィー、ノートパソコン、テンプル大学日本キャンパス主催アカデミックイングリッシュプログラムが贈呈されました。 また、本選出場者全員にTOEIC® Listening & Reading公開テストとTOEIC® Speaking & Writing公開テストの無料受験(各1回)が贈呈されるとのこと。 受賞者たちは、審査員や聴衆からのあたたかい拍手と共に称えられ、コンテストは幕を閉じました。
その他の方のスピーチはこちらからご覧いただけます。
出場学生へのインタビュー
今回出場された学生の皆さんに、その経緯や準備の方法などを聞いてみました。
ー今回、『IIBC大学生英語スピーチコンテスト』に応募したきっかけは?
コンテストのような大会が好きで、先輩が2人出ていることもあり応募しました。 スピーチは人に思いを伝えることが大切で、人に気に入られようとして行うものではなく、スピーチが楽しいから応募しました。
ー本番までに行った準備の方法を教えてください。
テーマや文章をブレストする段階から、先輩にみてもらいながら進めました。 数えきれない回数添削していただいて、OB、OGの方々もいつでも連絡が取れる状態だったので、沢山の人からアドバイスをもらいました。
また、今回インタビューした学生さんの中には、Chat GPTに想定される質問を考えてもらって質疑応答の練習をした方も複数いました。スピーチコンテストにおいてAIとの共生は避けて通れないトピックになっていると感じます。 応募したきっかけは、「ESS(English Speaking Society)に所属しているから」という理由から、「後輩に誘われたから応募してみた」まで様々で、あらゆる人に向けて門戸が開かれているコンテストだと思いました!
取材を終えて…
今回の取材で、母語ではない言語で意見を伝えられる学生さんが心底かっこいいと思いましたし、私もそのようになりたいと英語学習のモチベーションがとても上がりました。 言語習得が世界の扉を開く鍵になるという表現はよくされますが、違う言語で思いを表現することにより、多角的な視点から物事を観察することができ、見える世界が広がるという印象を受けました。 次回のスピーチコンテストは、来年2月に開催される予定とのことですので、IIBCのサイトをチェックしてぜひ皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうか!!
ライター:伊藤さくら(ガクラボメンバー)
編集:ろみ(学窓編集部)