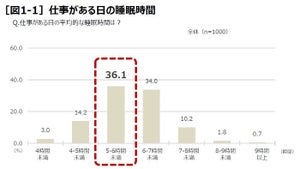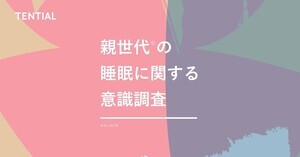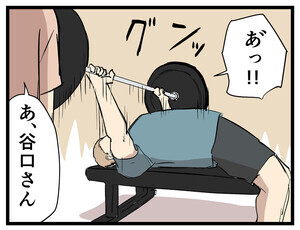新年度になり、生活リズムが変わった方も多いことでしょう。そして迎えたゴールデンウィークでは休みを満喫したはずが、明けてみたら「朝すっきり起きられない……」なんて声も。それ、もしかしたら自律神経の乱れが原因かもしれません。今回は、睡眠と自律神経の関係性について、精神科専門医の大迫鑑顕先生にお伺いしました。
■不眠症の4つのタイプと原因
ーーまずは、不眠症になるとどんな症状が現れるのかをお聞かせください。
大迫先生:はい、不眠症は以下の4つのタイプに分類されます。それぞれ症状や原因が異なります。
<1. 入眠障害>
眠ろうとしてもなかなか寝付けない状態です。布団に入っても30分~1時間以上眠れないことが多く、神経が高ぶっていたり、考え事が頭から離れなかったりします。
<2. 中途覚醒>
夜中に何度も目が覚めてしまい、再び眠るのが難しくなるタイプです。特に高齢者に多いですが、ストレスや不安が原因で起きることもあります。
<3. 早朝覚醒>
希望する起床時間よりかなり早く目が覚めてしまい、それ以降眠れないタイプです。うつ状態が背景にあることもあります。
<4. 熟眠障害>
睡眠時間は確保できていても、「ぐっすり眠った感じがしない」「疲れが取れない」といった感覚が続く状態です。睡眠の質そのものが低下している場合が多いです。
ーー不眠症と言っても、単に眠れないだけではないんですね。これらはどんな人がなりやすいのでしょうか?
大迫先生:不眠は、性格・生活習慣・精神的なストレス・身体的疾患・加齢など、さまざまな要因が重なって引き起こされます。
●神経質・完璧主義な性格の人は、日中のストレスを引きずりやすく、夜に脳がオフになりにくいため入眠障害になりやすいです。
●ストレスを感じやすい人や仕事量が多い人は、交感神経が活発になりやすく、熟眠障害や中途覚醒に陥りがちです。
●高齢者は、加齢により睡眠が浅くなる傾向があり、特に中途覚醒や早朝覚醒が起こりやすくなります。
●うつ病や不安障害を抱える人も、睡眠のリズムが乱れやすく、複数の不眠タイプを併発することがあります。
■自律神経と睡眠の関係
ーーさまざまな原因によって引き起こされる不眠症ですが、「自律神経」と「睡眠」はどのような関係があるのでしょうか?
大迫先生:自律神経には、「交感神経」と「副交感神経」の2種類があり、私たちの体の活動と休息を自動的に調整する役割を持っています。日中は活動を促す神経が働き、夜間はリラックスを促す神経が優位になります。
ところが、ストレスや不規則な生活習慣が続くと、このバランスが崩れ、夜になっても体がリラックスできず、睡眠に支障をきたすことがあります。
つまり、自律神経のバランスが保たれているかどうかが、睡眠の質に直結するのです。
ーー自律神経のバランスが崩れると、不眠以外にも症状が出ることはあるのでしょうか?
大迫先生:自律神経は体温・血圧・消化・代謝・ホルモン分泌などを調整する役割を司っているため、そのバランスが乱れると全身にさまざまな不調が現れます。代表的なものには以下のような症状があります。
●めまい、立ちくらみ
●動悸、息切れ
●消化不良、便秘や下痢
●頭痛、肩こり
●冷えやのぼせ
●疲れやすさ、倦怠感
●イライラ、不安感、気分の落ち込み
これらの症状が不眠と同時に見られる場合、自律神経の乱れを疑うことが大切です。
■自律神経に悪影響を及ぼす行動とは?
ーー先ほど、生活習慣が自律神経に悪影響を及ぼすとお聞きしましたが、具体的にはどんなものが要因となるのでしょうか?
大迫先生:以下のようなことが自律神経に大きな負担を与える可能性があります。
●過度なストレス
●不規則な生活習慣
●睡眠不足
●運動不足
●栄養バランスの乱れ
●過度な飲酒、カフェインの過剰摂取
●スマートフォンやパソコンの長時間使用(特に就寝前)
これらが重なると、交感神経が慢性的に優位になり、副交感神経がうまく働きにくくなるのです。
ーーなるほど…思い当たることばかりです。特に寝る前の過ごし方は要注意なのでしょうか。
大迫先生:就寝前の習慣は、睡眠の質に大きく影響します。
●電子機器の使用:スマートフォンやタブレットの画面から発せられる光は、脳を刺激し、眠気を妨げることがあります。
●飲酒:アルコールは一時的に眠気を誘うことがありますが、睡眠の質を低下させる可能性があります。
●遅い時間の食事やカフェイン摂取:これらは体を活性化させ、入眠を難しくすることがあります。
■5月は自律神経が乱れやすい? 受診の目安
ーー自律神経は生活習慣が大きく影響を及ぼすことがよく理解できました。例えば今の時期、5月ごろに自律神経の乱れを生じるケースなどはあるのでしょうか?
大迫先生:5月は特に自律神経が乱れやすい時期です。その背景には以下のような点が挙げられます。
●新年度の環境変化(入学・転勤・異動など)によるストレス
●気温や気圧の変動が激しい季節の変わり目
●ゴールデンウィークによる生活リズムの乱れ
●連休で一時的に副交感神経が優位になったあと、急に通常モードへ戻る反動
このように、心身両面での負担が集中しやすいため、5月は「不眠シーズン」とも呼ばれるのです。
ーー不眠や自律神経の乱れに関して、セルフケアではなく受診が必要となる目安があれば教えてください。
大迫先生:以下のようなケースでは、医療機関への受診を検討してください。
●不眠が2週間以上続いている
●日中の生活や仕事に支障をきたしている
●気分の落ち込みや不安感が強くなってきている
●体調不良が慢性的に続いている(頭痛・めまい・消化不良など)
●セルフケアを続けても改善が見られない
特に、精神的な不調や体の異常を伴う場合には、早めの受診が望ましいです。放置することでさらに症状が悪化し、慢性化するリスクもあります。
■良質な睡眠をとるための“整え方”
ーー不眠を解消するための「自律神経の整え方」について、日常から心がけて実践できることがあれば、詳しく教えてください。
大迫先生:以下は、自律神経のバランスを整え、睡眠の質を高めるために日常で意識すべきポイントです。
(1)朝起きたら太陽の光を浴びる
体内時計をリセットし、夜に自然な眠気を誘うメラトニンの分泌を促します。
(2)就寝の90分前に入浴
40℃前後の湯船にゆっくり浸かることで、副交感神経が優位になり、寝付きが良くなります。
(3)夕食は就寝の2~3時間前までに済ませる
消化活動が活発なままだと、眠りが浅くなってしまいます。
(4)寝る前のスマートフォンなどは控える
少なくとも就寝30分前からは画面を見ないようにしましょう。
(5)軽いストレッチや深呼吸を行う
体と脳に「もう休んでいいよ」というサインを送ることができます。
■5月の体と心に「立ち止まる時間」を
大迫先生:不眠の背景には、目に見える疲れだけでなく、心の緊張や生活の乱れ、日常に潜む刺激など、さまざまな要因が複雑に絡んでいます。
特に5月は、一息ついたタイミングで不調が表に出やすく、「気づき」が起こりやすい時期でもあります。
眠れない日が続いたり、「なんだか調子が出ないな」と感じたりしたときは、自分に小さな問いかけをしてみてください。「最近、自分の心と体をちゃんとケアできていただろうか?」
必要なら、専門家の力を借りることも選択肢の一つです。
あなたの不調は、あなたのせいではありません。5月は“整える”ためのスタート地点として、自分に優しい時間を作ってみてはいかがでしょうか。
この記事は、医療健康情報を含むコンテンツを公開前の段階で専門医がオンライン上で確認する「メディコレWEB」の認証を受けています。