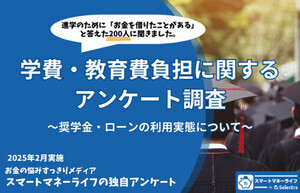明治安田総合研究所は3月28日、痛税感に関する調査レポート「日本人の『痛税感』を紐解く鍵は9割中流意識? ~政府の信頼を高めるために必要なこととは~」を公開した。
財務省によれば、2024年度の国民負担率(国民所得に占める租税負担・社会保障負担の割合)は45.8%。物価高の影響も相まって税・社会保険料に対する負担感、いわゆる「痛税感」は強まっており、Google Trendsにおける税・社会保険料に関するワードの人気度(最も検索があったタイミングを100として相対化したもの。以下「関心度」と呼ぶ)を示したものを見てみると、「負担」「社会保険料」「税」といったワードがコロナ禍以降上昇している。
「社会保険料」の関心度は2005年以降、概ね横ばいで推移していたが、2020年から少しずつ上昇しはじめ、2024年11月には100に。次期年金制度改正の内容が昨年の秋以降に明るみになるにつれ、関心がより高まったとみられる。「税」に関しては、2025年3月時点で80となっており、所得税の課税最低限を引き上げる103万円の壁の議論が影響しているよう。さらに「減税」は、昨年6月の定額減税の際に100を付けた時ほどの関心はないが、リーマンショック時を上回っており、税負担の軽減を求める声が根強く残っている様子がうかがえた。
国民負担率を国際比較すると、日本における租税負担率は29.4%と欧州主要国よりも低い水準にある。にもかかわらず、日本人の痛税感が強いのは、政府への信頼が低いことが挙げられ、給付とのバランスを考えたときに負担ばかり押し付けられているとの意識が、とりわけ現役世代を中心に強いよう。
しかしながら、年齢階級別に所得格差を測る指標であるジニ係数(0に近いほど所得格差が小さく、1に近いほど大きい)を見ると、税・社会保険料を差し引く前の当初所得における格差は、50代以下と75歳以上で20年前より広がっている。一方、当初所得から税・社会保険料を控除し、社会保障給付を加えた再分配所得では、20代前半と50代後半を除いた多くの年齢階級で格差が縮小している。
内閣府が2024年に実施した「国民生活に関する世論調査」によれば、世間一般から見たときに自身の家庭の生活の程度が「中の上」と回答した人は14.2%、「中の中」が46.7%、「中の下」が28.1%と、約9割を占めており、現役世代を中心に当初所得の格差が拡大している一方で、中流意識が保たれているのは、社会保障の所得再分配効果による面もあると考えられる。にもかかわらず痛税感が強いのは、低所得者にのみ社会保障の恩恵が行き渡っており、自らはその対象ではないとの意識が働いていると推測される。
国民の痛税感を和らげ、財源調達力を高めるには、国民に納得感を持って負担してもらう必要がある。上述のとおり、9割もの人が中流意識を保てているのは、所得再分配効果による面があり、また、高齢世代に対する給付が多いことが現役世代の不満につながっているとみられるが、機能別に社会保障給付費を見ると、足元では年金や介護などの「高齢」への給付割合は低下に向かっている一方で、子ども・子育て支援などの「家族」の割合が上昇している。これは、高齢世代への給付と現役世代への給付のバランス改善を図る必要があるとの課題認識のもと、政府が子ども・子育て支援を進めてきた結果でもあり、こども未来戦略における総額3.6兆円規模の加速化プランを策定し、こうした方向性は今後も継続していく見通しである。
問題はこうした政策の意図が国民にほとんど伝わっていない点にある。そもそも日本では税の使い道が見えづらい。欧州の研究機関Tax Expenditures Labが公表する「世界租税支出透明性指数」を見ても、日本は105ヵ国中73位、G7では最下位であり、今後は情報公開や政策評価を通じて支出の透明性を高めるとともに、政府が将来必要となる公的サービスや社会保障給付のビジョンを先に示すことも重要である。そうしたビジョンに対する理解促進への努力を怠っているうちは財源調達に対する国民の納得感を得ることは難しいだろう。