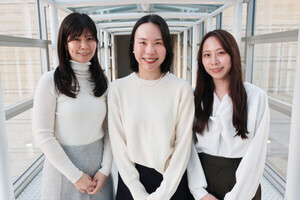2022年に締結された東京ガスネットワーク、東京電力パワーグリッド、NTT東日本グループによるインフラ3社による連携協定。インフラ事業における持続安定化や地域価値向上を実現しイノベーションを起こそうという目的のもと社会基盤を支える3社で共にできることを見つけていくという取り組みは日本中の注目と期待を集めた。この連携協定を促進すべく、地域間で何ができるのかを考える試みを始めたのが、先の3社の神奈川県に拠点を置く支社達だ。いわゆる地域版3社連携ともいえるこの試みが何を生み出したのか、取材してきたので紹介しよう。
3回目となる神奈川県インフラ3社連携の下地作り
2025年2月10日、NTT東日本 神奈川事業部に、東京ガスネットワーク、東京電力パワーグリッド、そしてNTT東日本およびNTTMEの各支店のメンバーが集結。インフラ3社の連携によって何ができるのか、その方法を模索する「インフラ事業者間(電気・ガス・通信)の社員交流会」がおこなわれた。これは冒頭でも触れたように、先に取り交わされたインフラ3社の本社間の締結を受け、連携を加速する上の試みとして全国からも注目されている「神奈川版」としての取り組みとなる。
3社連携で取り組む目的はこちら。今回の取り組みを通じて、神奈川地域のレジリエンス向上を図り、地域からの信頼を更に高めていく布石となるものだ。
各社から5~6名ずつ30代前後の次世代リーダー候補生が選出され、渉外・設計・維持管理の3班に分かれてディスカッションし、新たな業務効率化やより良いサービスへのヒントなどを模索することが目的となる。
当日、ディスカッション開始前にNTT東日本の光回線の仕組みについて、同事業部内にある展示施設・光HOUSEによる見学会も用意されるなど、各社の知見を増やすアクティビティもあり、参加者たちの協力意識を高めていた。
模擬設備や実際の端末機器を用いて、光回線がNTT東日本の基地局から個人宅・集合住宅・ビルなどにつながる仕組みを解説。最新の10Gbps環境によるデモンストレーションも実施された。
見学会では東京ガスネットワーク、東京電力パワーグリッドの社員らが、説明員に質問をする場面も多く見受けられた。光回線によるインターネットサービスは多くの人に利用されている社会インフラの一つであり、興味は尽きないといったところだ。NTT東日本およびNTTMEの社員にとっても、ユーザーの声を聴く良い機会となり、さっそく交流会の良い効果が現れた形となった。
3班に分かれてのディスカッション
続いては本日のメインとなる、3社代表が3班に分かれて「3社で連携できること」、「交流会で習得した知見を自部署の業務にどのように活かしていくか」の2点をテーマに議論がはじまった。
ディスカッションの時間は2時間。ある程度の意見の集約は見られることが期待できるが、議論を進めてみないことにはわからない。だが、これまで2回のディスカッションを経験していることもあり、当日はどの班も落ち着いたスタートだった。
議論が進み、残り時間が1時間を切ってくると、ディスカッションは熱を帯び始める。データを大画面ディスプレイに投影して語り合う姿や、意見交換をする場面が多くなり、いよいよ話をまとめる段階へきていることがこちらにも伝わってくるほどだった。
「時間が来ましたので、順番に発表してください」と司会者からアナウンスが入り、ディスカッションは終了。小休止を挟んで各班が出した答えを発表することになった。
各社の次世代リーダー達が導き出した答えは?
■A班
―連携によって何ができるのか?
橋梁など各社に共通するインフラ設備点検の効率化、コストダウンを目指せないか施策を検討した。
―交流会で習得した知見を自部署の業務にどのように活かしていくか?
3回の討議をしていく中で、各社の業務内容について意見を交換する機会が非常に多く、とても有用な議論だったので、今回だけでなく業務改善を考えていく際には他2社からもヒアリングする機会を持つようにすれば、課題解決も早まり、業務効率化につながる意見が得やすいのではないかという提案がなされた。
■B班
―連携によって何ができるのか?
各社が実施している埋設物調査や工事立ち合いについても更なる連携により、各社の効率化や事前準備の制度向上による顧客満足度の向上が期待できるとした。
―交流会で習得した知見を自部署の業務にどのように活かしていくか?
今回の取り組みを経て得ることができたパイプについては今後も活かしていく。例えば、3社に共通するのは、工事関係書類の作成が細かく、煩雑化している現状があった。今回の協議の中で、デジタル化に成功している社があると、その方法を教えてもらうことで実際に稼働時間の削減に成功した例もあった。今後も意見交換を続けていき、お互いの業務効率化につながりそうな情報があれば共有していきたい。
■C班
―連携によって何ができるのか?
「人材育成」という点に注目し、議論の結果、各社がおこなっている研修において、親和性のある内容であれば協働できる部分が多いのではないかという結論を得た。
―交流会で習得した知見を自部署の業務にどのように活かしていくか?
交流会を重ねてきた経験により、各社がどこに強みがあり、自社に何が足りないかを理解した。それぞれに対して知見があるところが相談窓口を持つことで、お互いを補い合えるのではないかという可能性を見出した。
第3回交流会の議論結果が報告され、それぞれに質疑応答も繰り広げられた。発表内容の詳細について、具体的な方法や課題感についてほかの班からも次々と質問が飛び交う白熱した内容だ。参加者全員が、この取り組みに対していかに期待が大きいのか理解できる時間だった。
各社のトップはどのようにとらえたのか?
1日のスケジュールを終え、報告会も完了したのち、それぞれの企業のトップが総評を述べた。どのような受け止めをしたのか、その内容をダイジェストで紹介しておきたい。
「今日まで本当に様々なアイデアを聞かせていただきました。共通するもの、各チームのカラーにあったもの、どれも素晴らしいものだったと思います。普段違うを仕事しているメンバーたちが、お互いの業務を理解し、知見を深め、そのうえでしっかり話し合うのは大変だったと思います。まだまだ、課題はあると思いますが、明日からできることもあるはずです。今ここにいる皆様が情報連携の窓口になっていただき、できることから始めてください。私たちとしても、一緒になって検討を続け、実現への道を考えていきたいと思います」(相原氏)
「本社でも3社連携は進めていますが、今回みなさまが提案してくれた内容は、まさに現場ならではの視点であり、こういう意見をボトムアップしていくことも本社サイドに気づきを与えるという意味ではとても大事だと思いました。自分たちのアイデアが最終的に地域社会やお客様にもつながっていることを意識していけば3社連携はもっと良くなるはずです。自分たちの弱い部分を補い合うのが3社連携の良さだと思いますので、人の力を借りながら、高いサービス意識を持ってこれからも活動を続けていただければと思います」(坂上氏)
「スタートした当初は地域インフラ事業者が集まれば何かできるはず、という漠然と期待から始まりましたが、本日のような具体性のあるアイデアがどんどん出てくると、やっぱりやって良かったと感じました。特にICT活用に関してはそれぞれの企業が積極的に取り入れています。それらは各社の部分最適化に収まってしましたが、3社連携によってインフラ業界の全体最適化へと広げていく。最終的にお客様や地域のためのサービス向上につなげていければなと考えます。これからは若いみなさんの時代なので、引き続き頑張っていただきたいと思います」(中上氏)
先輩や上司はどう見た?
すべてのスケジュールが終了した後、今回の取り組みを参加者以上に緊張した面持ちで見守り続けていた、先輩、上長のみなさんにも感想を伺ってみた。
「初回のときは遠慮も見えましたが、3回目の今回はかなり楽しめている様子も見えました。事前に連絡を取り合うなど、準備をする余裕もあったようなので成長を感じますね。彼らはちょうど30代という働き盛りということもあって、自分の業務や会社のルールに集中しすぎる傾向もありますが、他社さんの文化に触れることで良い学びを得ているようで安心しました」(作本氏)
「以前はどうしても社内の人間としか付き合いがほとんどないといったところもあり、今回のポジションは不安だったところもありましたが、やってみると私たちでは出ないようなアイデアが生まれるような成長も見せてくれました。社会インフラを支える仲間としても、共存共栄できるようにお互いに助け合っていけるよう、これからも視野を広げていって欲しいですね」(飯野氏)
「回を重ねるごとにみんなの表情が明るくなってきたのを感じました。自分たちが将来会社を引っ張っていくことを期待されているということを理解してくれたのだと思います。3社に共通する部分では、30代の彼らの上の世代が極端に少ないということがいえると思います。ですから、若い彼らが率先して社会インフラを支えていけるよう、今回の取り組みで学んだことや、人脈を活用してどんどん成長していって欲しいですね」(大西氏)
「同じインフラ企業ということもあり、共通の課題を見つけて、前向きな議論につながってくれたのを見て今回の取り組みは良い機会だったのだと思いました。今回集まったメンバーは各企業の中でも職場のコアとなる人材だと思います。自分の会社のことだけでなく、社会インフラ全体をとらえながら、それぞれのポジションでしっかり力を発揮できる人間になって欲しいと願っています」(平出氏)
「まさに私の部下がグループメンバーとして参加していますが、回を重ねる度に自主的に集まって議論したという話も聞いたりして非常に頼もしいなと思いました。社会インフラを支えているのは私たちだけでなく、例えば水道など自治体様も同じような悩みを持っているかもしれません。同じ世代の人材で議論ができるような取り組みに広げてくれるのも地域を支えるという意味でよいなと思っています」(米田氏)
参加者、関係者すべての人が真剣に3社連携による将来を託した取り組みはこれで一区切りを迎えた。当日のディスカッションや報告会の内容を見れば、3社連携が現実になったとき、地域社会がより良い方向へと向かうことは明らかだろう。なお、神奈川県によるこの3社連携は違う形になって継続されるという話もある。社会基盤を支える3社による新たなサービスが届く日はそう遠い話ではないはずだ。