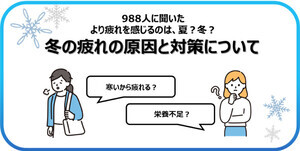Morghtは2月21日、「添い寝と睡眠の質」に関する実態調査の結果を発表した。調査は2025年1月16日~1月18日、全国の子育て世帯およびパートナーと同居している20~60代の男女計1,100人を対象にインターネットで行われた。
子育て世帯の約7割が添い寝派
今回の調査では、子育て世帯の69.2%が子どもとの添い寝を実践しており、さらにそのうち68.8%が毎日添い寝をしていることが判明した。これは、欧米の10%以下という数値と比較して極めて高い割合となっている。また、パートナーとの添い寝についても主に7割の家庭が実践しているデータがあるという。多くの家庭に一般的な添い寝は日本の生活習慣の1つといえる。
添い寝による睡眠の質の低下「添い寝シンドローム」
調査によると、毎日添い寝をしている大人の84.0%が睡眠の質に課題を感じていると回答しており、これは添い寝をしていない人(64.1%)と比べて約1.3倍高い数値となる。
また、子どもの睡眠についても同様の傾向が見られる。毎日添い寝をしている家庭では58.3%の保護者が子どもの睡眠の質に課題を感じており、これは添い寝をしていない家庭の子ども(22.7%)と比べて約2.6倍高い数値となっている。
日本睡眠協会理事長の内村直尚氏によると、添い寝を妨げる要因としては、互いの寝返りによる振動やスペースの狭さ、いびきなどの騒音など、様々挙げられるという。実際その1つである「添い寝による振動」に着目すると、実に全体の75.0%の人が「添い寝による振動が睡眠の妨げになったことがある」と回答している。
この調査結果から、添い寝が親子双方の睡眠の質に大きく影響を及ぼしていること、また4人のうち3人が「振動が睡眠の妨げになっている」ことを自覚していることがわかる。添い寝による睡眠の質の低下は、1つの社会問題「添い寝シンドローム」といえる。
また、「添い寝による睡眠の質への悪影響」については、子育て世帯全体の47.1%が「知らない」と回答。「添い寝シンドローム」を課題として認識できている家庭は半数程度にとどまることがわかった。
「添い寝は心理的にポジティブな影響を与えている」9割超
しかし、内村氏は「添い寝には心理的に安心する、幸福感を得られるという側面もあり、それが良質な睡眠につながることもある」と述べている。
今回の調査では添い寝をしている親の95.1%という圧倒的多数が「添い寝は心理的にポジティブな影響を与えている」と回答し、添い寝が持つ心理的価値を実感していることがわかる。添い寝を行う理由としては「安心するため」を筆頭に、「近くにいないと子どもが寝ないため」「寝具を分けるスペースがないため」「日々のコミュニケーションのため」と多岐にわたり、自分自身の要望や物理的な要因、相手の要望など様々な理由により添い寝をしていることが明らかになった。
この結果からは、添い寝が単なる睡眠の形態ではなく、心理的なニーズを満たす重要な役割を果たしていることが伺える。したがって、添い寝には、安心感が得られるなどのポジティブな要素もある一方で、睡眠の質を低下させる傾向があることが分かり、この矛盾を埋めることが求められているといえる。
「添い寝シンドローム」対策は?
内村氏は「添い寝シンドローム」という課題を軽減するために、部屋やベッドを分ける以外の方法としては「振動を抑えるマットレス」を選択することが大事だと述べている。
しかし、マットレスユーザーのうち10人に4人を超える45.9%は自分の使用しているマットレスの種類を把握していないという結果となり、「マットレス選び」についての意識の低さが明らかになった。
さらに、今回の調査対象者が使用しているマットレスの素材に着目すると、「睡眠に課題を感じていない」と答えた割合に差が見られる結果となった。ウレタン、ファイバー、ボンネルコイルのマットレスユーザーのうち「睡眠に課題を感じていない」と答えたのはそれぞれ4.3%、2.9%、4.4%だったのに対し、ポケットコイルのマットレスユーザーは14.3%と、他素材のマットレスと比べ約10ポイント高い結果となった。