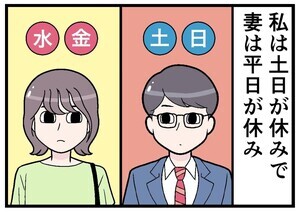横浜市旭区で活動する軟式少年野球チーム「レッドスネークコルツ」。スポーツメディカルコンプライアンス協会主催の『Best Coaching Award』ではベストコーチングアワードの殿堂入りを果たすなど、コーチングと子どもの怪我・故障防止に積極的に取り組んでいるチームです。そんなチームのグラウンドを7年ぶりに訪れてみました。
【ドリルに落とし込んで技術を身につける】
練習が行われていたのは道路脇にあるフットサル二面ほどのスペース。全部員は28名、この日は低学年チームが試合のためにいなかったとはいえ、それでも手狭に思える決して広くないグラウンドでした。そういった環境であるからこそ練習はグループに分かれて行われ、「ボール集めはみんなで1分でやろう!」と監督が声がけをして子ども達に時間を意識させるなど、時間とスペースを効率的かつ有効に使った練習が行われていました。
体の真横に投げる、ゼロポジションから投げるなど7つのドリルが取り入れられたキャッチボールが終わると、次に行われたのは内野と外野に別れて行われたノック。外野のグループは大谷翔平選手が使っていたことで一部の野球指導者のなかで話題にもなっていた『レッドロケット』を使ったフライキャッチが行われ、内野のグループではサプルバット(ストレッチにも使われる細長い棒)を両手に抱えた状態で正面のゴロを捕球するドリルが行われていました。これはグローブだけでボールを捕りに行かないように顔とグローブの距離を保つためのドリルで、捕球の際は当然バットを落とすことになるのですが、これが早すぎても遅すぎてもダメ。そうやってゴロを捕球する体勢に入るタイミングも養うことができるというもの。これは中学軟式野球強豪チームで監督をしていたお父さんコーチが発案したドリルなのだそうです。
内外野のグループに分かれて行われていたノックは、その後グループが入れ替わり、内野のグループが外野のフライキャッチを行い、外野のグループが内野のゴロ捕りを行っていました。この入れ替わりは「ポジションを固定せずに全員に全ポジションを守れるようになって欲しい」(河原哲大監督)という狙いがあるから。色んなポジションを守れることによって子ども達も試合に出られる機会が増え、色んなポジションを経験したことが中学、高校で役立つ機会もあるかもしれません。こんなところが「ベストコーチングアワード」殿堂入りを果たしている理由の一つなのかもしれません。
【こだわりのフロントトスバッティング】
このチームの練習で一番特徴的だったのはトスバッティングです。トスバッティングというと打者の斜め前方からトスされたボールをネット中央に向かって打つ光景がお馴染みですが、ここではバッターの前、ピッチャー方向からネットに隠れたお父さんがトス(フロントトス)するボールをネットの上部に向かって打っていました。斜め前方からトスされたボールを打たないのは「リストターンをさせたくない」という考えがあるからだと河原監督は言います。
斜め前から飛んでくるボールをネットの中央を狙って強く叩こうとすれば、どうしてもインパクトで手首を返してヘッドを走らせようとしてしまいます。これが「リストターン」ですが、その癖がついてしまうとスイングの軌道が水平ではなく波を打つ形となるので当然打ち損じが増えてしまいます。また、斜め前からトスされるボールは打てるポイントが1点しかないわけですから、当然ヒットが打てる可能性も低くなってしまいます。実際、アメリカでトスバッティングと言えばフロントトスが一般的です。
フロントトスされたボールもただ打つだけではなく、スイングにも次のようなドリルがありました。
①体を開いて上半身を使って打つ
②足をスクエアにしてノーステップで打つ(下半身、股関節を使って打つ)
③上記①②を意識して普通に打つ
そのスイングの軌道も他の多くの少年野球チームとはかなり異なっており、バットを水平ではなく縦に出して振り上げる、いわゆる「縦ぶり」の軌道を意識して打っていました。「このスイングは4、5年前から指導していましたが、当時は上手く子ども達に教えることができませんでした」。そんな河原監督が教えを請うたのは、プロ野球選手もお忍びで指導を仰ぐ、日本人初の3A野手でもある根鈴雄次氏。根鈴氏がバッティング指導を行う『根鈴道場』で縦ぶりの理論を自ら学び、それを子ども達に分かるようにチームに落とし込んで指導をしています。
縦ぶりを取り入れたからホームランが増えたという単純な話でありませんが、「ゴロが明らかに減りましたし簡単に三振しなくなりました」と河原監督はその効果を話します。
このチームには「全員に年間100打席打たせる」という決まり事があるように、全力で勝利を目指しながらも指導陣は子ども達の成長、将来にも目を向けた指導が行われていました。アメリカ式指導の良さを積極的に取れ入れながらも、礼儀や挨拶、マナーなど日本の少年野球文化も大事する。グラウンドを訪れてみて「ベースボール」と「野球」のハイブリッドチーム。そんな印象を受けました。そんなチームから巣立っていった子ども達のこれからに注目してみたいと思います。(取材・写真:永松欣也)