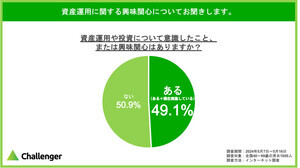投資の中でも初心者向けと言われる「投資信託」。新NISA制度の開始も影響し、最近では多くの人が投資信託を活用した資産形成にチャレンジしようと考えています。しかし、投資信託を始めようと思っても、「どんな準備が必要? 」「口座を開設したら、どうやって買えばいいの? 」などわからないことが多いかもしれません。
そこで今回は、投資信託を始める際の準備や買い方、初心者が注意すべき点について解説します。口座を開設した後、スムーズに運用を始められるよう、しっかりと流れを確認しておきましょう。
■投資信託とは? メリットとデメリットは
投資信託とは、投資家から集めたお金を1つの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などの金融商品に投資・運用するものです。投資信託を買う前に、投資信託の特徴やメリット、デメリットを確認してみましょう。
<投資信託の特徴>
投資信託には多種多様な商品があり、さまざまな切り口で区分されます。投資する資産や地域の違いでは、「国内株式型」「国内債券型」「海外株式型」「海外債券型」や、複数の資産にバランスよく投資する「バランス型」の商品があります。投資家はそれらの商品から好きなものを選んで購入するだけでよく、実際の運用はプロに任せることができます。
<投資信託のメリット>
投資信託のメリットは、購入するだけで「分散投資」ができる点です。通常、投資信託は1本で数十から数百種類の銘柄に投資していますので、一部の銘柄が値下がりしても他の銘柄の値上がりでカバーできる可能性があります。
さらに、少額から投資できるのも魅力です。投資信託は、金融機関によっては100円や1,000円から購入できるため、投資に不安がある人でも始めやすいでしょう。
<投資信託のデメリット>
投資信託のデメリットは、手数料がかかる点です。手数料には、購入時にかかる「購入時手数料」、保有している間にかかる「信託報酬(運用管理費用)」、解約時にかかる「信託財産留保額」の3つがあります。ただし、最近は購入時手数料がかからない投資信託「ノーロードファンド」も増えてきているので、ぜひ活用してみましょう。
もう1つのデメリットは、投資信託には元本保証がない点です。預貯金など元本保証のある商品と違い、値動きによる損失リスクがあることを覚えておきましょう。
■投資信託を買う前に考えておきたいこと
投資信託の運用を始めるには、まず証券口座を開設する必要がありますが、その前に考慮すべき点がいくつかあります。投資信託の購入前に検討したい点は、以下の5つです。
1.どの金融機関で運用するか
まずは、どの金融機関で投資信託を運用するのか決めましょう。投資信託は、証券会社だけでなく銀行や信用金庫・信用組合、郵便局、農協など多くの金融機関で購入可能です。
また、金融機関の窓口のほか、ネット証券で買うという選択肢もあります。店舗窓口では、個別の担当者がついて推奨する銘柄を教えてくれたり、運用に関するアドバイスをしてくれたりします。一方、ネット証券は、パソコンやスマートフォンなどからいつでも自由に購入できますし、手数料が安いというメリットもあります。
初心者の場合、店舗窓口で直接アドバイスを受けながら購入することが安心かもしれませんが、ご自身に合った方法を選択しましょう。
2.「特定口座」か「一般口座」か
また、運用する口座の種類も把握し、決めておくといいでしょう。口座の種類には「特定口座」と「一般口座」があり、「特定口座」はさらに”源泉徴収あり”と”源泉徴収なし”に分かれます。特定口座(源泉徴収あり)は、金融機関が運用益にかかる税金を計算し、天引きしてくれるため、自分で確定申告を行う必要はありません。
一方、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座は、原則として確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)で口座を開設すれば、確定申告の手間が省けるため、初心者の方にはおすすめです。
3.どのような運用方針にするか
次に、どのような運用方針で投資信託を運用するのか決めましょう。値上がり益を積極的に求めるなら株式の割合が大きい投資信託、長期で安定した運用がしたいなら債券の割合が大きい投資信託を選ぶのがポイントです。
ただし、投資においては、リスクとリターンは表裏一体の関係にあります。リスクが高い商品は大きなリターンが期待できる一方、大きな損失を出す可能性もあることを理解しておきましょう。
4.「一括投資」か「積立投資」か
このほか、投資信託の「購入手法」も考えておきましょう。投資信託の購入手法には、「一括投資」と「積立投資」の2つがあります。一括投資は、まとまった金額を一度に投資する方法です。一方、積立投資は、「毎月〇〇円」といった一定の金額を定期的なタイミングで積み立てていく方法です。
どちらの購入手法がいいのか迷うかもしれませんが、積立投資は毎月自動で買付が行われるため手間がかかりませんし、購入のタイミングを分散させることで、リスクの軽減が期待できます。また、まとまった資金がなくても投資が始められるメリットもあります。
特に初心者の場合は、積立投資での運用をおすすめします。
5.「分配金受取」か「分配金再投資」か
投資信託によっては、決算ごとに収益の一部を「収益分配金(分配金)」として投資家に支払うものがあります。収益分配金のある投資信託を購入する場合、分配金をそのまま受け取る「分配金受取」という方法か、分配金を受け取らず再投資する「分配金再投資」という方法のどちらかを選べます。
分配金を受け取る場合、定期的に指定口座への入金が期待できるため、趣味に使ったり、他の金融商品への投資に充てたりして活用する人もいます。その反面、利益が利益を生む「複利効果」が薄まり、長期的な運用を考えた時の投資効率は下がる可能性があります。
■投資信託の購入とその後の流れ
購入前の検討事項について考えたら、自分が選んだ金融機関で証券口座を開設しましょう。証券口座を開設すると、同時に投資信託口座も開設され、投資信託が購入できます。
ここでは、一般的なネット証券を例にして購入とその後の流れを解説します。口座開設後は、以下の流れで投資信託を購入し、分配金を受け取ったり好きな時に解約したりすることができます。
1.口座への入金
まず、銀行振込やインターネットバンキングを利用し、証券口座に投資信託の購入資金を入金します。証券口座から投資信託口座への振替は、原則として不要です。
2.選んだ銘柄の購入
次に、ネット証券のオンライントレード上で自分の選んだ銘柄を検索し、「買付方法」も選択します。投資信託の買付には、「金額買付」「口数買付」「積立買付」の3種類があります。
金額買付は購入する金額を自分で指定する方法で、投資信託によって「100円以上1円単位」のように購入単位が決められています。口数買付は「何口購入するか」を決めて買う方法、積立買付は1ヶ月に一度、自動的に買付を行う方法です。
なお、購入する際は「投資信託説明書(目論見書)」にも目を通し、投資信託の目的や特色、投資リスク、留意点、運用実績、手数料(購入時手数料、信託報酬、信託財産留保額)などの詳細を確認しましょう。
3.分配金の受け取り
投資信託を購入し、決算日を迎えると、投資信託によっては分配金が支払われます。また、投資信託の販売会社から、運用実績を記した「運用報告書」が交付されます。運用報告書には、運用実績のほか、今後の運用方針、費用、資産、負債等などの情報が記載されていますので、目を通しておきましょう。
4.解約(換金)
投資信託は、基本的にいつでも解約(換金)して現金を手元に戻すことができます。全額でも一部でも、資金計画に合わせて柔軟に解約することが可能です。
なお、詳しい購入の流れは各金融機関で異なりますので、口座を開設した金融機関のホームページ等で確認しましょう。
■投資信託の運用で初心者が注意したい点
最後に、投資信託の運用を行ううえで、初心者が特に意識すべき点をご紹介します。
<投資は余裕資金で行う>
投資信託に限らず、投資は余裕資金で行うのが基本です。投資は不確実なものですので、資産が増えることもあれば減ることもあります。そのため、生活費や将来使う予定のお金を投資に回すと、必要な支払いができず困ってしまう場合があります。投資には元本保証がないことを踏まえ、必ず余裕資金で行いましょう。
また、貯金ができない家計状況での投資もおすすめしません。まずは家計を見直し、毎月一定額を貯金できるようになってから投資を始めましょう。
<自分の「リスク許容度」について考える>
また、自分の「リスク許容度」を見極めることも大切です。リスク許容度とは、「どの程度の損失まで受け入れられるか」という度合いのことで、年齢、収入、資産の額、家族構成、投資の知識や経験、性格などによって異なります。
リスク許容度はあくまで主観的なものであるため、正確に測定することは難しいですが、一般的には、運用期間を長く持てる若い人や収入の多い人、資産を多く持つ人などはリスク許容度が高いとされています。
自分のリスク許容度を超えた運用をすると、値下がり局面において、生活に支障をきたすほどの損失を出してしまったり、過度に不安な状態が続いたりすることもあります。投資を始める際には、自分のリスク許容度を考え、それに適した資産配分や商品選びを意識しましょう。
<「長期・積立・分散投資」を心がける>
リスクを抑えて安定的なリターンを目指すには、投資の基本である「長期・積立・分散投資」が大切です。長期投資に明確な定義はありませんが、投資期間は長ければ長いほどお金を増やしやすいと言われているため、10年以上を目安にするといいでしょう。
積立投資は、少額から自動で買付ができ、購入のタイミングを分散することで比較的リスクを抑えやすいというメリットがあります。
分散投資には、積立投資で可能になる「時間の分散」に加えて、「資産の分散」や「地域の分散」もあります。たとえば、国内の株式だけに投資すると利益や損失にはばらつきが生じますが、株式と債券、国内と海外など投資対象を分散させることで、利益や損失の平準化が期待できます。
投資信託はもともと1つの商品の中で多くの銘柄に分散投資していますが、そのうえで、投資対象の異なる投資信託を複数組み合わせて持ったり、「バランス型」の商品を活用したりすると、より分散投資のメリットが享受できるでしょう。
■まずは口座を開く金融機関や口座の種類、運用方針などを検討してみよう
投資信託を始めたいと思っても、実際に運用を始めるには考慮すべき点が多くあります。そこで、口座開設の前に方向性を決めておくと、スムーズに運用を始められるでしょう。まずは、口座を開く金融機関や口座の種類、運用方針などを検討し、自分がどのような運用を目指すのか考えてみましょう。