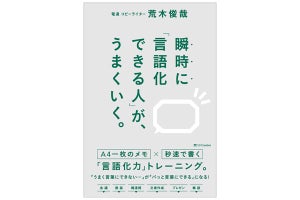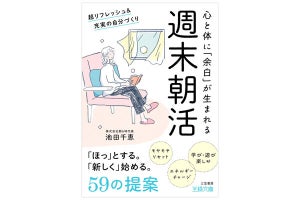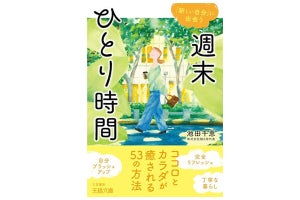自分はいったい何が好きなんだろう。それを見つけられたら、自分を漫画の主人公にできる。
本の要約サービス・フライヤーが展開する「Dig Talk」は、本をひとつのきっかけとして、その人の人生の奥底を「深掘る(ディグる)」動画コンテンツです。
今回は、HKT48の元メンバーで、「モテクリエイター」としてKOSの起業やライバー事務所・321の立ち上げを行ない、タレント、モデル、SNSアドバイザー、インフルエンサーとしても活躍中のゆうこすさんの深みに迫った番組のハイライトを紹介します。
等身大の自分をセルフプロデュースして、いろんな方向から「モテ」を追求するゆうこすさんは、InstagramやYouTubeなどでも多くのフォロワーに影響力を持っています。そんなゆうこすさんの原点はどこにあったのでしょうか? 前後編動画の見どころを4つ、紹介します!
■ポップなメッセージを伝える
いまのゆうこすさんを「つくりあげた」本、1冊目は、イラストレーターなどでマルチに活躍するみうらじゅんさんの『「ない仕事」の作り方』です。アイドルグループを辞めた直後、自分のやりたいことと自分にしかできないこと、そしてビジネスとのつながりにギャップを感じ、不安に思っていたときに読んだそうです。「自分はモテクリエイターでいいんだ!」と背中を押してくれた、まさにゆうこすさんの「人生を変えた」一冊。
「マイナスのものを名前を付けて面白がってみると、自分の気持ちすら変わってプラスになる」というような一節には特に影響を受けたとのこと。いまはKOSの社長としての立場もあるし、失敗して「やばい」と感じる状況に陥っても、自分が落ち込んでいたら社員もファンも不安にさせてしまう。だから、自分はみんなにとってのタレント的存在になって、「ゆうこすさんがいるからがんばれる、勇気をもらえる」と言ってもらえるオーラを出していきたい。そうした気持ちをゆうこすさんは、トップが率先して「ポップに考える」というように表現しています。それが、社員のやりがいや、ファンの生きがいにつながっていったら素敵ですよね。
■自分の「好き」の見つけ方
ゆうこすさんは、この「ポップさ」の考え方をモテの感覚にも応用していきます。その結果、「モテクリエイター」としての自分を見つけることができました。
就活生たちはみんな、深い自己分析を求められます。その過程で、自分をどう掘り下げていけばいいのか迷子になってしまう人も続出します。「自分にしかできないこと」「自分がやるべきこと」がわかれば、仕事も楽しんでいけるはずですが、簡単には見つけられません。
ゆうこすさんは、「自分の得意なことは、意外と無知のなかにある」と語ります。友だちと話しているときに、「あ、自分はこれが好きだったんだ」と気づくこともある。その瞬間に、どうしてそれが好きと感じたのか、メモしてみる。その延長線上で、自分のやりたいことが見えてくるのです。
次は、それをどういう人に、どんなふうに届けていったらいいのかを考える。そこにも、ゆうこすさんの「マジック」があります。これを身近な人にも当てはめていったら、「愛する」ことの考え方も変わっていったそうです。
■思いを届けたい人の心を「1秒でつかむ」ために
YouTubeやInstagramなどで自分から発信していくようになると、ただ自分の言いたいことを並べるだけではファンの心をつかめない、ということも見えてきます。ファンファースト、視聴者ファーストになって、徹底的に自分の脳をゼロにして、効果的に伝えていく。 その方法について真剣に考えさせられたのが、映像プロデューサーの高橋弘樹さんが書いた『1秒でつかむ』でした。自分を知らない人でも、ひと目見て映像に入り込める。そうした「初見さん」も、ずっとファンでいてくれている人も、どっちも楽しめるものを提供したい。
そのためには、取材相手の前に、まずは「取材者自身を取材すること」が大事だ、というメッセージをゆうこすさんはこの本から受け取ります。つまり、自分のことを「めちゃくちゃ知って」いれば、強みも弱みもポップに、届けたい人に届けられるようになる。
それが端的に見えたのは、2つのファンイベントを企画したときでした。片方は男女問わず誰でも来られるイベント、もう一方は春に上京してくる18歳の女の子限定のイベント。応募者数が多かったのは、後者の「限定されたほう」だったのです。その理由にはとても納得させられました。
■自分が語られるストーリーを思い描く
届けたい相手に向かって、自分のなかの「なぜ」「どうして」を深掘っていく。そうして自分のモチベーションを見届ける。それが「愛される要因」につながっていきます。これは、『1秒でつかむ』のなかでは「東野圭吾力」という名前で紹介されています。
東野圭吾さんの小説に出てくる犯人にはしっかりとした動機があり、それを含めて犯人でさえ愛せるキャラになっている、ということです。逆に言えば、動機がないと「愛せないし応援できない」。だからこそゆうこすさんは、何をするにしても自分のなかの「動機集め」をしっかりやるのです。
それは自分の内だけには留まりません。ゆうこすさんが何かを発信するときは、それを見た人が友人やクラスメイト、会社の人たちなどに、ゆうこすさんのことをどう伝えるかまで考えるそうです。自分のことを自分以外の人がどう伝えるか、それ自体がストーリーになるのです。
ゆうこすさんが「#ゆうこす現象」というハッシュタグ運動によって何をしようとしたのか、そこに、「誰かの人生というストーリーのなかに自分を入れてもらう」「漫画の主人公みたいな自分になる」ためのヒントが隠されています。
いかがでしたか? これらの内容を、ゆうこすさんの声と表情付きで受け取れば、より強い納得感を得られるはずです。ご興味のある方はぜひ、本編動画をお楽しみいただけますと幸いです。