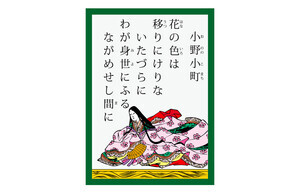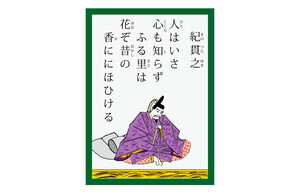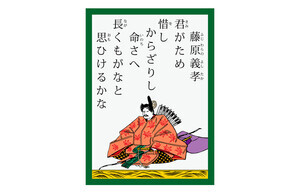「秋の田のかりほのいおのとまをあらみ…」は、小倉百人一首の1番目として選出されている有名な和歌。大化の改新でも有名な天智天皇(中大兄皇子)が作者といわれています。
本記事では「秋の田のかりほのいおのとまをあらみ…」の歌について、現代語訳と詳しい意味や理解のポイント、読み方を紹介。決まり字や出典の『後撰和歌集』、作者の天智天皇に、元ネタとされる歌についても解説します。
百人一首1番「秋の田のかりほのいおのとまをあらみ…」とは
この歌の全文は以下です。
秋の田の かりほの庵の 苫を粗み わが衣手は 露にぬれつつ
早速、この歌について細かく解説していきます。
ひらがな(読み方)
あきのたの かりほのいほ(お)の とまをあらみ わがころもでは つゆにぬれつつ
「庵」をひらがなにするとき、歴史的仮名遣いでは「ほ」と表記しますが、現代では「お」となります。
現代語訳・意味
秋の田の刈った稲穂の番をするのに使う仮設小屋は、屋根の苫(草)の編み目が粗いので、
そこに泊まる私の衣の袖は、夜露に濡れ続けているよ。
解説・理解のポイント
この歌は作者とされる天智天皇の実体験ではなく、貧しい農民の生活を思って詠まれた歌といわれています。
それを念頭に、もう少し細かく分解して見ていきましょう。
かりほの庵
「かりほ」とは「仮庵(かりほ)」、つまり仮設の粗末な小屋と、「刈穂(かりほ)」、刈り取った稲の穂とを掛けています。苫をあらみ
「苫(とま)」とは草を編んで、小屋の屋根などに使用する覆いのこと。「あらみ」は「粗いので」という意味です。「み」は理由を表す接尾語で、多くは「○○を××み」という形で用い、「○○が××なので」ということを表します。衣手
服の「袖」のことです。同じく小倉百人一首の15番の歌、「君がため 春の野に出でて 若菜摘む わが衣手に 雪は降りつつ(光孝天皇)」も有名ですね。ぬれつつ
「つつ」は、「ずっと~し続けて」という継続の意味などを持つ接続助詞です。「ぬれつつ」で「濡れ続けている」ということを表します。
貧しさゆえのわびしさ、孤独さを表現していますが、同時に秋の夜の静けさや透明感も感じられる歌です。また「つつ」で余韻を残すことで、奥深さや風情があります。
決まり字
決まり字は「あきの」で、三字決まりです。
百人一首の一覧 - ひらがなや作者、かるたのルールや決まり字も解説
出典は『後撰和歌集』
この歌は元々、『後撰和歌集(ごせんわかしゅう、略して後撰集とも言う)』の秋の中、302に収録されていた歌です。
『後撰和歌集』は平安時代中期に、村上天皇の命により編さんされました。『古今和歌集』に次ぐ、第二の勅撰(ちょくせん)和歌集です。
分類は春(上中下)、夏、秋(上中下)、冬、恋(一~六)、雑(一~四)、離別・羇旅(きりょ)、慶賀・哀傷となっています。
『古今和歌集』に比べて、公的な歌よりも私的な贈答歌が多く、歌物語的な傾向が見られるといわれています。
作者とされる天智天皇(中大兄皇子)とは何をした人?
天智天皇(てんじてんのう/てんちてんのう)は第38代天皇であり、生没年は626年~671年と、飛鳥時代の偉人です。
まだ中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)の名だったときに、藤原鎌足(ふじわらのかまたり)と共に蘇我氏を滅ぼした乙巳の変(いっしのへん)、そして大化の改新を行ったことで有名です。これにより、中央集権国家の礎を築きました。
また飛鳥(現奈良県明日香町)から近江の大津宮(現滋賀県大津市)に遷都し、即位後には日本で最初の成文法である近江令や、戸籍にあたる庚午年籍(こうごねんじゃく)を作りました。
実は「秋の田の…」の元の歌は、作者未詳だった
「秋の田の かりほの庵の 苫を粗み わが衣手は 露にぬれつつ」の歌は、優れた偉人・天智天皇の歌として広まっています。
しかし実は『万葉集』には、この歌の原型となったとされる、よみ人しらずの歌があります。それは「秋田刈る 仮庵を作り わが居れば 衣手寒く 露ぞ置きにける」というもの。
これが変化し、『後撰和歌集』で天智天皇の作として定着したとされています。そして小倉百人一首では、歴代天皇の祖として尊敬される天智天皇の歌が冒頭に置かれたといわれているのです。
登場人物の気持ちをイメージして、和歌を作ったり理解したりしてみよう
和歌は、五・七・五・七・七という短い文字数の中に、自分の体験から得た情報や、感じた思いを込めることができます。
さらに実際に体験していなくても、天智天皇が農民の暮らしを思って「秋の田のかりほのいおのとまをあらみ…」を詠んだとされるように、想像力を働かせることで、これほどまでに生き生きとした歌を作ることができます。
あなたも自分の経験や誰かに対して感じたことを、和歌にしてみてはいかがでしょうか。
また競技かるたやテスト対策として、百人一首の暗記に挑戦してみようとしている方もいるかもしれません。その場合はただ字だけを覚えようとしても難しいので、一つ一つの言葉の意味を理解して、自分なりにどう思うか考えてみると、覚えやすいかもしれませんね。