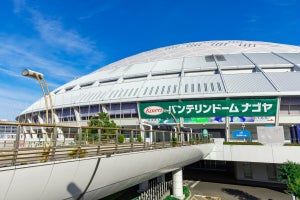あれから35年が経っても、元号が2度変わっても忘れられないプロ野球名勝負がある。1988(昭和63年)10月19日・川崎球場、近鉄バファローズvs.ロッテオリオンズのダブルヘッダー。それは熱く、切ない試合だった。
残り2試合を勝ち切れば近鉄が優勝。だが1つでも負けるか引き分ければ、すでに全日程を終えている西武ライオンズのリーグ4連覇。シーズン終盤「13日間に15試合」という苛烈日程の末、川崎に辿り着いた猛牛戦士たちが、最後の力を振り絞り闘いに挑む─。
■引き分けも許されぬ第1試合
1988年、世間は騒がしかった。
携帯電話などない時代、バブル真っ只中。ソウル五輪が開催された年で、リクルート事件等が大きな話題となる。そして9月19日に昭和天皇が吐血され容体悪化。以降、テレビ・新聞のニュースは、この一色に染まった。
セ・リーグでは、10月7日に星野仙一率いる中日ドラゴンズが6年ぶりVを決めており、その12日後に「パ・リーグの一番長い日」は訪れた。
空は青い。15時、第1試合プレイボール。
いきなり重い雰囲気が立ち込める。
1回表、中3日で先発マウンドに立った小野和義がロッテの3番ファースト・愛甲猛からホームランを浴び、いきなり2点のリードを許した。
「うちにも意地がある」
試合前に有藤通世監督はそう話していたが、すでに最下位が決まっているロッテも本気モードだった。先発は二桁勝利を挙げていたサイドハンドの小川博。来季を見据えた若手主体起用ではなく、外国人選手のマドロックも残すベストのスタメンで試合に挑んでいた。
ロッテがリードしたまま試合は進む。そして1-3で迎えた8回表、ようやく近鉄打線が火を噴く。1死一、二塁の場面で代打・村上隆行が小川から左中間にタイムリー二塁打を放った。二者が生還し3-3の同点。
そして運命の9回を迎える。
近鉄にとっては絶体絶命のピンチ。当時のパ・リーグ規定でダブルヘッダーの場合、第1試合は延長戦に入らない。よって、この回に点が入らなかった時点で優勝はなくなってしまう。
最終回、5番レフトの淡口憲治のツーベースヒットで近鉄は1死二塁のチャンスを摑んだ。ここでロッテはピッチャーを小川から、抑えのエース牛島和彦に代える。その直後、6番センターの鈴木貴久がライト前にボールを弾き返した。
「よし、逆転だ!」
スタンドがドッと沸いたが、当たりが良すぎた。ライトを守っていた岡部明一から矢のようなバックホーム。代走として二塁にいた佐藤純一が三本間で挟まれタッチアウトになってしまう。
「あ~」
球場全体からタメ息が漏れる。
「ここまでか…」
三塁ベース近くで立ち上がれず、茫然としている佐藤の姿をベンチから見ながら近鉄監督の仰木彬も一度は、そう思った。
■忘れ難き梨田の執念の一打
ランナーは二塁にいるが、ツーアウト。あと1つのアウトでここまで辛うじて繋いできた優勝への望みが絶たれてしまう。この大切な場面で仰木はピンチヒッターを送り出す。
「代打、梨田!」
このシーズン限りで引退するベテランの一振り、「こんにゃく打法」の執念に賭けたのだ。
マウンドに立つ牛島はベンチに目を向ける。一塁が空いている。梨田を敬遠すべきかどうか、ベンチの指示を仰ごうとした。
「任せる」
ロッテベンチは、そう返した。
次の打者は、代走からショートの守りに入っている安達俊也。打率1割5分の選手だから歩かせるのが得策。だが牛島は、これが梨田にとって最後の打席になるかもしれないことを知っていた。
(ならば勝負だ!)
そう決めて牛島が投じた初球はインコースのシュート。これを梨田が打つ。つまった打球に「打ち取った」と牛島は思ったが、ボールはセンター森田芳彦の前にポトリと落ちる。二塁ランナー鈴木は迷わず本塁突入。キャッチャーのタッチをすり抜け、ホームベースへ右手を伸ばしながら転がり込んだ。
「セーフ!」
主審の橘修が両腕を真横に広げて、そうコールした直後、いつしか満員になっていたスタンドは大熱狂。起き上がった鈴木は、ベンチから飛び出してきていた中西太コーチと抱き合う。そのままグラウンドに転がり土まみれになり喜び合っていた。
十数年後に私は当時の想いを梨田、牛島両者に尋ねた。
梨田は言った。
「あの場面、ここは俺しかないと思ってバットを持ってベンチを出ていた。なのに仰木監督が、なかなかコールしてくれなくてね。その時間を凄く長く感じたことをよく憶えている(笑)。
歩かされるなんてことは、まったく頭になかったですよ。悔いは残せない、ストライクが来たら何でも打つ!そう決めていた」
対して牛島は、こう振り返る。
「勝負しての結果だから悔いはありません。でも野球としては、やってはいけないこと。守りやすいように塁を埋めるのがセオリー。あれは当時のパ・リーグだからできた。(日頃から注目度が高いセ・リーグの)中日ドラゴンズ時代だったら、あそこで勝負はできなかった」
土壇場で4-3と逆転した近鉄は、9回裏に2死満塁のピンチを迎えるも急遽リリーフ登板した阿波野秀幸が凌ぎ切り勝利を収める。
あと1つ。
昭和最後のパ・リーグVの行方は、第1試合終了から23分後に始まるダブルヘッダー第2試合に持ち込まれた。
<「伝説の『10・19川崎』─。なぜ近鉄は勝てなかったのか? 誰が名勝負をつくったのか?」に続く>
文/近藤隆夫