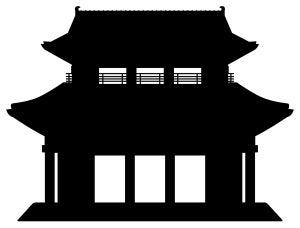『こころ』は夏目漱石の晩年における代表作の一つで、国語の現代文の教科書で読んだという人も多いでしょう。読書感想文の課題図書に採用されることも多い名作です。
新潮文庫版の『こころ』は、2021年時点で新潮文庫の累計発行部数ランキングの1位(750万部以上)となっていて、作品の人気のほどがうかがえます。
「お嬢さん」をめぐる三角関係の果てに親友を失った「先生」の告白には、エゴイズムと矛盾に満ちた人間の深層心理が垣間見えるでしょう。
本記事では200字の短いあらすじと、章ごとの詳しいあらすじ、登場人物や結末に、先生とKの死に対する考察、感想文などを紹介。作者である夏目漱石の生涯や死因についても解説します。
※本記事はネタバレを含みます
夏目漱石『こころ』のあらすじを簡単に200字で要約
『こころ』は元々、1914年(大正3年)の4月20日~8月11日まで、東京・大阪の『朝日新聞』に『こころ』というタイトルで連載された長編小説です。その後同じく1914年9月、岩波書店より『こゝろ』として刊行されました。なお現在では、『こころ』と記載されるのが一般的です。
まずは全体のあらすじを、200文字程度で簡単に確認しておきましょう。
学生の「私」は鎌倉の海で「先生」と知り合い、惹かれていく。先生はなかなか心を開いてくれず、秘密めいていて、悲しみを帯びていた。しかし私の熱意と単純さに、先生は自分の過去をいつか残らず話すことを約束した。
病の父のもとへ帰郷した私は、父の死の間際、先生からの手紙を受け取る。そこには先生が昔、親友を出し抜いて結婚を決め、その直後に親友が自殺したこと、そして自分もついに生涯を閉じるという旨が書かれていた。
『こころ』の主な登場人物
『こころ』は、「私」と「先生」と2人の視点で描かれます。『こころ』の主な登場人物についてまとめました。
私
ある夏、鎌倉の海で「先生」と出会った青年です。先生を慕い、傾倒するようになりますが、先生には何か秘密があるようだ、とも感じています。
大学を卒業して病の父のいる故郷に戻っていましたが、先生からの手紙を受け取って、東京行きの汽車に飛び乗りました。
先生
夏の鎌倉で「私」と親しくなった男性です。「先生」と呼ばれてはいますが、特に職を持たず、妻と2人で暮らしています。
「私」が出した手紙には久しく返事を書きませんでしたが、ついに1通の手紙をしたためます。それが先生の遺書になったのです。
先生の奥さん(お嬢さん/静)
先生の妻は美しい女性で、先生の手紙の中では「お嬢さん」と呼ばれています。学生時代の先生の、下宿先の娘でした。
名前は「静(しず)」と言います。
K
先生の幼い頃からの親友です。寺の次男として生まれ、医者の養子になりましたが、どちらの家とも縁が切れてしまいます。
金銭的に苦しく、過労から肉体的にも精神的に弱っているKを見かねて、先生は自分の下宿先にKを引き入れます。
道のためにはすべてを犠牲にするべき、ということを第一信条にしています。
『こころ』のあらすじを章ごとに詳しく紹介
『こころ』は「上 先生と私」「中 両親と私」「下 先生と遺書」の3部から成ります。
「私」を語り部にした「上 先生と私」「中 両親と私」と、先生が自身の過去を語る手紙という形の「下 先生と遺書」との、3部で構成されています。教科書で取り上げられることが多いのは「下 先生と遺書」の後半、Kの自殺にまつわる部分です。
なお「下 先生と遺書」は「私」目線ではなく「先生」目線で語られているため、ここで「私」と書かれているのは、「先生」自身のことなので注意しましょう。またここでは先生の妻も「奥さん」ではなく「お嬢さん」と記され、別途「奥さん」と記されているのはお嬢さんの母のことです。
それでは、章ごとの詳細なあらすじを見ていきましょう。
『こころ』のあらすじ - 上「先生と私」
友人に呼ばれて夏の鎌倉へ来た「私」は、「先生」と出会いました。なぜか先生に心惹かれた「私」は、東京に戻ってからも交友を続けます。しかし先生には、「私」や奥さんとの間に距離を置くようなところがありました。
先生は月に一度、雑司ヶ谷へ墓参りに向かうようです。その墓の主と先生にはどんな関係があるのか、先生は多くを語ろうとはしません。
そして先生は「私は世間に向かって働き掛ける資格のない男だから仕方がありません」「恋は罪悪ですよ」「人間全体を信用しないんです」などと曖昧に、言葉少なに、悲しいことを述べます。
奥さんは先生のことを「若い時はまるで違っていました」と言います。しかし奥さんにも、先生がなぜ変わってしまったのかはわからないのでした。
先生のことをもっと知りたいと、先生に大胆にぶつかって行く「私」に対し、先生は「私は死ぬ前にたった一人で好(い)いから、他(ひと)を信用して死にたいと思っている。あなたはそのたった一人になれますか」と言い、ついに「適当の時機」がくれば、自分の過去を全て話すと約束しました。
『こころ』のあらすじ - 中「両親と私」
大学を卒業した「私」は、病気の父のいる実家へ帰省します。父と母は客を招いて「私」の卒業祝いをしようと提案しますが、明治天皇の病気の知らせを受け、取りやめとなります。
その後、父の元気はどんどんと無くなっていき、先の短いことを悟った「私」は、遠方にいる兄に電報を打ちます。久しぶりに顔を合わせた兄弟は、父の死後について語り合うのでした。
そしていよいよ父が亡くなるという間際、先生から長い手紙が届きました。このような状況下では当然手紙を読んでいる時間がない「私」ですが、手紙の1ページ目に、自らの過去について「自由が来たから話す。しかしその自由はまた永久に失われなければならない」という旨の記載を確認します。
そして「この手紙があなたの手に落ちる頃には、私はもうこの世にはいないでしょう。とくに死んでいるでしょう」という句を見つけるのです。
「私」は父と家族を残し、手紙を持って東京行きの汽車に飛び乗るのでした。
『こころ』のあらすじ - 下「先生と遺書」
先生は手紙の冒頭で、真面目な「私」が、自分の人生そのものから教訓を得てくれるなら満足である、と言う旨を述べます。そして秘密にしてきた自分の過去を語り出します。
先生は20歳になる前に、病で両親を亡くしています。そしてしばらくは、その後を引き受けてくれた叔父と、その家族と良好な関係を築いていました。
しかし叔父は先生をだまし、先生に渡るべき両親の遺産をごまかしていました。その経験から人間不信となり、故郷を捨てた先生でしたが、下宿先の娘である「お嬢さん」と親しくなります。
さて先生にはKという、幼少期からの親友がいました。実家や養家とのトラブルがあり、過労で肉体的にも精神的に弱っているKを、先生は自分の下宿先に住まわせることにしました。
下宿先の奥さんや、その娘であるお嬢さんに、Kに温かく接してくれるよう頼む先生でしたが、やがてKからお嬢さんに対する切ない恋心を打ち明けられてしまいます。実は先生もお嬢さんのことが好きだったのですが、「先(せん)を越された」と思った先生は、そのことをKに打ち明けられません。
先生が打ち明ける機会をうかがっているうちに、何日も過ぎてしまいます。しかしある日Kは先生に対し、進んでいいか退(しりぞ)いていいか迷っているがどう思う、という旨を、苦しそうに尋ねます。
そして先生は「精神的に向上心のないものは馬鹿だ」と言い放ちます。かつてKが先生に告げた言葉を、そのまま返したのです。道のためにはすべてを犠牲にすべき、ということを第一信条にしているKにその言葉を投げ掛けることは、非常に残酷な意味を持っています。
先生はそのことを十分に分かった上で、Kが恋を諦めてくれるようにあえてその言葉を使ったのです。
「僕は馬鹿だ」と力なく言うKですが、「覚悟ならない事もない」と、独り言のようにつぶやきます。
Kが恋を諦め、今まで通りの道を進んでくれると思い、一度は得意になる先生ですが、ふと「覚悟」という言葉が気になり始めます。これはKがお嬢さんを諦める覚悟ではなく、お嬢さんに対して進んで行くという覚悟ではないか、と思った先生は、急いで事を運ばなくてはならないと思います。
そうして先生は下宿先の奥さんに「お嬢さんを私に下さい」と言ってしまうのです。首尾よくお嬢さんとの結婚を取り付けた先生でしたが、それを知った後、Kは自殺してしまいます。遺書と言うべき先生宛の手紙には、先生への恨みつらみは全くなく、ただ薄志弱行(はくしじゃっこう)でこれから先の望みがないから自殺する、という旨が書かれていました。
先生が奥さんや他人、そして自分自身に対して心安らかに接することができないでいたのは、このKの死が原因でした。
長年死んだつもりで生きてきた先生でしたが、明治天皇の崩御、そして35年もの間、死ぬ機会を待っていたという乃木大将の殉死を知って、ついに自殺する決心を固めたのでした。
しかし妻(お嬢さん)にだけは、本当のことを何も知らせずに、過去への記憶を純白に保ったままにしておいてやりたいというのが、先生の唯一の希望でした。
そのため「私」にも、この秘密を腹の中にしまっておくように頼み、手紙は終わります。
各セリフの心理解釈は、テストにも出やすいポイント
登場人物の心の動き、セリフの背景は、テスト勉強として『こころ』を読むときにも大切なポイントです。
例えば、恋に苦悩するKに先生が言い放った「精神的に向上心のないものは馬鹿だ」というセリフ。これは先生が「ただ一打(ひとうち)で彼を倒す事ができる」言葉として選んだものであり、「利己心の発現」として発せられたとの記載があります。
このとき先生の頭には、Kを打ち倒すことしかありません。Kが恋を成就させる、そこまで行かずとも自分の気持ちに正直になるという可能性をつぶし、自分の恋路と衝突しないように仕向ける、つまり自分の利益しか考えないエゴイズムから発せられたこの行動は、後々まで先生を苦しめることになるのです。
人間の「エゴイズム」は、『こころ』の大きなテーマの一つにもなっています。
なぜこの時、この登場人物はこのセリフを述べたのか、ということを想像しながら読み進めることが、『こころ』を読み解く上で重要です。
『こころ』の感想と考察
『こころ』は三角関係を軸として、友への思いや己の信念、利己心、迷いなどの心の動きが描かれた作品です。本作の内容について、感想を交えながら、さまざまな観点から考察していきましょう。
Kが自殺した理由
お嬢さんとの結婚が決まったのは良いものの、Kにそれを打ち明けられない先生。
自分もお嬢さんのことを好きだということすら結局言い出せていないので、どこからどう説明すればいいかわからないまま時が過ぎてしまいます。
しかしある日、下宿先の奥さんから、Kに結婚の話をしたという旨を知らされます。
奥さんによるとその時のKの様子は、驚きながらも落ち付いていたとのことでした。微笑を洩らしながら「おめでとうございます」と述べ、立ち去り際には「何かお祝いを上げたいが、私は金がないから上げる事ができません」と言ったそうです。
その時、Kが結婚について奥さんから知らされてからすでに2日がたっていたのですが、その間Kは先生に対して「少しも以前と異なった様子を見せなかった」という描写があります。それについて先生は「彼と私を頭の中で並べてみると、彼の方が遥(はる)かに立派に見えました」と述べています。
そしてその後、Kは自殺します。
後に先生はKの自殺の理由を考えます。それは失恋のつらさでもなく、また己の今まで貫いてきた信念と恋という、理想と現実との乖離からの苦しさでもなく、親友にすら理解されずに世の中でたった一人という淋しさから死んだのではないか、と述べています。
Kの遺書の内容とその意味
Kの残した手紙、つまり遺書にも、Kの自殺の本当の理由のヒントが隠されていると考えられます。
Kの遺書には、先生への怒りや恨みは一切書かれていませんでした。先生はそのことに安堵(あんど)し「助かった」と思います。
お嬢さんについては一言も述べられておらず、Kがわざと回避したのだと先生は感じました。
自殺の理由については、ただ薄志弱行(はくしじゃっこう)でこれから先の望みがないから自殺する、という旨が書かれていました。
この遺書がわかりやすいところに置いてあったのは、先生のせいで自殺したのではないかと、疑いの目がいかないようにという優しさからだったのかもしれません。
Kは最後に余った墨で「もっと早く死ぬべきだのになぜ今まで生きていたのだろう」という意味の文句を残しました。これがKの本心だったのではないでしょうか。
先生に恋心を打ち明け、「覚悟」について語った時には、彼を苦しめていたのは恋と自分の信念との葛藤だったはずです。もしかするとKの「覚悟」とは、恋の悩みを断ち切って自ら命を絶つことを意味していたのかもしれません。
しかし先生の策略を知ったことで、彼の苦悩には、親友の裏切りが加わります。Kがすでに死の覚悟を決めていたとしたら、早々にそれを果たせずにいたせいで、苦悩がより深まったとも言えるのではないでしょうか。
Kの遺書に続くのは、「早く死んでいれば、親友に裏切られることもなかった」という言葉だったのかもしれません。さらに言うと「早く死んでいれば、親友に自分を裏切らせることもなく、彼を苦しめることもなかった」という言葉である可能性もあります。
Kは、自分の弱さのせいで親友が悪の道を選んでしまい罪悪感にさいなまれていること、そして自らも孤独になってしまったことを嘆いていたのかもしれません。
先生が自殺した理由
Kの死後、先生は自責の念を抱きます。そしてかつて自分を裏切った叔父と自分は同じ人間だったのだと、自分に愛想をつかします。
そのうち先生は「自分で自分を殺すべきだという考え」を抱くようになります。しかし母を亡くした孤独な妻を残すのが不憫で、なかなか死ぬことができません。そうして死んだ気で、命を引きずって生きてきた先生は、「私」と出会うのです。
先生は死ぬきっかけを探していたのでしょう。明治天皇の崩御、そして35年もの間、死ぬ機会を待っていたという乃木大将の殉死を知って、ついに自殺する決心を固めたのでした。
先生は明治天皇の崩御の際に「明治の精神が天皇に始まって天皇に終った」「最も強く明治の影響を受けた私どもが、その後(あと)に生き残っているのは必竟(ひっきょう)時勢遅れだ」とも感じています。当時の多くの人たちにとって、それほどに大きな出来事だったということがうかがえます。
「時代の終わり」に死期を感じた先生は、人生の引き際として最もらしい理由を見つけたのかもしれません。
ただ燃え尽きるように、ちょうどいい時期が来たから消えるような先生の命は、その死に際がどんなものだったのかも作中では語られませんでした。Kが死んだとき、本当の意味では先生も共に死んでいたのかもしれません。
先生とKの違い
お嬢さんへの恋心に対し、Kを出し抜いて行動に出た先生と、それを非難せずに自ら命を絶ったK。先生はKに「おれは策略で勝っても人間としては負けたのだ」と感じます。
親友でありながら、2人の人生は相反するものでした。
先生は友情と自分の善良な心を汚してまで恋を手に入れたものの、自分を責め続けて、苦しみながら屍(しかばね)のように生きていきます。
一方でKは、友を思い、黙って恋を諦め、早々にこの世を去ります。
人は誰でも、先生のようにも、Kのようにもなり得ます。それぞれの立場で本作を読んでみると、また違った見え方をするかもしれません。
先生が「私」に遺書を書いた理由
先生はなぜ、「私」に遺書を送ったのでしょうか。先生は「私」にいずれ過去のことを話すと約束していましたが、それだけではなく「半(なか)ば以上は自分自身の要求に動かされた結果なのです」と述べています。
先生は、「私自身さえ信用していない」と言います。人間に失望し、誰一人信用せず、孤独に生きていた先生のもとに足しげく通った「私」。
「私は死ぬ前にたった一人で好(い)いから、他(ひと)を信用して死にたいと思っている」と述べる先生にとって、「私」は希望だったのでしょう。
また自分よりもずっと若く、まだ恋も知らない、真面目で単純で大胆な「私」に、先生はそうありたかった自らの姿を重ねているようにも思えます。
その「私」に過去の過ちを語ることは、何も知らなかった頃の純粋な自分に向けて手紙を書くような気持ちだったのかもしれません。
作者の夏目漱石とは? その生涯や死因、脳の行方など
夏目漱石(なつめそうせき)は、明治から大正時代にかけて活躍した小説家・英文学者です。
徳川慶喜が大政奉還を行い、江戸時代が終わる年である1867年(慶応3年)、現在の新宿区に生まれ、1916年(大正5年)にこの世を去りました。
本名は金之助であり、漱石は「漱石枕流(そうせきちんりゅう)」という四字熟語をもじったペンネームで、「失敗を認めず、負け惜しみする人」という意味があるといわれています。
夏目漱石は上に兄が4人、姉が3人おり、生まれてすぐに養子に出されます。9歳の時に義父母が離婚したために実家に戻っています。
1890年に現在の東大文学部である帝国大学文科大学に入学、1893年に卒業した夏目漱石は、愛媛の松山中学校や熊本の第五高等学校の講師として働きました。1900年には文部省から命じられてイギリスに留学します。
1903年に帰国すると、第一高等学校と現在の東京大学にあたる東京帝国大学の英文科の講師になりました。
1907年、40歳になった夏目漱石は教職を辞めて朝日新聞社に入社し、専属作家になります。
1916年の12月に胃潰瘍のため亡くなり、雑司ヶ谷霊園に埋葬されました。なお『こころ』の作中では、Kの墓も雑司ヶ谷にあると描かれています。
夏目漱石の脳は、東大の医学部にホルマリン漬けで保存されています。日本人男性の脳の平均は大体1,350gですが、夏目漱石はそれよりも若干重く1,425gありました。
夏目漱石の1,000円札は、1984年から2007年まで、20年以上もの間発行されていました。
夏目漱石は何を書いた人? 人物像や『こころ』など作品のあらすじを解説
エゴと苦悩の果てに「私」が見つけた答えとは
先生はKに人間として負けたと感じ、「死んだ気で生きて行こうと決心」する一方で、遺書は妻を気遣う言葉で締めくくられました。
Kを裏切り、犠牲にしてまで手に入れたお嬢さんとの結婚生活を、先生は「幸福」だったと振り返ります。「人間の罪」を感じてKの墓参りに向かいながらも、妻への愛を振り切ることはできずにいるようです。
先生は死んでもなお、妻に本当のことを告げず、自分のように汚れてほしくないと願っています。先生にとってこの恋、そして愛は、ある意味で希望だったのかもしれません。
しかしそれもまた、先生のエゴだと考えることもできます。奥さんに本当のことを告げたら、奥さんはもっと幸せだと感じたかもしれません。それともやはり、奥さんに暗い影を落とすかもしれません。
人の「こころ」とは、どこまでも答えのないものです。だからこそ、皆が向き合うべきものなのでしょう。
※作品内には、現在では不適切とされる可能性を持つ表現がありますが、本記事では基本的に、作中の表現を生かした形で記載しています