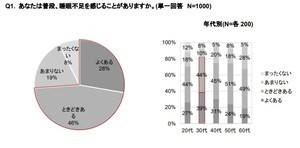「来週は忙しいから、体調崩さないように今日はしっかり寝なくちゃ」
「休日は、たっぷり寝て疲れをとろう」
このようなことを考えて、たっぷり睡眠時間をとっている人もいるのではないでしょうか。確かに睡眠は非常に大切です。しかし、ただ長い時間寝ていれば、病気や不調知らずの元気な体になるかといえばそうではないようです。
順天堂大学医学部教授の小林弘幸氏の著書『名医が教える免疫力が上がる習慣』(アスコム)の内容から抜粋・編集して、「免疫力を上げて、病気や不調を遠ざける睡眠法」を紹介します。
睡眠を最高の「免活」にするちょっとしたコツは
皆さんは、「寝れば治る」という言葉を聞いたことはありますか?おまじないのように聞こえますが、本当です。
睡眠時間が短いと風邪をひきやすくなることは、研究によっても明らかにされています。2015年に米学術誌「Sleep(スリープ)」に発表された研究によると、睡眠不足の人が風邪をひく確率は、十分な睡眠をとった人より4倍以上高くなると報告されています。
一晩の睡眠時間が6時間未満だった人は、7時間を超える睡眠時間をとっていた人と比べて風邪の発症リスクが4・2倍高く、5時間未満の人は4・5倍も高いという結果でした。
ただし、睡眠が大切といっても、ただ眠ればいいというわけではありません。実際、9~10時間以上の睡眠をとっている人は、将来的に体重が増えやすかったり、がんや生活習慣病になりやすかったりする傾向があるという調査もあります。
また、以前は「22時〜2時の間が睡眠のゴールデンタイム」というのが定説でしたが、近年はさまざまな研究により、免疫力に関わる成長ホルモンは時間帯に関係なく、眠りについてからの3時間のあいだに多く分泌されることが明らかになっています。
つまり、眠りに落ちてから3時間にぐっすり眠ることができれば、成長ホルモンが分泌されて免疫力が上がる、質のいい睡眠だといいます。
といっても睡眠の質がいいかどうかの判断は、なかなか難しいかもしれません。ただ、次の項目がひとつでも当てはまる人は睡眠の質が悪くなっている可能性があるので、要注意です。
・眠るまでに時間がかかる。
・夜中に何度も目が覚めてしまう。
・朝起きたときに頭がボーッとする。
・昼間に強い眠気を感じて集中できない。
・寝ても疲れがとれない。
・眠りが浅くて熟睡感が得られない。
「夜は早めに布団に入るし、睡眠時間はしっかりとれているはず!」と自信を持っている人でも、実は眠りが浅くて質のよい睡眠がとれておらず、免疫力が低下している……というケースも珍しくありません。
睡眠の質が悪いと、どんなに長時間眠ったとしても、睡眠が不足しているのと同じことですので、以上のような状態があれば注意が必要です。
「免活睡眠」のキーワードは「7時間睡眠」
ただし、睡眠の質がよければ、3時間でも、4時間睡眠でもいいというわけではありません。
理想の睡眠時間については、先ほども述べたように「3~4時間でも問題ない」という人もいれば、「8時間以上眠らないと体調を崩す」という人もいるなど、人によって個人差がありますが、最近の研究では、平均して7時間くらい眠っている人が最も死亡率が低いといわれています。
また、2010年に発表された岡村尚昌氏らの「睡眠時間と唾液中の免疫物質ⅠgAの関係」に関する研究によると、睡眠時間が6~8時間のグループは免疫力に関わるⅠgA(Immunoglobulin A:免疫グロブリンA)の分泌量が多く、5時間以下もしくは9時間以上のグループは、ⅠgAの分泌量が減少したという結果が報告されています。
つまり、睡眠時間は、短すぎても長すぎても免疫力が低下します。
以上から考えて、免活睡眠がおすすめする睡眠時間の目安は、7時間。まず 起床時間を基準にして、そこから7時間を引き算して、就寝の時間を決める。たとえば、いつも朝7時に起きるのであれば、就寝時間は夜12時になります。
免活睡眠の理想をいえば、同じ時間に寝て、同じ時間に起きる生活がベスト。しかし、毎日実行するのはなかなか大変です。忙しくて就寝時間が遅くなってしまう日もあるでしょう。
そんなときは、起床時間をそろえるのがポイントです。免疫システムをコントロールしている自律神経と連動している体内時計は、朝日を浴びることで毎日リセットされています。寝る時間が遅くなっても、いつもと同じ時間に起きて朝日を浴びれば、自律神経が乱れにくくなります。
寝不足かな?と感じたときは、起きる時間を遅くするのではなく、寝る時間を早めることで睡眠時間を調整するのがおすすめです。起床時間を守れば、少しぐらい睡眠時間が長くなっても構いません。残業がない日や休日などは、いつもより1〜2時間早く布団に入ってみるといいでしょう。
休日の寝だめは時差ぼけの原因!
絶対に避けたいのが、平日の睡眠不足を休日に「寝だめ」で補おうとすること。
平日の睡眠不足を解消するために休日に寝だめする不規則な生活は「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ぼけ)」という症状を招き、睡眠の質を低下させることが近年の研究でも証明されています。
ソーシャル・ジェットラグとは、「平日と休日の就寝・起床リズムのずれによって起こる心身の不調のこと」で、2006年にドイツの時間生物学者・教授のロネンバーグ氏らによって提唱された新しい概念です。「社会的時差ぼけ」が疲労感と関連することが確認されています。
疲労感とは免疫力が低下している現れでもあるので、休日の寝だめが免疫力を低下させる可能性があるともいえるのではないでしょうか。
免疫力を維持するには、起床時間を守って、できる限り7時間の睡眠時間を確保することです。
著者プロフィール:小林弘幸(こばやし・ひろゆき)
 |
順天堂大学医学部教授。日本スポーツ協会公認スポーツドクター。
自律神経研究の第一人者として、プロスポーツ選手、アーティストなどへのコンディショニング、パフォーマンス向上指導にかかわる。書籍、メディア出演も多数。