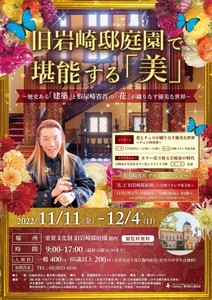発酵デザインラボが企画・運営する博覧会「発酵で旅する東京の森」が、立川のGREEN SPRINGSで開催されています。東京の西、多摩エリアの発酵食と47都道府県の発酵食が一堂に集結し、日本の発酵文化を存分に味わえる。場内では角打ちでクイッと一杯やったり、ところせましと並んだ様々な発酵食品も購入できる、そんなユニークなイベントの一部をご紹介します。
この博覧会のキュレーションを務める“発酵デザイナー”の小倉ヒラクさんは今回、立川、昭島、福生、羽村、青梅にまたがるエリアを巡り、各地の発酵食を調査。多摩の気候風土と文化によって培われた、多様で多彩な発酵食に出会ったといいます。
「東京の西側の山間部には清水が湧き、その地下には酒や醬油などの発酵食品を醸す仕込み水が流れる“隠れた水の道”があるんです」とヒラクさん。その水を、青梅の小澤酒造さんは「ピュアで、毒がなく、微生物の栄養となるミネラルを適度に含んだ、“森の仕込み水”」と語っていたそう。
そんな水で醸された多摩の発酵食は日本酒、酒まんじゅうなど、古くから受け継がれてきたものに加えて、近年ではビールやチョコレート、パンまで、バラエティに富んでいます。
東京都には10軒の酒蔵があり、大半が西側に集中しています。ここでは「田村酒造」「石川酒造」「小澤酒造」の3つの酒蔵が紹介されています。
「福生の石川さんと田村さんは、比較的やわらかい中軟水で仕込んだ、軽やかな飲み口で、街の人に愛されてきたお酒。いっぽう青梅の小澤さんはどっしりと辛口で、山仕事をやっている人たちに愛されてきたお酒です」とヒラクさん。それぞれのキャラ(酒)の個性がわかりやすい!
また多摩の発酵食に加えて、全国47都道府県から発酵食を集めた企画展も開催されていて、知られざるユニークなローカル発酵食がずらり! 特に“ニオイ”に特徴があるものは、嗅ぐこともできるようになっています。
伊豆諸島の新島で生まれた「くさや」は、島で塩が貴重だった江戸時代に、魚の塩漬けの塩汁をリサイクルするという苦肉の策で生まれた発酵食。今でいうインフルエンサーが島を訪れてくさやを食べ、その歌を一句詠んだらバズり、高値のつくお土産になったのだとか。
こちら「碁石茶」は、高知県の山間地のたった一軒の農家の納屋で作られている、“幻の発酵茶”。遅摘みの茶葉をむしろで巻いて発酵させて“お茶の鰹節”みたいなものを作り、さらに乳酸発酵させる……という、二段発酵で作られているそうです。
会場には「角打ち」コーナーも常設され、日替わりで3種類のお酒を1杯500円で楽しめるとあって、酒好きにはたまりません。
さらにもうひとつの目玉が、物販のコーナー。多摩エリアはもちろん、企画展に登場した全国のローカル発酵食品たちがところ狭しと並んでいるので、買い物欲に火が付くこと間違いなし。
多摩と全国のローカル発酵食を知り、ニオイを嗅ぎ、個性豊かな酒を味わい、気になる発酵食品に出会ったら買って、帰っておうちで味わう、「発酵」を存分に堪能できる博覧会。気になった方はぜひ足を伸ばして、奥深い発酵の世界に触れてみてはいかがでしょうか。
■information
「発酵で旅する東京の森 (Fermentation Tourism Tokyo)」
会場:GREEN SPRINGS 2F TAKEOFF-SITE(東京都⽴川市緑町3-1)
期間:12月4日まで(11:00〜19:00)
入場無料