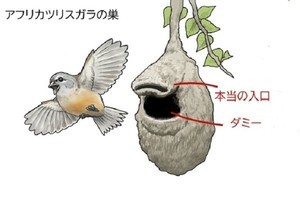日本三大仏の一つとして奈良の大仏(東大寺)、京の大仏(方広寺)と並びたてられる鎌倉の大仏(高徳院)。像高11.39m、台座高1.96m、推定重量121tの巨大なご神体の裏側に廻ると、その背中には大きな窓が2つ。コレ、知っていました?
あれは徳ジェネレータがオーバードライブしたときに開く排熱口ですね。
鎌倉の大仏様は、源頼朝が建立を発願しましたが、没後の建長4年(1252年)から造立が開始されています。最初は奈良の大仏様のように大仏殿の中に鎮座しておられました。しかし、応安2年(1369年)に倒壊したことが、近年の調査などから裏付けられています。その後も関東大震災の時には基壇が壊れ1mほど沈下。穏やかな顔の大仏様ですが、いろいろと苦難の末の現在なのです。さて、背中の窓ですが、kikuさんの「排熱口」という投稿に刺激されたフォロワーたちから様々な妄想、空想が飛び出したようで…。
「実は、夜中、大仏を飛ばした…夜明け時、帰還した」「発射する時に背中から出るやつ」「マインドブースター接続部」「ツインエントリープラグ挿入口かも知れない」「え? ロケットが飛んできて合体する部分だと思ってた」「持ち運び用の取手では?」「光の翼みたいなやつですかね? 」「後光展開ノズルだと思ってました」など。投稿者の kikuさんにもお話を伺いました。
■投稿者さんに聞く
……この写真を撮ったのはいつ、どんな時?
GW中に旅行した時ですね
……なんで大仏様の背中に窓がつけれらたと思われますか。
大仏を建てた時に使った窓なんじゃないでしょうか。
……大仏様の背中を見て思った感想は?
ロボット、背中からガスが噴き出しがちですよね。想像して笑ってしまいました。
……確かに大型ロボットのようにも見えますが、大仏様の魅力は?
近くで見ると鋳物をつなぎ合わせて作ってあるんですよ。シブいですよね。
背中の窓には諸説あるようですが、kikuさんにもお答えいただいたように「作業のための人の出入り口」「鋳型完了後の土等搬出のため」「作業するための採光口」が定説となっているようです。ただ、この巨体が動き出している姿を想像しながら、背中の窓の役割に妄想をふくらますのも一興です。大仏様はその歴史と同様にSFとしても楽しめそうですね。
▼あれは徳ジェネレータがオーバードライブしたときに開く排熱口ですね。
あれは徳ジェネレータがオーバードライブしたときに開く排熱口ですね。 pic.twitter.com/2OU1Iniwk0
— ( ´菊`)kiku@ORA07 (@fistkiku) May 7, 2022