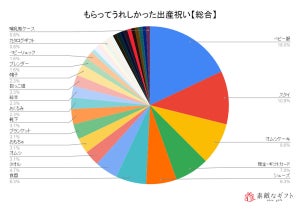仕事の関係者や友人、きょうだいや親戚が出産したら、「おめでとうございます」の気持ちをこめて、出産祝いを贈ります。出産祝いを現金で贈る場合は祝儀袋に入れ、ギフトを贈る場合はのし紙を添えます。
出産は生まれてきた赤ちゃんにとっても、新しく親になった人にとっても、節目となるおめでたい出来事なので、親しい間柄であっても正式なマナーにのっとって行いましょう。
本記事では、祝儀袋やのし紙の書き方をパターンに分けてご紹介します。シーンによって選ぶべき種類も異なるため、まずは基礎知識からしっかり確認しましょう。
出産祝いに使われる「祝儀袋」とは
「祝儀袋」は、出産祝いとして現金を贈る場合に使い、「のし」や「水引」が添えられている祝儀袋が一般的です。別名「のし袋」とも言います。
「のし」とは
「のし」は、袋右上のひし形状をした折り紙を指し、お祝いの贈答品に付ける飾りです。本来は干しアワビを意味しており、貴重で高価なアワビをお祝い事に贈る昔の風習の名残が今日にも残っています。
「水引」とは
「水引」は、祝儀袋にかかっている飾り紐のことです。水引は和紙を“こより”にして水のりで固めたもので、おめでたい時は赤や白、金、銀などに染めたものを使います。
水引の結び方には種類があり、「一度きり」という意味を込めた「結び切り」は結婚式の祝儀袋に、何度重なってもうれしい出産などの祝い事には、「蝶結び(花結び)」など、シーンにより使用する種類が異なるため、適切なものを選ぶようにしましょう。
「のし紙」とは
「のし紙」は、「のし」や「水引」がすでに印刷されている包み紙のことです。贈答品は、のし紙をかけて贈ります。
デパートなどの小売店で購入した贈答品は、のし紙をかけてくれるケースがほとんどです。さまざまな用途に合わせた「のし」が用意してあり、配送か手持ちかによっても、適切な包装をしてくれます。
のし紙も同じく水引の結び方や色が決まっています。出産祝いには、紅白の蝶結びの水引が印刷されたものを選ぶようにしましょう。
出産祝いに選ぶべき「祝儀袋」の種類とは
伝統的な祝儀袋では、白い袋に赤や白、金銀の水引を使ったものですが、近年ではキャラクターが印刷されたものや、ピンクや水色などのパステルカラーのかわいらしい祝儀袋も販売されています。中には、水引が手書きのイラストになっているものもあります。
現代風のかわいらしい祝儀袋は、仲の良い友人やきょうだいには喜んでもらえるでしょうが、目上の人に対しては適切ではありません。贈る相手との関係性に合わせて、ふさわしい祝儀袋を選びましょう。
「祝儀袋」の書き方
贈る相手にふさわしい祝儀袋を選んだら、表書きなどを記していきます。ここでは出産祝いにふさわしい祝儀袋の書き方を説明します。
「表書き」の正しい書き方
水引の上側に書く言葉を「表書(おもてが)き」といいます。ここには「御祝」や「御出産祝」など、何のための贈り物か、贈り物の目的を書きます。
出産祝いの場合は「御出産祝」と書くのが一般的ですが、人によっては4文字になることを嫌う人もいるので注意が必要です。四文字になるのを避けるために「御出産御祝」のように5文字にすることもあります。
「名入れ」の正しい書き方
水引の下には、贈り主の名前を書きます。贈り主が個人か複数人かによって、名前の書き方が異なりますので注意しましょう。
個人で贈る場合
水引の下・中央に、表書きより少し小さめの字で氏名を書きます。
夫婦で贈る場合
全員の名前を表書きに記載します。夫婦の場合は、夫の名前をフルネームで書き、妻は名前だけを左に書くという形式が一般的です。名字を大きめに書き、下に夫婦の名前を並べて書く場合もあります。また別姓の場合は、2つの姓名を並べて書きましょう。
連名(職場の同僚や上司との連名)で贈る場合
役職や年齢の高い人の名前を中央に置き、役職や年齢に従って左へ順に書きます。4人以上の場合は、会社名や部署名を用いるか、代表者のみ氏名を書いて、「〇〇課一同」のような形で記載しましょう。このような表書きでは、全員の名前を別紙に書き、同封してください。
連名(友人との連名)で贈る場合
友人の連名は3名程度までとし、右から五十音順で書きます。4人以上の場合は代表者の名前を書き、「外一同」と左に書きます。前述と同じように、全員の名前は別紙に書き、同封しましょう。
「中包み」の正しい書き方
「中包み」とは祝儀袋の中に入っている封筒です。同僚や友人らと名入れをする際に別紙を用いた場合、この中包みに包んでおきましょう。
中包みには表面、裏面に書くことが決まっているので、ルールに従って記載します。
【表面】
表面には、包んだ金額を縦書きで書きます。金額は大字で記載するのがマナーです。大字とは、証書などで用いられる漢数字の「一」「二」「三」などの代わりに用いられる旧文字のことです。
| 漢数字 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 百 | 千 | 万 | 円 |
| 大字 | 壱 | 弐 | 参 | 肆 | 伍 | 陸 | 漆 | 捌 | 玖 | 拾 | 佰 陌 |
仟 阡 |
萬 | 圓 |
仮に五千円を包んだ場合は、中包みの表面に「金伍仟圓」と書きます。
【裏面】
中包みの裏面には、左下方に贈り主の住所と氏名を書きます。市販の祝儀袋の中包みの場合は、住所氏名欄がすでに用意されていますので、そこに記入してください。
【お札の入れ方】
中包みには新札を入れます。お札の表面(顔が印刷されている側)が表に向くように入れるのがルールです。
「のし紙」の書き方
「のし紙」は各部名称はもちろん、書き方も、基本的に祝儀袋と同じです。印刷された水引の上側を「表書き」、下側を「名入れ」と呼びます。
贈答品をお店で購入した場合、お願いすれば表書きや名入れなどもしてくれます。基本的な書き方を理解しておけば、お願いする際にも「表書きは〇〇としてください」「名入れには〇〇と△△の連名でお願いします」と頼むことも可能です。自分で書くチャンスがあれば、ぜひ筆を執ってください。
「表書き」の正しい書き方
水引上部の表書きは、祝儀袋と同じく「この贈り物が何のためであるか」を書く欄です。出産祝いを贈る場合は「御出産祝」や「御出産御祝」と書きます。
「名入れ」の正しい書き方
前述の「表書き」同様、基本的に祝儀袋の書き方と同じです。水引の下、表書きと中心線を合わせ、表書きよりやや小さめの字で、贈り主の名前を書きます。連名の場合は、中央に代表者の名前を書き、左に他の人の名前を記載します。人数が多い場合は「〇〇課一同」のように、組織名を書く場合もあります。
「祝儀袋」「のし紙」に使う筆記用具
市販の祝儀袋やのし紙には、すでに表書きが書いてあり、用途に合わせて選ぶようになっているものもあります。いずれも毛筆のようなフォントで印刷されていますが、自分で文字を書く場合には何を使って書けばよいのでしょうか。ここでは祝儀袋や水引に文字入れする際の筆記用具について説明します。
毛筆が理想だが、筆ペンでも可
結婚や出産などの慶事には、濃い墨の色で書く毛筆が理想です。しかし書道の心得のある人を除くと、今日の私たちは毛筆で書く機会はほとんどありません。その場合は、筆ペンを使用してかまいません。
筆ペンを選ぶ際には、インクの色が濃い黒のものを選びます。筆ペンの中には薄墨の種類があるため、注意が必要です。薄墨のものは弔事の際に「突然のことで墨をする暇もない」あるいは「涙で墨が薄まった」という意味をこめて使います。
万年筆やボールペンは不適切
祝儀袋やのし紙に表書きや名入れをする場合には、黒く太い楷書体で書くことが基本とされています。万年筆やボールペンで書いた文字は細いため、祝儀袋などにはふさわしくありません。筆や筆ペンがない場合は、太めのサインペンで書いても大丈夫です。
ただし中包みの封筒に記入欄が印刷されていて、その欄が狭い場合などにはボールペンを使用しても問題ありません。
出産祝いのメッセージの書き方のポイント
出産祝いにギフトを贈る際、お祝いの気持ちを込めたメッセージも添えると、より祝福していることを伝えられます。
ただし、お祝いのメッセージと言えども、一定のマナーがあります。お祝いの気持ちを文字に紡いだはずが、相手の気分を害するようなことになってしまっては、せっかくの気持ちが台無しです。しっかりと出産祝いのメッセージのマナーを理解しておきましょう。
「忌み言葉」など、特定の表現を避ける
不幸や縁起の悪い事象を連想させる忌み言葉は、出産祝いでは避けるようにしましょう。具体的な一例を以下にまとめました。
- 「流れる」
- 「落ちる」
- 「枯れる」
- 「早い」
- 「短い」
- 「失う」
また、励ましの意味を込めた「頑張れ」もおすすめできないフレーズです。特に初産のママにとっては初めての育児となるため、産後間もない時期は不安な気持ちに苛まれる日々が続くことが予想できます。そのようなタイミングでの「頑張れ」という言葉は、かえってプレッシャーになってしまう可能性があります。
同様に、「早く」「大きく」という表現も、赤ちゃんの成長には個人差があるため、出産祝いのメッセージとしては避けたほうがよいです。
メッセージは出産後1カ月までを目安に贈る
出産祝いのメッセージは、産後1週間から1カ月を目安として贈るようにしましょう。
出産してから数日はママがまだ入院している可能性がありますし、退院してからも自宅への赤ちゃんの迎え入れでバタバタすることも考えられます。そのため、生後7日目の赤ちゃんに名前をつける「お七夜」を過ぎて一段落ついた頃を見計らって贈るとよいでしょう。
一方で、遅すぎても出産祝いの意味が薄れてきてしまいます。赤ちゃんの健康を祈願する「お宮参り」を行う生後1カ月までを一つの目安とし、このタイミングまでに贈るようにしましょう。
句読点は控えたほうがよい
文章中に使う「、」や文末に使う「。」といった句読点は、「分ける」「区切る」などの意味合いを持つため、祝福メッセージには不要との考え方があります。あまり気にしないという人もいるかもしれませんが、最悪の事態を想定しておくならば、使わないほうが無難と言えるでしょう。
出産祝いのメッセージの例文
ここからは、具体的なメッセージの例文を贈る相手ごとにご紹介します。
【親しい友人に贈る際のメッセージ例文】
しばらくは無理をせずにゆっくり休んでね そして落ち着いたらまた皆で集まろうね!
【親戚に贈る際のメッセージ例文】
困ったことがあったら遠慮なく相談してくださいね お盆に会えることを今から楽しみにしています
【会社の同僚に贈る際のメッセージ例文】
子育ては大変かと思いますが ○○さんの職場復帰を皆心待ちにしております まずは無理せずにゆっくりと過ごしてください
【会社の上司や取引先に贈る際のメッセージ例文】
赤ちゃんの健やかな成長とご家族の皆様のご多幸をお祈りしております
家族にとって、新しい命を迎える出産はとても喜ばしい出来事です。昔から出産をお祝いするために、周囲の人はご祝儀やお祝いの品を贈ってきました。
祝儀袋やのし紙、のしや水引などは、それぞれ古くからの歴史と由来があり、それぞれ意味を持ちます。のしは、お祝いの品に添えていた干しアワビから来ていること。水引の結び方にも、「ほどいて何度でも結び直せる」=「喜びは何度重なっても喜ばしい」ことを意味していること。出産祝いを贈ることは、日本の伝統的な文化の一端を知る機会でもあります。
約束事の意味をきちんと理解し、作法に従って贈ることで、お祝いの気持ちもしっかりと伝わります。祝儀袋やのし紙のルールを守り、先方の幸せを願い祝福していることを心から表現しましょう。