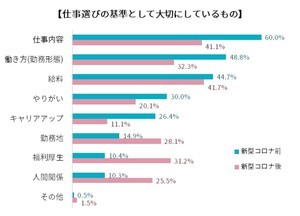伊藤園は5月20日、都内で第3回 伊藤園健康フォーラム『お茶で人生100年時代を豊かに生きる知恵』を開催。「新型コロナウイルスと茶カテキン」「口腔ケアと茶カテキン」といったテーマの基調講演や、コロナ禍ならではの新・生活習慣病と茶カテキンに関するパネルディスカッションを行った。
消費者の生活の質向上へ
冒頭では、伊藤園 中央研究所 所長の衣笠仁氏が登壇。同社ではこれまで、緑茶とインフルエンザ予防、緑茶と生活習慣病の改善などの観点で消費者の生活に役立つ研究を行ってきた。衣笠氏は「今後、新型コロナウイルスと闘い、共存していく時代になります。そのためしっかりとした予防方法を身に付け、ウイルスに立ち向かう身体をつくっていかなければなりません。お茶がどう活かせるか有識者と考えていきます」と挨拶。本フォーラムにより、消費者の生活の質が向上できれば嬉しい、と話した。
新型コロナウイルスと茶カテキン
続いて「新型コロナウイルスと茶カテキン」というテーマで、京都府立医科大学大学院医学研究科 免疫学 教授の松田修氏が基調講演を行った。松田氏は「まだ試験管で行った実験の結果しか分かっておらず、ヒトにおいても有効なのかは未検証です」と断ったのち、お茶がウイルス拡散の予防に一定の効果を示すのでは、との見解を示した。
「もともと新型コロナウイルスを抑制するような天然物、食品成分がないか探していたところ、お茶の成分に行き着きました。緑茶のカテキン、ほうじ茶のカテキン誘導体、紅茶のガレート型テアフラビンが、ウイルスの感染能力を低下させることを見出しています」と松田氏。試験管における実験では、緑茶、ほうじ茶、紅茶のいずれかで10秒間の処理を行うと、新型コロナウイルスの感染力が100分の1~検出感度以下に低下したという。なお濃度は薄くても効果があり、ペットボトルや急須のお茶でも充分な効果を得られたとしている。
このことから、新型コロナウイルスの感染者がお茶を飲んだとき、その人の飛沫に含まれるウイルスは不活化しているのでは、と松田氏は推察。ひいては、これが感染拡大の抑制効果につながるのでは、とした。もっとも、新型コロナウイルスは人の経口だけでなく、鼻、気道などからも感染することが分かっている。このため「自分が罹患しないため」というよりは、「飛沫で他人を感染させないため」という公衆衛生学的な話に限定されるようだ。
口腔ケアと茶カテキン
また「口腔ケアと茶カテキン」について、東京大学大学院医学系研究科 イートロス医学講座の特任准教授・米永一理氏が基調講演を行った。米永氏は、お茶の効果については世界中で様々な研究が行われており、歯周病の予防になる、口腔がんの発症率が減少する、血圧が下がる、総コレステロールが下がる、といった効果はすでにエビデンスがあると説明する。
そのうえで、コロナの時代になりマスクの着用シーンが増えたことで、自分の口臭を気にする人が増えたと紹介。そこで、最近ではお茶に含まれる「カテキン」に口臭抑制効果があるとの研究が行われている、と述べた。なお、お茶の濃度は大きな問題ではなく、人と会う直前などに飲むと有用だという。
withコロナの時代、お茶の有効性
フォーラムの後半では、さらに有識者2人を加えて「コロナ禍においてクローズアップされる新・生活習慣病と茶カテキン」と題したパネルディスカッションが実施された。
まず長期自粛による社会交流の制限は、健康にどのような変化を与えているのだろうか。TLC医療会ブレインケアクリニックの名誉院長・今野裕之氏は「コロナ禍において、患者の方は感染するのではないかという不安感や、外出控えのストレス、そして経済的な不安も受けています。それまで安定していた患者も、うつ症状の悪化や認知機能の低下が見られるようになりました」と指摘する。
福岡県みやま市のみやま市工藤内科 院長・工藤孝文氏は「体内リズムが狂うことでコロナ太りになり、血糖値や血圧も上がる症状が見られます。睡眠の質が落ちることにより過食ホルモンが身体から出て、その結果食べすぎてしまい、内臓脂肪が増え、高血圧や糖尿病のリスクが増す、といった負のスパイラルに入ってしまうことが考えられます」と指摘した。
また、そのようなコロナ禍における新たな生活習慣病に対して、茶カテキンが有効であることについても言及が行われた。今野氏は、認知機能の低下の予防には、お茶を1日に何回も飲むと良いと勧める。「1日に5杯以上飲んで頂くと、認知機能の低下の予防に役立つと言われています。高齢者によくある脱水による意識障害も、ある程度解決します。またテアニンによるリラックス効果も期待できるでしょう。テアニンは比較的ぬるめの温度で抽出されやすく、かぶせ茶に多いと言われています」。
工藤氏は、コロナ太りを改善するお茶の利用法として、お茶をふりかけにして食べる"出汁緑茶"を紹介。「緑茶の成分にはカテキン、テアニンなどが入っています。緑茶を食べることで、食欲の制御、脂肪燃焼の効果が期待できます」。ちなみにお茶の産地では、柔らかい葉である新茶の出し殻にポン酢を垂らして食べる方法もあるそうだ。
米永氏によれば、口臭ケアの観点から、お茶は「含み飲み」をすると良いという。「『含み飲み』は、口に30秒くらい含み、口の中に行きわたらせてから飲む方法です。漢方薬でも、口腔内環境を整えるため含み飲みすることもあります」と解説。なお口腔環境が汚いと、菌が血流に乗りやすく、ひいては菌を全身にばらまく原因にもなるとのこと。口腔ケアは、健康のためにも重要であると説いた。
コロナ禍では、認知機能の低下や、ストレスの増大、コロナ太り、口内環境の悪化など、新たな健康の課題が起きている。こういった課題に対して有用なお茶や茶カテキンとの上手な付き合い方として、衣笠氏は4つのポイントを挙げた。「ひとつは自分のため周りのために飲む衛生習慣を身につけること、そして『含み飲み』で口腔内の健康管理を行うこと、またお茶で心にゆとりとコミュニケーションを持つこと、最後にお茶を飲みながら体内リズムを整えることです」。すぐに始められるお茶の利用法を提案され、第3回 伊藤園健康フォーラムは閉会した。