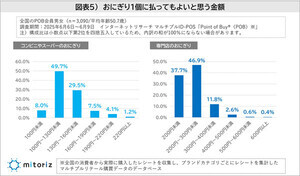具体的なアドバイス
それでは具体的なアドバイスをみていきましょう。
貯蓄を目的別に分ける
家賃がかからなくなった後、家計を緩めることよりも月々の貯蓄を増やされたYさんご夫婦に好印象を受けました。今後必要になる仕送り代や老後資金などもしっかり考慮されているようで安心です。お子様2人は高校受験や大学受験を控え、これからますますまとまった資金が必要になることが予想されます。引き続きしっかり貯蓄を続けていきたいですね。
そこで提案したいのですが、貯蓄は目的別に分けてはいかがでしょうか。現在の貯蓄の状況や、貯蓄の使い方を拝見すると、学資保険で教育費の準備をしている以外はとくに目的を分けず、すべての貯蓄を一緒にまとめ、必要になったときに「お金が貯まっているところ、引き出しやすいところから出す」というふうにされているのではないかという気がします。
Yさんご夫妻も認識されているように、この先Yさんご家族が準備すべき資金として「進学資金」「住宅の修繕・メンテナンス資金」「老後資金」があります。それぞれ必要となる時期は違いますが、「お金が貯まっているところから出す」というのを繰り返していれば、別の何かの目的でお金が必要になったり、老後が近づいたときに貯蓄が足りていなかったりする状況になりかねません。
そこで、これらの3つの目的別に「いつまでに」「いくら必要か」のプランを立ててみましょう。こうすることで、たとえば「進学資金は2年後に必要だから元本確実な定期預金、リタイアまでには20年近くあるから老後資金は運用も検討する……」など、資金準備やお金の出所の設計をしやすくなります。
まずは現在ある貯蓄をどの目的に充てるか、これから積み立てる分はどの目的の分にするかなど、ボーナスから貯金する分も含めて考えてみましょう。なお、老後資金のためにはiDeCo(イデコ)を利用されるのもいいでしょう。原則、60歳まで払い出せないため、他の資金との区別をしやすくなります。
3つの目的と言いましたが、ほかにも車や家電製品の買い換え、家族旅行の費用など、不定期にさまざまなお金が必要になります。これらは「特別費」としてまとめ、前述した3つの目的分とは別に一定額を確保しておくことも大切です。
住宅の修繕費は月々の住居費として貯めていく
Yさんご家族は古い一戸建てにお住まいとのことで、目的別貯蓄のなかでも住宅の維持費もしっかり準備が必要になりそうです。今回250万円の修繕費を払うことになりましたが、今後も定期的に大きな金額がかかることも予想されますから、そのときになって困らないように毎月一定額を積み立てていきましょう。
維持費にいくらを要するかは、住宅の状況やメンテナンス・修繕をする箇所などにもよりますから一概には言えませんが、今回工事を依頼された業者に今後の相談を兼ねて確認してみるといいでしょう。ただし、施工費用は業者や使用する素材などによっても異なります。インターネットなどでもさまざまな情報を集めてみるといいでしょう。
ご参考までに、住宅産業協議会では住まいと設備に関するメンテナンススケジュールや費用の目安を紹介しています。これらの情報も参考にしながら、Yさんご家族宅のメンテナンス計画を立てましょう。
大体の目安がわかれば、次回必要となりそうな時期と費用から月々いくら貯めていけばいいか逆算してみましょう。これに固定資産税を含めて「住居費」として家計予算を組み、貯蓄していきましょう。住居費の貯蓄には財形住宅貯蓄を利用されるのもおすすめです。Yさんは一般財形をされていますが、会社が財形住宅も取り扱いしているか確認してみましょう。
財形住宅は利息が非課税になるメリットがありますが、低金利の昨今ですから大きな節税効果を期待できるわけではありません。しかし、給与天引きすることで確実に貯めていけますし、住宅購入・改修など目的外の理由で払い出しをすると過去5年に遡って課税されるため、他の貯蓄との区別もつけやすくなります。
ただし、適格払い出しとなる改修工事にはさまざまな要件がありますから、しっかり確認するようにしてください。また、毎年必要となる固定資産税などは財形住宅とは分けて積み立てておくことが必要です。財形住宅を利用する場合でも、住居費のすべてを財形住宅で積み立てるのは避けましょう。
2年後の仕送り開始に備え、支出を減らす
収支の状況もプラスで毎月の貯蓄もしっかりできている様子ですが、2年後に長男さんの仕送りが始まれば今と同じようには貯蓄できなくなる可能性があります。仕送りの支出が増えても、老後資金や家の修繕費などの必要額は減ることはありません。現在の積立額を減らさないようにするためには、今から少しずつ家計を絞ることに慣れていくことが望まれます。今から家計の見直しをして支出削減にも努めましょう。
まずは、被服費・美容費、交際費などから始めてみるのもおすすめです。子どもの成長にともなって、洋服などにこだわりを持ち、支出が増えるのは仕方のないことかもしれません。だからといって望むままに買ってあげるのは、家計のためにも子どもの将来の金銭感覚のためにも良いこととは思えません。家計見直しの機会に、子どもも含めて支出ルールを作ってみてはいかがでしょうか。
たとえば、「洋服は2カ月あるいは3カ月に1回だけ買う」「金額はいくらまで」と決めるのもいいでしょう。もしくは、お小遣いの額を少し上げる代わりに、洋服を含めてお小遣いのなかでやりくりさせてみるのもいいでしょう。長男が家を出た後、月々の仕送りのなかで生活費をやりくりするようになるときにも役立つはずです。
両親も同様にすれば子どもも見習うかもしれません。家族みんなで予算の中でのやりくりに慣れていくうちに、自然に節約ができるようになるのではないでしょうか。
今回の相談内容と皆さんの家計簿に似ている部分があるようでしたら、ぜひともFPの方のアドバイスを参考にしてみてくださいね。