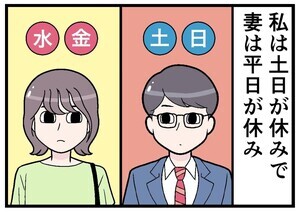◆本記事はプロモーションが含まれています。
【この記事のエキスパート】
保育士ライター/ベビーシッター/家事サポーター:すぎ けいこ
17年の保育園勤務経験と子育て経験があります。現役ベビーシッターとしても活動中。
「子育てはみんなのもの」周りの人に頼りながら子育てするのが、当たり前な世の中になってほしい。パパママが元気になってほしいと願いながら、発信にも尽力しています。保育士資格所持
幼稚園や小学校の遊具としてなじみのある竹馬。遊びながらバランス感覚や体幹が鍛えられるため、子どもから大人まで愛されている遊具です。補助脚を使えば竹馬に乗れない人でも簡単に遊ぶことができます。この記事では、竹馬を選ぶ際のポイントとおすすめの商品をご紹介します。
乗りやすいものを選ぼう!
竹馬の選び方
まずは竹馬の選び方をチェックしていきましょう。保育士ライターのすぎ けいこさんのアドバイスもご紹介しています。自分の使い方にぴったりの竹馬を選ぶために参考にしてみてください。
材質の違いや特徴を知ろう
竹馬は大きくわけて、スチール製と竹製の2種類があります。最近はスチール製が主流となっていますが、2つの違いや特徴を知っておくことで自分にあった使いやすいものが選べるでしょう。
スチール製は丈夫で長持ち
スチール製は、おもに幼稚園や小学校で導入されているタイプの竹馬です。耐久性が高いので壊れにくく、長期間使えるというのが、大きな特徴として挙げられます。
また、足台の高さが固定されていないので、自分にあった高さに調節できます。竹馬の上達に応じて難易度を高めることもできるでしょう。
補助脚がついているタイプの竹馬なら、小さい子どもや竹馬が苦手だという方でも取り組みやすいです。
竹製は子どもでも扱いやすい
竹製の竹馬は、スチール製よりも軽くて扱いやすいものが多いので、小さい子どもでも乗りやすいという特徴があります。また、自然の竹でつくられたものであれば、足台がまっ平らではないものが多いため、より平衡感覚を鍛えられるでしょう。
ただし、竹製はスチール製の竹馬とは異なり、足台の高さを変更することができないものが多いです。また、天然素材を使用しているため、保管の仕方が悪ければカビが生えることも考えられます。購入する場合は、保管方法をきちんと考えることが大切です。
サイズは体格に合わせて選んで!
竹馬は小・中・大などメーカーによって多少の違いはありますが、サイズ別に売られているものがほとんどです。そのため、竹馬に乗る方の体格に合わせて選びましょう。
メーカーによって、目安の身長や体重、対象年齢などを記載しているものが多いです。対象サイズを確認したうえで、長さが調節できるタイプのものを選ぶとよいでしょう。
初心者は補助脚があるものを購入しよう
竹馬は誰もが最初から上手に乗れるわけではありません。小さい子どもやあまり竹馬が得意ではないという方が挑戦するのであれば、補助脚がある竹馬を購入しましょう。
補助脚は、竹馬に乗ったときに重心が後ろになってもしっかりと支えてくれるので、転ばないで練習できます。
また、補助脚が地面につかなくても乗れるようになれば、普通に竹馬に乗れているということがわかります。上達の目安にもしやすいので、モチベーションを高めることもできるでしょう。
保育士ライターがアドバイス
バランス感覚とチャレンジ精神を養うのにぴったり
【エキスパートのコメント】
竹馬は、昔から子どもに親しまれてきた玩具です。今は幼稚園や小学校で取り入れられていることが多いですが、お家での練習や遊びのひとつに取り入れるといいでしょう。竹馬はバランス感覚を養い、体幹も鍛えることができます。
また、少しむずかしい遊びに取り組むことで、チャレンジ精神がやしなわれ成功したときの達成感から自己肯定感もあがります。ぜひ親子の遊びのひとつに取り入れてみましょう。