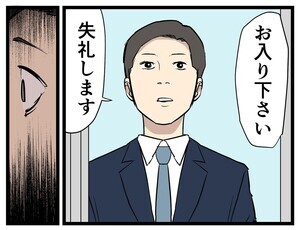◆本記事はプロモーションが含まれています。
【この記事のエキスパート】
IT・家電ライター:河原塚 英信
デジタル系トレンド情報誌の編集者を経て、フリーランスの編集ライターへ。
テレビやデジタルカメラ、スマートフォン、ドローンなどのデジタル製品を中心に執筆。
生活家電専門サイト『家電 Watch』の編集記者でもある。
印刷物や写真を水濡れや汚れなどから守ってくれるラミネートフィルム。A4・A3サイズや100・150ミクロンといった厚み、クロス・マットなど仕上がりのタイプもさまざまです。この記事では、ラミネートフィルムの選び方とおすすめ商品を紹介します。高コスパで人気のアイリスオーヤマもピックアップ。
ラミネートフィルムとは
「ラミネートフィルム」とは、ラミネート加工をするために使われる薄いフィルムのこと。接着剤が塗られた合成樹脂のフィルムで、熱を加えると溶けてのり状になり、冷めると透明なままかたくなります。なかには熱を加えなくても使えるものもあります。
ラミネートフィルムを使って加工すると、紙などの薄い原稿もプラスチックのような仕上がりになり、水や汚れ、折れ曲がってしまうことを防いで長い間きれいな状態を保てます。
また、フィルムの光沢感で色味が鮮やかになり、加工しない状態よりも見栄えがよくなるというメリットもあり、お店のメニュー表やPOPなどでも使用されているので目にすることが多いです。
ラミネートフィルムの選び方
それでは、ラミネートフィルムの基本的な選び方を見ていきましょう。ポイントは下記の5つ。
【1】サイズから選ぶ
【2】フィルムの厚みから選ぶ
【3】仕上がりタイプから選ぶ
【4】メーカーから選ぶ
【5】ラミネーターなしで使えるタイプを選ぶ
上記の5つのポイントをおさえることで、より具体的に欲しい機能を知ることができます。一つひとつ解説していきます。
【1】サイズから選ぶ
ラミネートフィルムを選ぶときは、サイズをかならずチェックしましょう。専用機であるラミネーターを使って加工する場合は、機種によって対応するフィルムサイズが決まっているので注意が必要です。せっかくフィルムを買ったのに、ラミネーターが対応していないサイズで使えなかったということにならないように注意しましょう。
「名刺サイズをラミネートしたいけれど、フィルムは小さいサイズを選ぶべき? 」と悩んだ場合は、ラミネーターに対応している範囲で大きめのサイズを選ぶのがおすすめです。ラミネート加工したものは、よほど厚みのあるものでなければハサミで切ることもできます。一度に複数枚の原稿を加工してカットすれば、作業効率アップにもつながりますよ。
A3サイズ対応のラミネーターであれば、A4サイズや写真用のサイズなども使用できます。ラミネーターがどのサイズまで対応しているかはきちんと確認するようにしましょう。
【2】フィルムの厚みから選ぶ
ラミネートフィルムを選ぶときは、厚みの違いにも着目しましょう。使用するフィルムの厚みによって、加工物の強度や耐久性が変わってきます。厚さの単位はミクロンで、一般的に使用されることが多い100ミクロンが0.1mmの厚さです。
フィルムのサイズと同じで、ラミネーターごとに対応できるフィルム厚が決まっています。かならず確認してから選ぶようにしましょう。
100ミクロン=0.1mm|もっとも一般的な厚み
もっとも一般的なのが100ミクロンです。「ラミネーターの対応する厚みがわからない」「どんな用途で使うかはっきり決まっていない」そんなときは100ミクロンを選んでおけば、ほぼ間違いないでしょう。ベースになる厚さなので、1種類の厚みにしか対応していないお手ごろ価格のラミネーターでも使用可能です。
100ミクロンなら加工後もわりとやわらかめ。ハサミやカッターでかんたんに切れるのもメリットです。複数を一度にラミネートしたものを切り分けたり、安全のために角を落とすのもラクにできます。種類も豊富で値段も手ごろな価格で手に入るので、迷ったらこの厚みを選ぶのがおすすめです。
ただし、耐久性を重視する場合は不向き。すき間から水が入ってきてしまうこともあります。長期保存したい場合や、屋外の掲示物などの加工には、もう少し厚手のタイプを選んだほうがよいでしょう。
150ミクロン=0.15mm|メニューやPOP向き
100ミクロンよりもやや厚手で、ほどよいかたさを感じられます。閲覧用のパンフレットやお店のメニュー表などを加工した場合でも、反りにくく見やすいでしょう。耐久性もあるので、長期保存したい書類や写真を加工したり、屋外での使用にも対応できます。
多少厚みはありますが、こちらもカッターなどで切れるので使い勝手もいいですよ。家庭用のラミネーターでも150ミクロンまで対応しているものもあるので、100ミクロンで物足りない場合は150ミクロンを選ぶとよいでしょう。
250ミクロン=0.25mm|下じきのようなかたさ
屋外で使うものを加工するなら、250ミクロンがおすすめです。耐久性もよく、水の侵入をしっかり防いでくれます。仕上がりはまるでプラスチック製の下じき。ただし、この厚みには対応していないラミネーターも多いので確認してから買うようにしましょう。
350ミクロン=0.35mm|業務用! 看板などに
ラミネートフィルムのなかでもっとも厚いタイプです。プラスチックの板のようなかたい仕上がりで、看板やプレートにも使えます。
一般的な家庭用ラミネーターでは対応できない厚みなので、業務用として使われることが多いでしょう。
【3】仕上がりタイプから選ぶ
ラミネートフィルムには、どんな仕上がりにしたいかによって2タイプ用意されています。目的に合わせたタイプを選びましょう。
グロスタイプ|写真やイラストに
ラミネートフィルムのベーシックなタイプは、ツヤの出る「グロスタイプ」です。パッケージに記載がない場合もこちらのグロスタイプの商品を指します。
光を反射するので、印刷物やイラストを加工すると、加工前の状態に比べてより鮮明で見栄えがよくなるのが特長です。掲示物などもぱっと目を引くようになりますし、手書きのイラストや写真も色鮮やかでうつくしい仕上がりになります。
マットタイプ|メニューやパンフレットに
お店のメニュー表や掲示物などは、ライトが反射すると見づらくなってしまうもの。文字を読ませたいものを加工するときは光の反射をおさえてくれる「マットタイプ」がおすすめです。
また、ツヤを消した落ち着いた雰囲気に仕上げたいときや、加工するものの色味や風合いをそのまま活かしたい場合にも適しています。
【4】メーカーから選ぶ
ラミネートフィルムを選ぶとき、ラミネーター本体と同じメーカーのものを選ぶひとも多いかもしれません。実際に同じメーカーのものを使用するよう本体に注意書きされている場合がありますが、ほとんどの場合で他社メーカーのフィルムでも問題なく使用できます。
ラミネートフィルムは多くのメーカーで取り扱っています。近ごろは100円均一ショップでも見かけるようになりました。しかし、ラミネートフィルムはメーカーによって品質や価格もさまざまです。
格安で販売しているメーカーのなかには、あまり質のよくないものも。きちんとしたメーカーのものを選んだほうが、うまく加工できないといった失敗が減って、結果としてコスパがいいという場合もあります。
【5】ラミネーターなしで使えるタイプを選ぶ
ラミネーターを頻繁に使わないけれど、イベントごとで限定的に使いたいという方もいるでしょう。そんなひとにおすすめなのが、ラミネーターのいらない手貼りタイプのラミネートフィルム。
熱処理が必要ないコールド用のラミネートフィルムなら、ラミネートの機械がなくてもかんたんにラミネート加工ができます。
選び方のポイントはここまで! では実際にエキスパートが選んだ商品は……(続きはこちら)