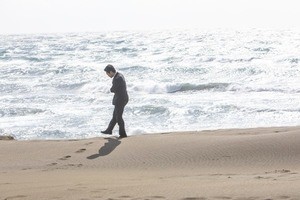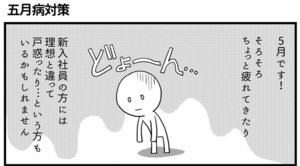新入社員や学生を中心に、大型連休明けに倦怠感や疲労感などの症状が出る「5月病」。ここ数年は、5月病と併せて「6月病」という言葉もよく聞かれるようになった。
実際に5~6月頃は仕事の意欲低下などのトラブルを抱えやすく、早期離職なども増えがち。だが、5月病の認知度は世間的にも高い一方で、多くの人が実践しやすい具体的な対策などは意外と知られていない。
前編では、医学的な側面から「5月病」「6月病」の症状や、なりやすい人の特徴などを紹介した。後編では、これらの症状に苦しむ人が心がけるべき点や、具体的な対策を紹介する。
5月病・6月病と無縁の最強マインドセットはこれだ!
前編で統合医療クリニック「ハタイクリニック」院長・西脇俊二氏から解説があったとおり、特に新入社員の場合は、仕事において自己重要感(承認欲求)と達成感が満たされにくいことが5月病・6月病の原因のひとつとなる。
「仕事で達成感を得る工夫は自分でもできます。先延ばしにしたくなる作業でも、漫然と働かないで『とりあえず20分』と決め、タイマーで計測しながらやる。20分刻みで頑張ると、セロトニンやドーパミンが出やすくなり、次の20分、また次の20分と達成感を味わいやすくなります。人間の集中力が持続するのは約20分、ADHDだともっと短くて5分刻みとか。だんだんこの時間は伸びていきますが、ある程度小刻みにやるのが肝心です。1時間ぶっ通しでやる場合と違い、20分刻みで1時間やると単純計算で3回セロトニンが出ますし、1時間を超えて集中すると脳の疲れが回復しにくくなるというデータもあります」
自己重要感を満たす上では、周りの上司や同僚のフォローも大切。新人の扱い方や褒め方に悩む先輩社員も多いが、以下のようなポイントを踏まえるのがコツだという。
「いい褒め方は相手により異なりますが、言動をよく観察して、大きく『パーソナリティ(人格)重視』・『パフォーマンス(結果)重視』・『ブランド(直感)重視』の3タイプに分けるとわかりやすい。束縛嫌いで自由が好きなブランド重視なら、人前で大げさに、短く簡潔に褒めるのが効果的。結果を大切にするパフォーマンス重視なら、オーバーなお世辞はあまり効かないので、冷静に分析して丁寧に評価してあげるほうがやる気が出る。本物志向のパーソナリティ重視は『あなたしかいない』と言われると仕事のやる気が出やすいタイプ、人柄を絡めて褒めるように」
また、職場環境や当人の完璧主義的な性格による強いストレスが5月病・6月病の原因という指摘もあった。職場環境を変える上では転職もひとつの手段だが、その前に向き合うべき問題について西脇氏はこのようにアドバイスする。
「大学受験も60点くらいが合格ラインで、その先は趣味の世界じゃないですか。仕事も同じで、個人レベルなら50~60点で十分。トヨタはクルマづくりにおける姿勢を“80点主義”と言われることがあります。世界的企業の仕事を超えるつもりなのかと自分に問いかけ、グレーゾーンの気持ち悪さを受け入れて完璧主義をやめましょう」
「職場環境については、ブラックかどうか社会的な基準もありますが、基本的には仕事量も含めて相対的なものです。少々ブラックでも適応できる人もいるし、完全週休2日じゃないとダメという人もいる。完全週休2日制が定着したのはごく最近の話ですが、当人の受け取り方・感じ方によって、実際に病気の症状が出てしまうこともある。認知の問題です」
現在と過去の働き方や業務の質などは、もちろん単純に比較できるものではないが、隣の芝は青く見えるもの。学生時代の友人らと比べすぎて、自分の職場に無用な不満やストレスを抱くことも、たしかにあり得る話かもしれない。
「この場合の比較というのは評価基準が外にありますし、目安が他人次第になってしまうので非常に不安定なんです。適応障害は無理に周りの環境に適応しようとして疲弊した結果、症状が現れます。他人の目ではなく自分で自分をきちんと評価する軸を持つように意識し、むやみに周りの影響を受けないようにする。『発達障害は営業に向いていないんですか』など、職種に関する質問も患者さんから多くいただくのですが、職種よりも自分と職場の雰囲気の相性のほうが大事です」
転職を検討する際は、1年以内の離職率など最低限自分で調べられることは事前に調べ、面接や試用期間を活用しながら職場環境との相性を冷静に見極める姿勢が重要だ。
動画鑑賞、編み物、料理、ゲーム……リフレッシュできるならすべて正解
5月病・6月病対策では、旅行などの非日常を楽しむレジャーでゆっくり休息をとるといったことが一般論として挙げられることも多いが、そもそも、それが難しいから苦労しているという面もある。より多くの人にとって実践しやすいストレス発散法はないのだろうか。
「自律訓練法という瞑想のような方法もおすすめですが、これは少しコツも必要です。漸進的筋弛緩法という方法がより簡単ですね。どちらも筋肉を緩めることで心もリラックスさせるという点は同じです。漸進的筋弛緩法では、手を力いっぱい20秒握ってパッと緩めるという風に、関節を使って筋肉の緊張と弛緩を繰り返し、全身の筋肉を緩めていきます。ストレッチや有酸素運動も効果的です。(220-年齢)×0.8の脈拍で20分以上走ると、β-エンドルフィンという脳内麻薬が出てリラックス状態になります。スピードや距離は関係ありません」
加えて、睡眠の質や食べ物の消化力を向上させ、なおかつ全身運動であるジョギングには、自転車などよりも身体の老廃物が流れやすいという利点があるようだ。
ただ、正直に言うと30分のジョギングはもちろん、ストレッチすら面倒くさいのだが……。
「セロトニンやノルアドレナリンといった脳内神経伝達物質の主原料になるタンパク質と、それを補助するビタミンC・B6、鉄分、亜鉛を摂る食事を意識してください。女性で鉄分が欠乏してうつ気味になる方もいますが、そうしたケースは抗うつ薬を処方する前に鉄分を補うほうが症状は改善します。特に多くの人に不足しがちなのが亜鉛ですが、不足している栄養素はサプリで補うといいでしょう」
また、寝不足になると身体が酸化してしまうが、ビタミンCには身体の酸化を防ぐ働きなどもあり、睡眠障害などにも有効だそうだ。
「昔の友達に会って話を聞いて頷いてもらえれば、それだけで精神的にだいぶ落ち着くんじゃないでしょうか。あとは、我を忘れて集中できるような、自分が夢中になれることをやる。お笑いの動画を見るとか、編み物や料理をするとか、読書でもゲームでもリフレッシュできるならアリ。あまり漫然とやるのでなければ。どんなくだらないことでも自分が集中してリラックスできることなら、それでいいんです」
こうしたポイントを踏まえ、限られた自分の時間を有効に使って日々を乗り切ろう。

|
監修者
西脇俊二 (にしわき しゅんじ)
統合医療クリニック「ハタイクリニック」 院長
ハタイクリニックの院長として診療をしながら、メディア出演やドラマなどの医療監修、執筆など多数の分野で活躍中。著書に『自分の「人間関係がうまくいかない」を治した精神科医の方法』(ワニブックス)、『コミックエッセイ アスペルガー症候群との上手なつきあい方入門』(宝島社)など。YouTubeチャンネルの運営も行っている。